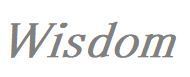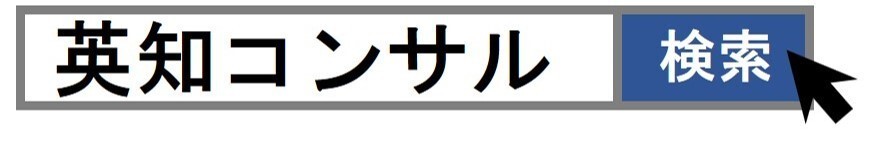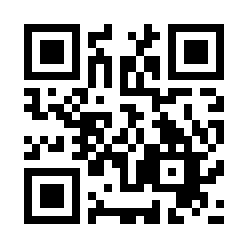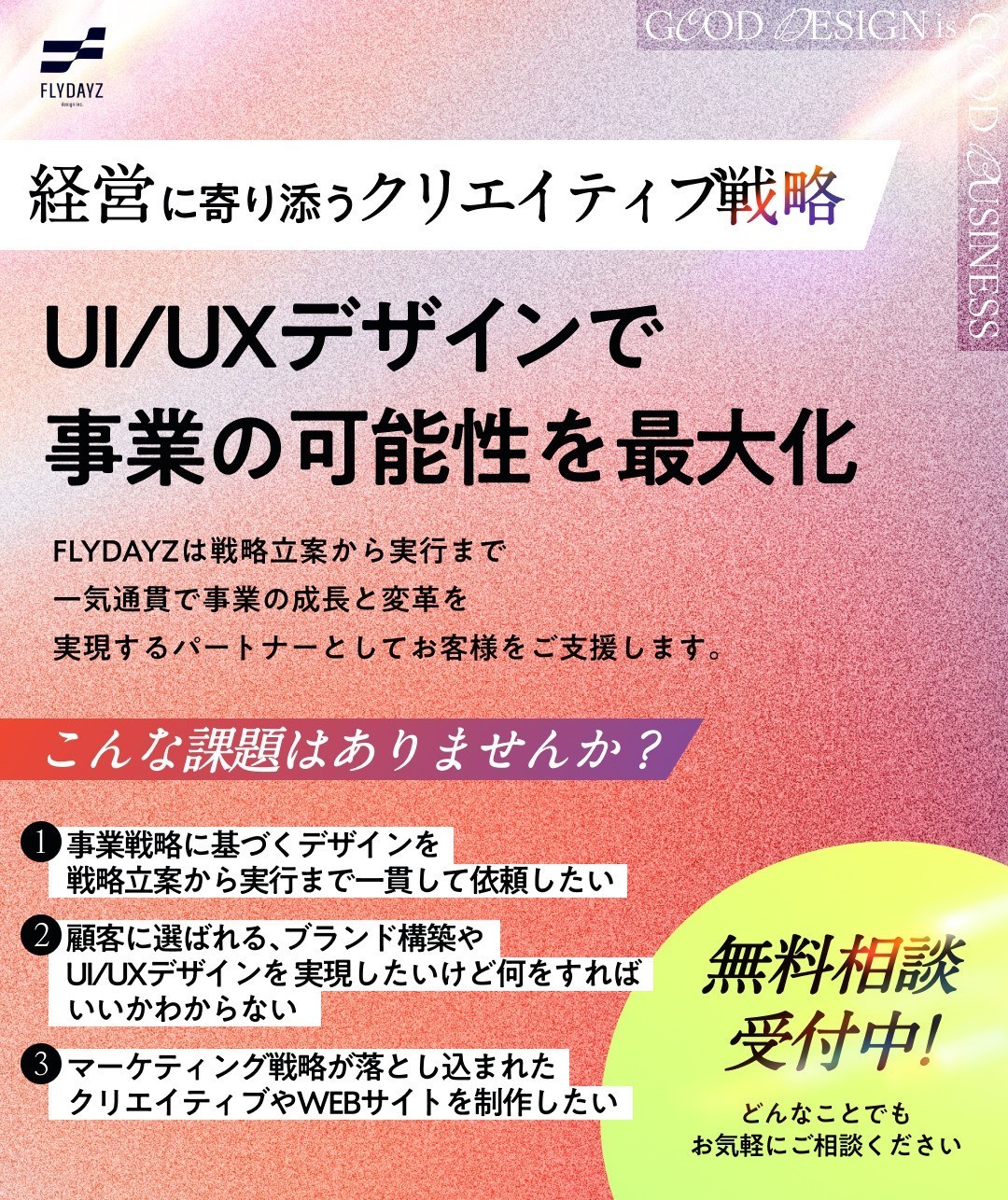中小企業・小規模事業者の経営コンサルティングは東京の英知コンサルティング株式会社(全国対応)
最終更新日 2024年07月23日
経営者・従業員向けファイナンシャルプランナー相談
経営者・従業員向けファイナンシャルプランナー相談は東京の英知コンサルティング株式会社へ。
「ライフプラン提案書」に強い完全独立系のFP事務所です。経営者・従業員さまとご家族さまが経済的に豊かな人生を実現できるよう、FPがご支援いたします。
FPコンサルティング

経営者・従業員とそのご家族様が経済的に豊かな人生を
実現できるようご支援いたします
FPコンサルティング 主なメニュー
| No. | サービスメニュー (例) | 人気度 |
|---|---|---|
| 8001 | ライフプラン提案書作成 | ★★★★★ |
| 8002 | 教育資金プラン提案書作成 | ★★★★★ |
| 8003 | 住宅資金プラン提案書作成 | ★★★★★ |
| 8004 | 老後資金プラン提案書作成 | ★★★★★ |
| 8005 | 家計診断 | ★★★★★ |
| 8006 | 生命保険診断(保険の販売は一切行っておりません) | ★★★★★ |
| 8007 | 公的年金診断 | ★★★★★ |
| 8008 | 金融資産投資・運用相談 | ★★★★★ |
| 8009 | 不動産投資相談 | ★★★★★ |
| 8010 | 相続相談 | ★★★★★ |
| 8011 | iDeCo・NISA 投資運用相談 | ★★★★★ |
| 8012 | 終活相談 | ★★★★★ |
| 8013 | 税金相談 | ★★★★★ |
| 8014 | 不動産売買相談 | ★★★★★ |
| 8015 | 住宅ローン相談 | ★★★★★ |

FPの限界
独占専門資格ではないので、誰でもFPと名乗れます
ファイナンシャル・プランニング業務は法的な独占資格ではないため、資格を持っているかどうかにかかわらず、誰でもFP(ファイナンシャル・プランナー)という職種名を称して業務を行うことができます。
独占専門資格との関係
FPの業務を大別すると、次の6分野に区分されます。
| FP6分野 | 個別・具体的な相談・実務を行うために必要な資格 |
| ①ライフプランニングと資金計画 | 社会保険労務士 |
| ②リスク管理(保険) | 生命保険募集人・損害保険募集人 |
| ③金融資産運用 | 公認会計士・証券アナリスト・一種証券外務員 |
| ④タックスプランニング(税金) | 税理士 |
| ⑤不動産 | 不動産鑑定士・一級建築士・宅地建物取引士 |
| ⑥法律相談・相続・事業承継 | 弁護士・司法書士 |
業務の制約
個別・具体的な相談・実務を行うために必要な資格を保有していないFPは、顧客の「個別・具体的な相談」や「税額の計算」は、税理士法違反となるため無償であっても行うことはできません。勿論これは、顧客保護のための「倫理規程」です。
英知FP事務所は、65種類の資格を保有する士業集団ですので、顧客の全ての、個別具体的なご相談および実務をお受けできる、我が国で唯一のFP事務所です。
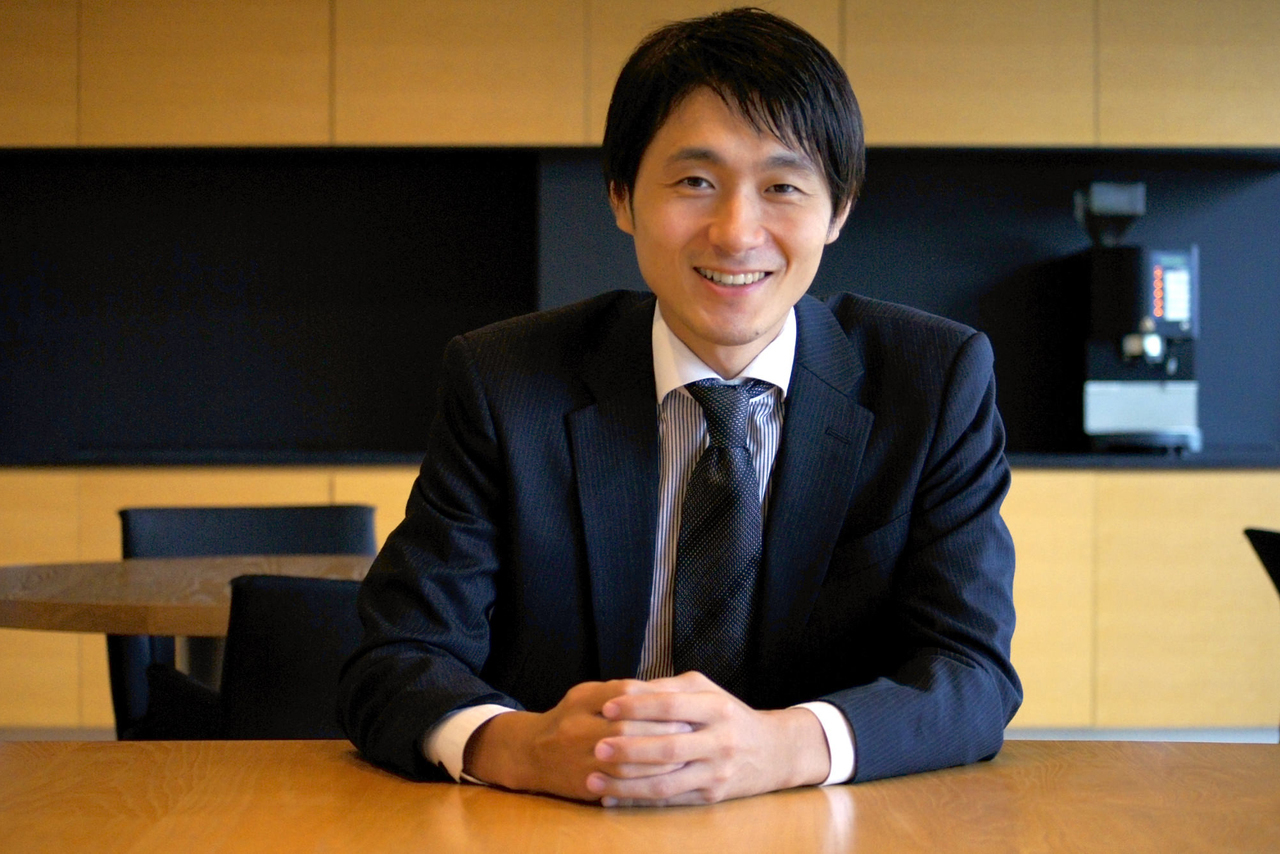
FPの役割
相談者の夢を叶えるファイナンシャル・プランナニングの専門家
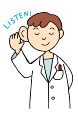
人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、
経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。
ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。
これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。
FPは「暮らしとお金」に関する幅広い相談にお応えします
FPは、相談者の夢や目標を達成するために、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など、あらゆるデータを集めて、現状を分析します。
そして、相談者の立場や、ライフイベントを考慮したうえで、長期的かつ総合的な視点でさまざまなアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助します。
また、必要に応じて、弁護士や税理士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながらファイナンシャル・プランニングを行います。

「お金の悩み」は、皆同じだった
- 生活が苦しい
- 貯蓄ができない
- 教育資金が不安
- 住宅資金の返済が不安
- 老後資金が不安
- 生命保険の額が適切か不安
- 年金だけで生活できるか不安
「ライフプラン提案書」の作成・実行支援に特化
「ライフプラン提案書」の作成・実行支援に特化した、英知コンサルティング株式会社に、ご用命ください。
老後破綻、高齢世帯の生活保護の実態
厚生労働省の直近の資料によると、2021年10月時点の生活保護受給世帯は過去最多の164万世帯、受給者数は214万人で、国民の約50人に1人が「生活保護」受給している計算になります。
世帯別では、65歳以上の高齢者世帯が90万世帯と全体の半数以上を占めています。第二・第三の人生を豊かに暮らすためには、計画・持続的にFPに指導を求める必要があります。
「人生の3大資金」
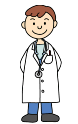
人生の3大資金とは
「教育資金」「住宅資金」「老後資金」
結婚、子どもの誕生、教育資金、住宅資金、老後資金、年金、海外旅行など、自分や家族に今後起こり得る大きな出来事で、その際、資金も必要になるものをライフイベントといいます。
ライフイベントの中でも、「教育資金」「住宅資金」「老後資金」の3つは必要な資金が大きく、「人生の3大資金」と呼びます。これに「生命保険」を加えて「人生の4大資金」と呼びます。
大きな資金が必要ということは、それだけ準備にも時間がかかります。必要な時期はある程度決まっていますから、早めの準備が肝心です。
お金の悩み BEST3

第3位 教育資金
幼稚園~高等学校の学習費総額 オール公立500万円、オール私立1,700万円
子ども一人当たりの教育費は「親がどのような教育を受けさせたいか」や「こどもが進学したい学校」などによって大きく変わりますが、希望する教育を受けさせるためにはある程度の資金を準備しておく必要があります。
子ども一人が幼稚園から大学卒業までに教育費はいくら位かかるのでしょう。先ず、幼稚園(3歳)~高等学校(3学年)にかかる教育費を「令和3年度子供の学習費調査結果の概要」(文部科学省)から見ていきましょう。
幼稚園は公立約23万円・私立約49万円、小学校は公立約31万円・私立約142万円、中学校は公立約45万円・私立約130万円、高等学校(全日制)は公立約39万円・私立約97万円かかっています。
「令和3年度学校基本調査報告書」(文部科学省)によると、生徒数全体に占める私立の割合は、幼稚園82%、小学校1.2%、中学校7.1%、高等学校(全日制)31.2%ですので、幼稚園のみ私立、小学校から高等学校は公立というコースが多いのではないでしょうか。
幼稚園のみ私立の場合の教育費総額は約580万円、幼稚園と高等学校が私立の場合では約753万円になります。因みに、オール公立では約500万円、オール私立では約1,700万円になります。
【幼稚園~高等学校にかかる学習費総額】
| 分 類 | 公 立 | 私 立 | 公立と私立の差 |
|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 23万100円 | 48万7427円 | 公立の2.1倍 |
| 小学校 | 30万5807円 | 142万2357円 | 公立の4.7倍 |
| 中学校 | 45万340円 | 129万5156円 | 公立の2.9倍 |
| 高等学校 | 38万6439円 | 96万6816円 | 公立の2.5倍 |
【大学の入学金・授業料・施設設備費】
| 分 類 | 入学金 | 授業料/年 | 施設維持費/年 |
|---|---|---|---|
| 国立大学 | 28万2000円 | 53万5800円 | - |
| 公立大学 | 39万7721円 | 53万7857円 | - |
| 私立文系 | 24万6749円 | 74万2478円 | 16万0019円 |
| 私立理系 | 26万5595円 | 104万3212円 | 18万7236円 |
| 私立医歯系 | 103万6391円 | 276万4631円 | 86万3538円 |
| 私立その他の学部 | 27万1318円 | 94万6556円 | 24万4073円 |
※自宅外通学の場合は、家賃や生活費等の仕送りが別途必要になりますので、少し多めに準備しておきたいものです。

第2位 住宅資金
住宅取得資金は購入物件の30%
「2020年度フラット35利用者調査」(住宅金融支援機構)によると、全国の平均購入価格は、注文住宅3015万円、土地付注文住宅3637万円、建売住宅3551万円、マンション3862万円でした。2018年度に比べ注文住宅が1.6%、土地付き注文住宅は2.1%、マンションは2.8%それぞれ上昇しています。
住宅取得資金は、一般に購入対象物件の30%と言われますが、頭金に20%、諸経費(税金や引っ越し費用等)に10%を充当します。
前出の「フラット35利用者調査」では手持ち資金の割合は、建売住宅15%程度、マンション22%程度、注文住宅22%程度、土地付き注文住宅12%程度です。建売住宅と土地付き注文住宅の購入者は厳しい返済になりそうです。
住宅ローンは20~35年の長期にわたり返済し続けるので、教育費や老後の生活費等とバッティングする人が少なくありません。
頭金が少ないと返済総額が多額になる、あるいは年金暮らしになっても返済しなければならないなど、あとあと生活を圧迫する多くの問題が起こりがちです。
「令和2年住宅・土地統計調査(速報集計)結果の要約」(総務省)では、全国の空き家率は13.5%(前年より0.4%増)で毎年伸びています。
住宅ローン破綻も増えており、住宅は資産ではなく負債になる可能性があることを肝に銘じ、住宅取得資金として購入物件の30%、少なくとも20%を準備しましょう。

第1位 老後資金
人生90年時代が到来
老後資金計画で先ず調べるのは自分の平均余命です。平成25年簡易生命表によると、65歳男性の平均余命は19.08年、女性は23.97年です。
ここで問題です。0歳の人10万人が65歳になったとき何人生存しているでしょうか。答えは、男性8万8041人、女性9万3933人。ほとんどの人が生存しています。
その後死亡数がふえ、男性は83歳、女性は90歳でほぼ半減し、3分の1 になるのは男性88歳、女性93歳です。男性は人生90年、女性は95年時代と考えて老後資金を準備する必要があるかも知れません。
老後資金の計算手順
老後の生活資金は、夫婦共に平均余命まで生きると仮定し、リタイア後の夫婦時代と夫を見送った後の妻一人時代の生活を賄う資金です。食費や光熱費、通信費、交通費、交際費、税金、社会保険料など日々の暮らしを維持するために必要なお金ですから、これは確実に準備したいものです。
計算式は次の通りです。
(1)夫婦時代の生活費=1年間の生活費×夫の平均余命
(2)妻一人時代の生活費=1年間の生活費×70~80%×(妻の平均余命-夫の平均余命)
老後の生活資金=(1)+(2)
*(1)の場合は、「1年間の生活費=現役時代の生活費×80%」とします。
「令和2年 家計調査報告(家計収支編)」(総務省)によると、夫65歳以上・妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯の1か月の支出は27万2455円(消費支出24万2598円、非消費支出2万9857円)です。
では、夫65歳(平均余命19.08年)、妻60歳(平均余命28.48年)の夫婦世帯の老後のモデル生活資金を計算してみましょう。
夫婦時代の生活費=27万2455円×12ヵ月×20年=約6539万円
妻一人時代の生活費=27万2455円×70%×12ヵ月×(29年-20年)=約2060万円
老後の生活資金=約6539万円+約2060万円=約8599万円
生活資金以外に、レジャー資金や家屋のリフォーム等維持管理費用、こどもへの援助資金、介護資金、葬式費用などの予備費も必要です。
これらはライフスタイルや健康状態、家族関係などによって異なりますが、一般に2000万~3000万円と想定する人が多いようです。
前出の夫婦の老後資金は、生活資金を約8599万円、予備費を2000万円とすると約1億円になります。一般に「老後資金は1億円」というのが妥当な数字であるとお分かりになるでしょう。
と言っても老後資金として1億円全額を準備する必要はありません。リタイア以降の収入、例えば退職金や公的年金や企業年金等、で不足する分を準備すればいいのです。
老後資金3000万円の妥当性は?
前出の家計調査によると、夫65歳以上妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯の公的年金収入は20万309円です。一生涯に夫婦で受給する公的年金を計算してみましょう。
夫婦時代の公的年金収入=20万309円×12か月×20年=約4,807万円
妻一人時代の公的年金収入=約12万円×12ヵ月×(29年-20年)=約1,296万円
夫婦が一生涯に受給する公的年金=約4807万円+約1296万円=約6,103万円
*妻一人時代の年金額は、本人の公的年金と遺族年金の合計額
では、老後資金として準備すべき金額はいくらになるのでしょう。それは、「老後の生活費+予備費-(退職金+夫婦で受給する公的年金(+企業年金))」で計算します。
前出の夫婦が準備すべき老後資金は、「老後の生活費+予備費-(退職金+夫婦で一生涯に受給する公的年金)=約8599万円+2,000万円-(約2,300万円+約6,103万円)=約2,196万円」になります。
一般に「老後資金として3,000万円を準備しよう」というのは60歳定年を想定していた頃の金額です。原則65歳まで継続雇用となった現在は、60歳から64歳の無年金期間の生活費の準備が不要ですので、老後の準備資金は1,500万円程度少なくなりそうです。
反面、マクロ経済スライドの実施により、将来の年金支給額の価値は現在より低くなる可能性があるので、それを考慮すると、はやり3,000万円程度は準備する方がいいような気もします。
教育費や住宅取得費用、老後の生活費は数千万円の単位で、準備期間は30歳~65歳の35年間に集中します。夢や希望は膨らみますが、現役時代の収入は限られています。
3大出費のバランスをよ~く考えて計画しないと、人生の後半で「しまった!」という事態になりかねません。アバウトなキャッシュフロー表を作成して資産管理を行うことおすすめします。
住宅は資産ではなく負債になる可能性があることを肝に銘じ、住宅取得資金として購入物件の30%、少なくとも20%を準備しましょう。

英知コンサルティングの特徴
「財産形成と豊かな暮らし」の実現をご支援
「ライフプラン」の相談と、「ライフプラン提案書」の作成および実行・支援で「財産形成と豊かな暮らし」の実現をお手伝いいたします。
遅くとも「婚約」したら、「顧問FP」を持つことを強く薦めております。
「豊かな老後」の実現をご支援
「人生100年時代」、「第三の人生」を経済的ゆとりと、生き甲斐を両立させる人生設計をご提案いたします!
「年金制度」の破たんにより「死亡リスクより、長生きをしてしまうリスク」の方が高くなっております。「年金」に頼らない老後の資金設計で「豊かな老後」を実現させます。
国内唯一の「完全独立型FP事務所」
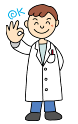
国内で唯一、保険・金融商品の販売、および投資用不
動産の斡旋を一切行っていない「完全独立型のFP事務所」です。
皆様は「FP」と聞いて、何をイメージされるでしょうか?
多くの方は「保険外交員」や「保険代理店」をイメージされるのではないでしょうか。
実際、「独立系」と名乗るFPの99%は、保険会社の代理店手数料など、提携している事業者からの収入が収益の柱になっています。
このようなFPが、果たして顧客に中立・公正なアドバイスをしてくれるでしょうか?
特に「無料相談」を行っているFPは要注意です。何故、大多数のFPが、保険や金融商品、不動産の勧誘・仲介」を行うのでしょうか。
その理由は、お客様から頂く報酬の何十倍、何百倍もの「手数料収入」があるからです。このようなFPはお客様の利益よりも、保険会社、金融機関、不動産会社等の利益を優先します。
英知FP事務所では「保険や金融商品の販売、および不動産の仲介」は一切、行っておりません。高い専門知識を持って中立・公正な立場に徹することを最優先としております。
そのため、英知コンサルティングは、商品販売は一切行わない「コンサルティングに特化」した、国内で最も誠実なFP事務所です。
専門知識が豊富なプロフェッショナルFP集団です
当社のコンサルタントは、公認会計士、証券アナリスト、社会保険労務士など65の難関資格試験に合格している一流の戦略コンサルタントです。専門分野の知識を駆使し、最高の「智慧」をご提供いたします。

FPは「家計のホームドクター」
家計のホームドクター
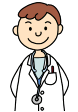
人はそれぞれ生き方や考え方が違いますし、人生に対
する夢や希望も千差万別です。
もちろん家族や生活する環境・経済基盤も違います。しかし、どのような生き方をするにしても金銭的な問題は避けては通れません。
税金や公共料金・年金・教育資金・住宅ローン・生命保険・損害保険・不動産など暮らしの中の金融システムは益々複雑を極め、「何が最良」で「どれが最善」なのかを理解して選択をすることは非常に難しい状況になってきています。
そこで生まれたのが家計に関する幅広い知識を備えた「ファイナンシャル・プランナー」です。つまり個人や家族が安心して暮らすために家計に関する金銭的な裏付け作りをアドバイスする「家計のホームドクター」のようなものです。
「自分や家族の暮らしを大切にする」アメリカでは職業別電話帳にも「Financial Consultant」「Financial Adviser」という職業の分類があり、40~50万人がFPとして働いており、多くの個人や家族の暮らしを支えています。
FPは「暮らしとお金」の幅広いご相談に対応致します
FPとは、相談者の夢や目標を達成するために、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など、あらゆるデータを集めて、現状を分析します。
そして、相談者の立場や、ライフイベントを考慮したうえで、長期的かつ総合的な視点でさまざまなアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助します。
更に、英知コンサルティング株式会社では。弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士など、65資格の資格者が在席しておりますので、ワンストップのサービスをご提供させていただいております。
FP先進国のアメリカでは、顧問FPを持つのがステイタス
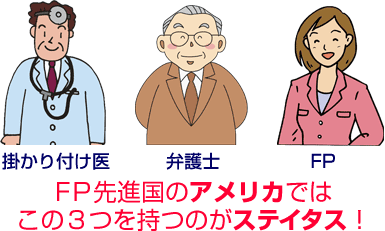
人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。
ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い専門知識が必要になります。
これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。

「第三の人生」の生き方
「第三の人生」は「第三の青春」
「愚者にとって、老年は冬である。賢者にとって、老年は黄金期となる」 という格言があります。
「生老病死」の四苦そのものが、わが生命を荘厳する宝に変わるのです。これほど、素晴らしく、有り難いことがが、他にありますでしょうか。
「しかし残念なことに、『死』 という根本問題から目を背けた現代社会は、そうした 『老い』 のもつ黄金の価値まで見失ってしまったように感じます」と戒められています。
賢者に学ぶ
あるエッセー本が話題となっている。著者は執筆当時、92歳だった作家の佐藤愛子氏。「もう『進歩』はこのへんでいい。更に文明を進歩させる必要はない。進歩が必要だとしたら、それは人間の精神力である」(『九十歳。何がめでたい』小学館)などと鋭い論評は健在である。
佐藤氏は88歳で自身最後の長編小説を書き上げ、「これからは、のんびりと老後を」と過ごしていたという。しかし、「ハリ」のない毎日を送るうちに、老人性のうつ病になりかける。
しばらくして、エッセー連載を持ち掛けられ、仕事を再開。すると、体調も回復。「人間は『のんびりしよう』なんて考えてはダメだということが、九十歳を過ぎてよくわかりました」と、巻末でつづっている。
「人生100年時代」ともいわれる現代日本。この言葉は、今年の「ユーキャン新語・流行語大賞」にもノミネートされた。医療技術の発達や社会福祉制度の充実により、多くの人が長寿を手に入れられるようになった今、「いかに生きるか”“何のために生きるか」といった人生の目的観に、ますます焦点が当てられるようになった。
加齢による脳や体の衰えなどで、どうしてもできないことは増えていく。だが、長年の人生経験は何物にも代え難い。定年退職後に、経験や技術、人脈、趣味などを生かして「シニア起業」に踏み出す人もいる。
いつまでも「生涯青春」の心意気で、魅力的に年を重ねる「賢者」から、「輝いて老いる」生き方を学んでいきたい。
「価値創造」の生き方
長寿社会とは、競争よりも協調が、効率よりもゆとりが、物の豊かさよりも心の豊かさが、求められる時代です。
自分が 「してもらう」 のではなく、わずかでもいい、自分には 「何ができるのか」 を考える時代です。いくつになっても、わが身を律しながら、貢献の道を探っていく。それが、「価値創造」 の生き方です。
「人生の最高の誉れは、人のために祈り、動くことで、自分も幸福になる。これほどの価値ある人生はないのです」

「長生き」の秘訣
「長生き」 の秘訣は何か、一般的に、心のもち方が大きく関係するといわれていますので、その項目を取り上げてみます。
①「くよくよしない」 ことが大切とされる。
②「目標をもって生きる」 ことである。
③「ユーモア、笑いを忘れない」 ことも大切である。
④「何らかの仕事、使命に励む」 ことである。
「精神的な努力」を止めてはいけない!
ハーバード大学のガルブレイス博士は 「健康法」を、こういわれました。
「何よりも大事なことは――朝起きた時、『きょう一日計画が決まっていない、考えていない』 といったことが、ないようにすることです!」。朝を 「さあ、きょうも!」 と元気に出発することである。
博士は言われた。
「年配者の最大の誤りは、仕事から引退してしまうことである。やるべき仕事がなくなれば 『肉体的努力』 と 『精神的な努力』 を、しなくなってしまう。
とくに 『精神的な努力』 をやめることは、非常によくありません」
「生きる」ということは、生涯かけて学ぶこと
アメリカの女流画家、グランマ・モーゼスの生き方を通して指導されています。
人生の年輪が増すごとに、創造の輝きを一段と強く放ちゆく人には、“老い” はない。それは、常に人生の 「現役」 であることを、自負しているからではないだろうか。
「生きる」 ということは、生涯かけて学ぶことである。また 「人生とは、私たち自身が創るもの」 なのである。
そのスタートが何歳であっても遅くないこと、さらに、それには学歴などは要らないことも、モーゼスおばあさんは教えている。
私はそこに、たぐいまれなる 「自律」 と 「自立」 の魂をみる。自らを律しつつ、自ら立つ。このとき人は、人生という名の舞台の上で、いつも “主役” を演じ続けることができるにちがいない。
「人生とは、私たち自身が創るもの である。そのスタートが何歳であっても遅くない。また、それには学歴などは要りません。」


英知コンサルティングの実績
実績
563件
料金
ご面談・ご相談の上、最適なプランとお見積りをご提案いたします。
一緒にご覧いただいているページ
ご相談・お問い合わせはこちら(無料)
コンサルティングのご依頼や、詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。ご相談は勿論、無料です。
お問い合せフォームでのお問合せは24時間受け付けております。
サイドメニュー
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー
Executive Consultant
清水 一郎
-------------------------------------
<専門分野>
経営再建、企業再生、経営戦略、営業戦略、マーケティング、間接部門改革、法務、財務、金融、会計、税務、監査、事業承継、IPO、資産運用、不動産、組織構築、人事制度、人事評価制度、目標管理制度
-------------------------------------