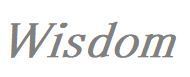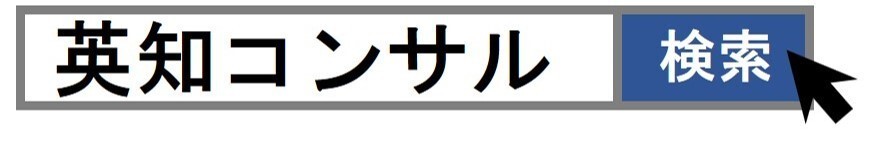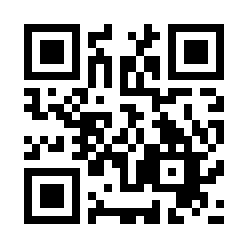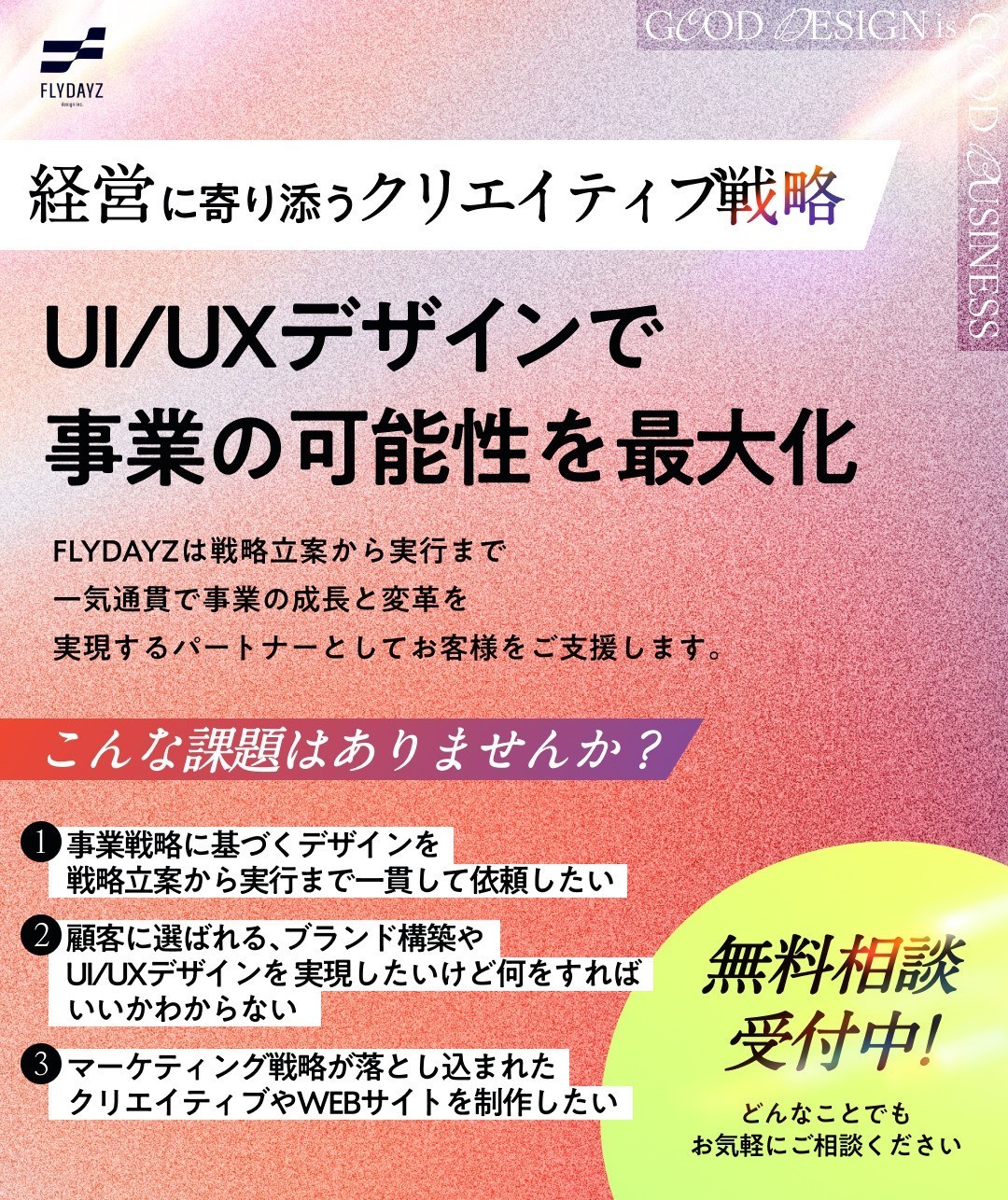中小企業・小規模事業者の経営コンサルティングは東京の英知コンサルティング株式会社(全国対応)
最終更新日 2024年08月17日
小規模M&Aコンサル
小規模M&Aなら東京の英知コンサルティング株式会社へ。当社では、中小企業経営者の皆さまのニーズに合わせたM&A支援を行っています。
当社の強み
M&Aは、他社との経営統合や新規事業の買収など、多様な形態で行われます。しかし、M&Aは一朝一夕で実現するものではありません。
計画段階から実行までのプロセスは複雑であり、専門的な知識や経験が求められます。そこで、私たち経営コンサルティングチームがお手伝いいたします。
そす。私たちのコンサルタントは、豊富な経験と専門知識を持つプロフェッショナルばかりです。あなたの事業に最適なM&A戦略を策定し、実現に向けたプロセス全体をサポートいたします。
まず、私たちが行うのは事前の調査と分析です。あなたの事業や業界の特性を理解し、現状の課題や機会を明確化します。
また、M&Aの目的や戦略を共有し、目指す成果を具体化します。これにより、戦略的な方向性を確立し、具体的な行動計画を策定することができます。
次に、私たちは優れたネットワークと豊富な情報源を活用して、適切なターゲット企業を特定します。業界動向や競合情報を綿密に分析し、相性の良い企業を見つけ出します。
その後、交渉やデューデリジェンスなど、M&Aプロセスの各段階でサポートいたします。私たちの経験豊かなチームが、あなたの代表として交渉を進め、最大の利益を追求します。
また、M&A後の統合プロセスにおいても、私たちはあなたを支援します。
文化の違いや組織の調整など、統合に伴う課題を早期に発見し、解決策を提案します。統合後のシナジー効果を最大限に引き出し、事業の成長を促進するお手伝いをいたします。
私たちのM&Aコンサルティングは、中小企業経営者の皆様の成功に向けた一助となることでしょう。
あなたのビジョンを実現し、競争力を強化するために、ぜひ私たちの経験と専門知識をご活用ください。当社のコンサルタントが最善のアドバイスとサポートを提供いたします。

M&Aコンサルティングとは何か
M&Aコンサルティングは、企業の買収や合併に関する専門的なアドバイスを提供するサービスです。経営者にとって、M&Aは企業成長や業界リーダーシップを確立するための貴重な機会であり、
しかし同時に非常に複雑で、失敗すれば大きな損失につながるリスクもあるということを理解しています。
弊社は、長年にわたりM&Aコンサルティングに携わってきました。
私たちは、豊富な経験と幅広い業界知識を活かして、経営者の方々がより戦略的かつ効果的なM&Aを実施できるよう支援しています。
M&Aコンサルティングの重要性を考えると、以下の理由から経営者の方々に対してこのサービスを積極的に検討していただきたいと考えています。
1.業界におけるリーダーシップを確立するために必要な成長機会を
提供する
M&Aは、競合他社を買収したり、新規市場に参入したりすることで、業界におけるリーダーシップを確立するための貴重な機会を提供します。
しかしながら、その際には複雑な戦略と財務計画が必要であり、このようなプロセスに関する知識や経験が不足している場合は、失敗する可能性があります。
弊社は、業界のリーダーシップを確立するために必要なM&Aの成功に必要な知識やスキルを持っています。
私たちは、経営者の方々が成長の機会を最大限に活用し、業界におけるリーダーシップを確立するための貴重なアドバイザーとしての役割を果たすことができます。
2.複雑なプロセスを支援する
M&Aは非常に複雑なプロセスであり、実行するには多くの時間と資源を要します。
また、M&Aには膨大な量の情報が必要であり、その情報を正確に評価する必要があります。さらに、法的、財務、税務、および人事面での問題に対処する必要があります。
弊社は、M&Aにおけるこれらの課題に対応するために、専門知識を持ったチームを構築しています。
私たちは、経営者の方々に代わって、複雑なプロセスを支援し、重要な問題に対処し、優れた成果を達成するためのプロセス全体を管理することができます。
3.企業価値の最大化を支援する
M&Aには、企業価値を最大化するための戦略的な判断が必要です。このため、経営者は、M&Aを行う前に、自社の目標や優先事項、および投資家の期待についてよく理解する必要があります。
弊社は、企業価値の最大化に向けて戦略的な判断を支援するために、幅広い分野での専門知識を持っています。
私たちは、経営者の方々に対して、自社の目標や優先事項に応じたM&Aの戦略的な計画を提供し、企業価値を最大化するための最適な方法を提示することができます。
4.失敗リスクを最小限に抑える
M&Aには、失敗するリスクがつきものです。失敗すると、企業にとって非常に高いコストがかかります。これは、失敗したM&Aによって、企業価値が低下し、投資家の信頼が失われ、経営者の信頼性が低下するためです。
弊社は、M&Aの失敗リスクを最小限に抑えるために、経験と専門知識を活かして、経営者の方々にアドバイスを提供しています。
私たちは、経営者の方々がM&Aに関するリスクを正確に評価し、失敗リスクを最小限に抑えるための戦略を提供することができます。
結論として、M&Aコンサルティングは、企業成長や業界リーダーシップを確立するために重要なプロセスです。
しかし、M&Aは複雑でリスクが高いプロセスでもあります。
弊社は、経営者の方々に対して、M&Aのプロセスに関する専門知識やアドバイスを提供することで、リスクを最小限に抑え、優れた成果を達成するための支援を行っています。
弊社のM&Aコンサルティングは、経営者の方々が自社の目標や優先事項に合わせた最適な戦略を立案し、優れた成果を達成するためのプロセスをサポートします。
私たちは、豊富な経験と専門知識を持つチームを構築し、経営者の方々がM&Aに関するリスクを正確に評価し、最適な戦略を実行することができるように支援します。

サービス内容
・M&A戦略の策定
・企業評価の実施
・法務、財務、税務、人事面でのデューデリジェンスの支援
・交渉、契約書の作成、およびクロージング支援
弊社は、経営者の方々がM&Aによって企業価値を最大化し、業界リーダーシップを確立することを支援します。
私たちは、経験豊富なチームを構築し、経営者の方々がM&Aに関するリスクを最小限に抑え、最適な戦略を実行することができるように支援します。
弊社のM&Aコンサルティングに関する詳細は、弊社のホームページをご覧ください。私たちは、経営者の方々が成功するためのサポートを提供することをお約束します。
また、弊社のM&Aコンサルティングは、M&Aに詳しくない経営者の方々にも分かりやすく、丁寧な説明を行うことを心がけています。
M&Aに関するプロセスや用語については、分かりにくい場合が多いため、私たちは、経営者の方々が理解しやすいように、わかりやすく説明することに力を入れています。
弊社のM&Aコンサルティングは、経営者の方々にとって、重要な投資になることがあります。
私たちは、経営者の方々の利益を最優先に考え、リスクを最小限に抑え、最適な成果を達成するための戦略を提供します。
私たちは、経営者の方々がM&Aによって企業価値を最大化し、事業拡大を実現するためのサポートを提供することをお約束します。
弊社のM&Aコンサルティングは、多くの企業から信頼を得ています。
私たちは、企業の規模や業界に関係なく、経営者の方々がM&Aに関するリスクを正確に評価し、最適な戦略を実行することができるように支援します。
最後に、弊社のM&Aコンサルティングにご興味をお持ちいただいた経営者の方々には、是非、お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。
私たちは、経営者の方々の成功に貢献することができるよう、全力でサポートを提供いたします。
M&Aは、企業にとって大きなチャンスであり、同時に大きなリスクを伴うこともあります。
弊社のM&Aコンサルティングでは、経験豊富なコンサルタントが、M&Aに関する様々な課題を解決するために、総合的かつ戦略的なアドバイスを提供しています。
私たちは、M&Aに関するあらゆる分野に精通しており、経験豊富な専門家のチームで構成されています。
私たちは、お客様にとって最適な戦略を策定するために、市場動向やトレンドを常に把握し、最新の情報や分析を提供しています。

支援内容
1.M&A戦略の策定
弊社のコンサルタントは、企業の戦略やビジネスモデルを分析し、M&Aによって企業が達成したい目的や戦略を明確化します。その上で、最適なM&A戦略を策定し、実行するための支援を行います。
2.デューデリジェンスの実施
M&Aを進める上で欠かせないデューデリジェンスについて、私たちは、厳密で緻密な実施を心がけています。
私たちは、経営者の方々に代わって、財務、法律、人事、技術など、様々な領域においてデューデリジェンスを実施し、リスクを最小限に抑えるための支援を行います。
3.価格交渉の支援
M&Aにおいては、価格交渉が非常に重要です。弊社のコンサルタントは、企業価値を正確に評価し、最適な価格交渉を行うために支援を行います。
私たちは、価格交渉において、お客様にとって最適な条件を実現するために尽力します。
4.M&A後の統合支援
M&A後には、企業の統合が必要となります。私たちは、M&A後の統合に向けて、企業間での連携や意思決定プロセスの改善など、様々な面で支援を行います。
また、M&A後の成功のためには、統合後の文化やビジネスモデルの調整が必要となります。弊社のコンサルタントは、このような課題にも取り組み、M&A後の企業の成長を支援します。
弊社のM&Aコンサルティングは、経験豊富なコンサルタントのチームによって、お客様のニーズに合わせたサービスを提供します。
M&Aに詳しくない経営者の方でも、弊社のコンサルタントが、分かりやすく丁寧に説明し、M&Aの成功に向けて、最適な支援を行います。
弊社は、M&Aの分野において多くの実績を持ち、多くの企業のM&Aに関する課題を解決してきました。
私たちは、企業価値の向上や事業拡大など、お客様が達成したい目標に向けて、最適な支援を行います。私たちは、お客様のM&Aの成功に向けて、共に取り組んでいきます。
M&Aは、企業にとって大きなチャンスであり、同時に大きなリスクを伴うこともあります。
弊社のM&Aコンサルティングは、お客様のビジネス成長のために、専門的かつ戦略的な支援を提供します。
弊社のコンサルタントが、お客様のM&Aの成功に向けて、全力で取り組みます。お気軽に、ご相談ください。

当社M&Aコンサルティングのメリット
1.専門的な知識と豊富な経験
弊社のコンサルタントは、M&Aに関する豊富な知識と経験を持っています。これにより、お客様に最適なアドバイスを提供することができます。
2.プロジェクトマネジメントの専門家
M&Aは、多岐にわたるプロセスから成り立っています。弊社のコンサルタントは、プロジェクトマネジメントの専門家でもあります。
お客様のM&Aプロジェクトを成功に導くため、スケジュール管理やリスクマネジメントなどを行います。
3.カスタマイズされたアプローチ
弊社のコンサルタントは、お客様に合わせたカスタマイズされたアプローチを提供します。お客様の業界や市場動向、企業の特性に合わせて、最適な支援を行います。
4.ネットワーク
弊社には、多数の業界や地域でのネットワークがあります。これにより、お客様のM&Aにおいて、最適なパートナーやアクイサションターゲットを見つけることができます。
5.継続的なサポート
M&Aは、終わりではありません。弊社は、M&A後の文化やビジネスモデルの調整など、継続的なサポートを提供します。お客様の成長に向けて、弊社と共に取り組んでいきます。
弊社のM&Aコンサルティングにより、お客様のM&Aが成功するよう、全力でサポートします。お気軽に、ご相談ください。

当社M&Aコンサルティングの期待される成果
1.ビジネス価値の最大化
M&Aは、ビジネス価値の最大化を目的として行われます。弊社のコンサルタントは、お客様のビジネス価値を最大化するための最適な戦略を提供します。
2.コスト削減
M&Aは、しばしばコスト削減のために行われます。弊社のコンサルタントは、お客様のコスト削減につながるM&Aを支援します。
3.業界での競争力の向上
M&Aにより、お客様の企業は業界での競争力を向上させることができます。弊社のコンサルタントは、お客様に最適なM&Aを提供することで、業界での競争力を向上させます。
4.新たな事業の創出
M&Aは、新たな事業の創出につながることがあります。弊社のコンサルタントは、お客様に最適なM&Aを提供することで、新たな事業の創出を支援します。
5.企業文化の融合
M&Aによって、企業文化が融合されることがあります。弊社のコンサルタントは、お客様の企業文化が融合されるようにサポートします。
以上のような成果が期待できるため、M&Aに関する問題を抱える経営者の方々は、弊社のM&Aコンサルティングをぜひご利用ください。

M&Aとは
M&A(エムアンドエー)とは「Mergers and Acquisitions」(合併と買収)の略で、資本の移動を伴う企業の合併と買収を指します。読み方はマージャーズ・アンド・アクイジションズとなります。
狭義的な意味のM&Aにおいては、吸収合併・新設合併などの企業の「合併」と、株式譲渡、新株引受、第三者割当増資、株式交換などの手段を通じた会社・事業の「買収」を指します。
広義的な意味では、事業の多角化などを目的とした資本提携(資本参加、合弁会社設立など)を含む、企業の経営戦略を指す場合もあります。
業績が好調であるにも関わらず、「後継者がいない」「今後の成長戦略が描けない」といった悩みを抱える中小企業が増えています。
特に後継者不在の問題が大きく、仕方なく廃業を選ぶ経営者が年々増加傾向にあります。
そのような中で、大きな注目を集めているのが「M&A」による事業承継です。
M&Aにより企業を信頼できる企業へ譲渡することで、長年培ってきた企業のノウハウを途絶えさせることなく、事業を存続・拡大させることが可能になります。

M&Aの目的
| 対象企業 | 目 的 |
|---|---|
| 譲渡企業 | ・事業承継などの後継者問題の解決 ・従業員やノウハウの承継 ・事業の整理 |
| 譲受企業 | ・新規事業への参入 ・既存事業の強化 ・スケールメリットの獲得 |
譲受企業(買い手)側の目的
事業の成長にななる時間を買うため
買収側にとってM&Aの大きな目的は時間を買うことができることにあります。
既存事業の拡大や、新規事業を立ち上げるには膨大な時間が必要です。M&Aにより、その時間を買い、事業拡大に要する時間を大幅に短縮することできる手法です。
シナジー効果を得るため
M&Aによって自社の弱みを補い、強みを最大化するシナジー効果を目的とする場合です。
自社の不足している技術や人材、市場を持つ企業と一つになることで、スピーディーに弱みを補完することが可能になります。
新規事業開拓のため
ビジネスチャンスを迅速に獲得することを目的とする場合です。
ビジネスは目まぐるしい速さで「成長期」⇒「成熟期」⇒「衰退期」のサイクルで動いています。一昔前までは、成長産業に参入する際には、自社で一から事業を立ち上げる必要がありました。
しかし、日進月歩でIT技術が進歩する中で、情報産業が高スピードで変化するだけでなく、全ての産業とDX(デジタルトランスフォーメーション)を起こし、産業のサイクルが高速化されました。
この結果、産業は短命化し、以前のように一から新事業を立ち上げる頃には、先行した競合相手に大きな差を付けられているようになりました。
このため、新たな事業に参入する場合、時間をかけ、迅速に行う必要性がでてきました。
投資資金を回収するまでの時間を短縮し、育成期を待たずに、次の新たなビジネスチャンスを獲得するにはM&Aは非常に合理的な手法です。
事業規模拡大のため
事業規模の拡大を目的とした場合です。
競争が激化する市場で勝ち残るためには、事業を拡大してスケールメリットを獲得する必要があります。企業は世界経済の中から選ばれる存在になる必要があります。
そのために必要なのは資本(体力)と効率の良い経営(筋肉質)です。
情報革命による変化は全ての産業で起きており、規模の拡大は既存事業の成長を待つだけでは追いつくことはできません。
業界上位となる規模の会社でないと、世界経済では生き残ることが難しくなってきてきました。そのために、M&Aでスピーディーな成長戦略を展開する企業が増えてきました。

譲渡企業(売り手)側の目的
後継者問題の解決
多くの中小企業経営者にとって、後継者問題は深刻な悩みです。
M&Aは、経営者が後継者問題を速やかに解決できる有効な手段です。一般的に中小企業の経営者が後継者を選ぶにあたり、先ずは親族または自社の役員や従業員の中から選抜しようとします。
しかし、後継者となり得る方に経営を引き継ぐ意思が無い場合や、意思があっても経営の才覚が無い場合も決して少なくあります。
このような場合に、M&Aで外部の第三者に経営を引き継ぐことができれば、廃業を避け、自社を生き残らせることが可能になります。
資金面でも、廃業にかかる費用を削減して、売却益を獲得することができます。
従業員の雇用維持
M&Aには、従業員の雇用を守れるという利点があります。
経営者にとって従業員の雇用を守るのは重要な役割です。特に地方では再就職先も少なく、廃業後に新たな職場を斡旋することも難しい場合が多々あります。
M&Aによって、経営者の引退後も将来にわたって事業が継続される状況を整えられれば、従業員だけでなく、その家族も安心して生活することができます。
それぞれの従業員はお客様や、取引先、販売先と深い関係性を作っている場合も多くあります。
その面でも従業員の雇用を守ることはその先の家族や取引先など、地域経済・地域資源を守ることにも繋がります。
経営者の個人保証が解除できる
経営者がM&Aに乗り出せない原因として、経営者自身が会社の債務の連帯保証人となっている場合があります。
しかし、M&Aの実行により、借入金を全て返済することができ、個人保証を外せるケースも多く、また、再生型のM&Aであれば、会社と併せ、経営者の保証債務についてもきちんと整理を行うことができます。
さらに、M&Aでは、一定の要件を満たすことで、借入金について一括返済も整理も行わずに、経営者の個人保証のみ解除できる場合もあります。
創業者利得の確保
M&Aでは、利益が出ている事業であっても売却するケース多くあります。
また、創業者はその功労に応じて、売却対価の一部を退職金の形で受け取ることも認められています。
自社株を第三者へ売却することで、その資金を元手に主力事業に注力する、または早期退職をするなどの様々なメリットがあります。

M&Aの流れ・順序
M&Aが実際にどのような手順で進んでいくのか、おおまかなM&Aの流れについて概要をご紹介します。
M&Aのプロセスは長期間に渡りますが、大きなくくりでまとめると3つのフェーズに分けることが出来ます。
1.準備フェーズ
2.交渉フェーズ
3.最終契約フェーズ
1. 準備フェーズ
M&Aの相談・検討
M&Aを行うにあたり、最初に行う事は「M&Aを行うことが自社にとって最も適した選択か」を考えることです。
併せて「M&Aを行う目的」や「自社にとって譲れない条件は何か」などの洗い出しを行いましょう。
M&Aを進めるとM&Aを行うこと自体が目的となるケースも多くあるため、検討段階で目的を明確にすることは重要です。
自社の経営状況の把握
M&Aの交渉を行う前に、交渉を行う際の好条件となり得る「自社の独自ノウハウや特許」、反対にトラブルとなり得る「簿外債務」などを含め、正確に自社の経営状況を洗い出すことは重要です。
この洗い出しを行うことでM&Aの交渉フェーズに移行した際にスムーズに進む確率が高くなります。
M&A仲介業者の選定
M&Aが自社にとって適した選択であるか、またM&Aの目的や自社の経営状況の把握を行った後、M&Aの仲介を依頼する業者を選択します。
M&AはM&A仲介会社に依頼することが一般的ではありますが、FA(ファイナンシャルアドバイザー)や銀行、士業事務所でもM&Aのサポートを受けることが可能です。
それぞれにメリットやデメリットがありますが、初めてM&Aを行う場合はM&Aのプロセスを一貫してサポートしてくれるM&A仲介会社がおすすめです。

2. 交渉フェーズ
ノンネームシートや企業概要書等の資料作成
ノンネームシートは企業が特定されない範囲の情報を纏めたものになり、M&Aアドバイザーが譲渡企業の紹介を譲受企業に行う際に使用されます。
また、ノンネームシートにより譲受を希望した企業に対してはより詳細な企業概要や財務状況などを纏めた企業概要書が開示されます。
譲受企業はこの企業概要書などを基にM&Aを進めるか否かを判断することになります。
そのほかにもM&Aを進めるにあたって、60品目以上の資料が必要となります。
資料の準備については時間がかかるものですので、思い立ったタイミングで少しずつ資料を纏めておくとスムーズに準備を進めることができるでしょう。
M&Aスキームの選択
M&Aを進める際にどういったスキームを用いるかを検討するのも、交渉フェーズです。
前述したようにM&Aのスキームには株式譲渡以外にも会社分割や合併など様々な種類があるため、M&Aの目的に合わせた選択が必要です。
M&Aスキーム次第でM&Aで得られる効果や財務会計面でも違いが生じるため、最も効果的なスキームを選択できるよう熟慮してください。
トップ面談
M&Aを進めたいパートナー企業が見つかった後は「トップ面談」を行います。
多くの場合、候補先企業が2~3社ほどになったタイミングで実施され、主に譲渡企業と譲受企業の経営ビジョンや譲渡後の運営方針など、お互いの理解を深める場となります。
また、後述するデューディリジェンス時に譲渡企業の不利な情報が明るみになると譲受企業は不信感を抱く可能性が高い為、譲渡企業は自社にとって不利な情報がある場合、トップ面談時に伝える事は重要です。
M&A基本合意・デューデリジェンス
トップ面談後、M&Aを進める相手企業が決定したら「基本合意書」を締結します。基本合意書では、これまでの条件を整理し譲渡価額やスケジュールなどを定めます。
また基本合意書締結後には「デューディリジェンス」と呼ばれる企業調査を譲受企業が譲渡企業に対して行います。
デューディリジェンスでは、譲受企業が選定した第三者の専門家が法務や税務などの観点から譲渡企業を調査します。
譲渡企業の規模や事業内容によりますが、中小企業であれば現地での実査に1~4日程、買収監査レポートが完成するまでに約1~2週間程を要します。
このデューディリジェンスの結果を鑑みて最終的な譲渡対価などが決定されます。

3. 最終契約フェーズ
M&Aの最終契約締結
「最終契約」はM&Aに関する最終的な合意内容になり、主に取引金額や表明保障、補償条項や解除条件などが含まれます。
基本合意の内容を基に作成されることが多いため、基本合意時に内容の確認を行うことが重要です。
なお、基本合意には法的拘束力はありませんが、最終契約には法的拘束力があるため、契約内容の確認は十分に行いましょう。
クロージング
「クロージング」は最終契約に基づいた経営権の移転手続きを指します。
このクロージングを行う事でM&Aの手続きは完了、成約となります。クロージングは法的にM&Aを有効にするための手続きですので、誤りが発生しない様、細心の注意を払う必要があります。
M&Aの事後処理
クロージングによる経営権の移転手続き後には「M&Aの事後処理」を行います。
新体制発足に伴う臨時株主総会の開催や変更の必要がある場合には定款の変更、代表取締役を新任する際には取締役会も実施する必要があるなどです。

英知コンサルティングの実績
実績
譲渡 52件
買収 23件
合計 75件
料金
ご面談・ご相談の上、最適なプランとお見積りをご提案いたします。
一緒にご覧いただいているページ
ご相談・お問い合わせはこちら(無料)
コンサルティングのご依頼や、詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。ご相談は勿論、無料です。
お問い合せフォームでのお問合せは24時間受け付けております。
サイドメニュー
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー
Executive Consultant
清水 一郎
-------------------------------------
<専門分野>
経営再建、企業再生、経営戦略、営業戦略、マーケティング、間接部門改革、法務、財務、金融、会計、税務、監査、事業承継、IPO、資産運用、不動産、組織構築、人事制度、人事評価制度、目標管理制度
-------------------------------------