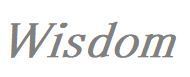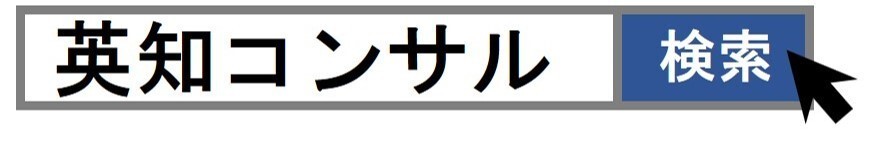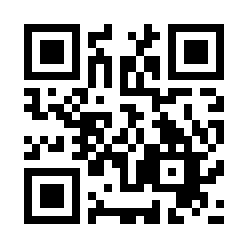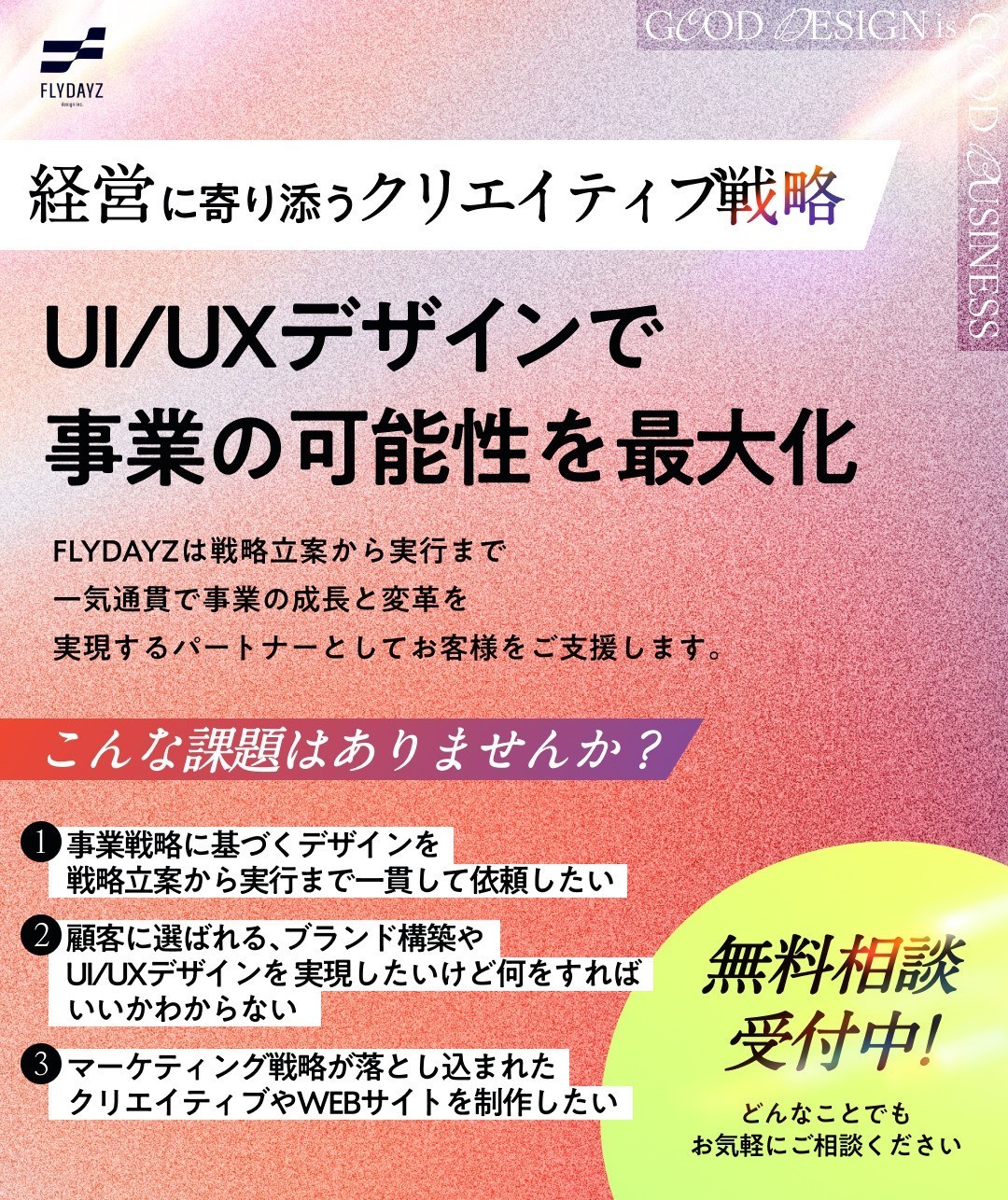中小企業・小規模事業者の経営コンサルティングは東京の英知コンサルティング株式会社(全国対応)
最終更新日 2024年08月17日
テレワーク導入
テレワーク導入なら東京の英知コンサルティング株式会社へ。
テレワークの導入で、働き方改革、時間の有効活用、ワークライフバランスを実現します。
テレワークの導入に当っては、各企業の個別事情を十分に分析して、最適なスタイルを総合的に設計しております。

テレワーク最新情報
2020年のパンデミック以降、ブームに乗って十分な検討・準備も行わずに「テレワーク」を導入した企業もあります。
一方で、現在も検討中の企業もあります。2022年になると、テレワークを恒久的な制度とする企業、テレワークは継続するものの出社日数を増やす企業、テレワークを完全に取止める企業など各企業の対応は分散してきました。
最新のテレワーク実施率
内閣府は、範型コロナウイルス感染症のパンデミック以降これまでに、「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」を4回実施しています。その最新の調査結果が、2021年11月に発表されています。
「地域別」では、全国のテレワーク実施率は32.2%、東京23区は55.2%と、東京23区の実施率が際立って高くなっています。
「業種別」の実施率が最も高いのは、情報通信業(IT系)が78.1%と、際立って高くなっています。次いで電気・ガスなどのインフラ系が45.3%、金融・保険・不動産業が44.5%と続きます。

テレワークの導入にあたり考慮すべき重要な要素
1. コミュニケーションの確立
テレワーカーとオフィスで働く仲間との効果的なコミュニケーションが鍵です。
コミュニケーションツールの選定やルールの設定が必要です。定期的なビデオ会議やチャットツールの使用により、情報共有と協力を確保しましょう。
2. クリアな目標設定
テレワーカーに対して明確な業務目標と成果物を設定することが重要です。
目標が明確であれば、業績評価や成果の追跡が容易になります。
3. セキュリティ対策
テレワーカーが外部からのセキュリティリスクにさらされないようにセキュリティ対策を強化しましょう。
データの暗号化、セキュアなアクセス方法の提供、セキュリティトレーニングなどが必要です。
4. オンラインツールの選定
テレワークを支援するために適切なオンラインツールを導入しましょう。
ビデオ会議、プロジェクト管理、コラボレーションツールなどが、効果的なリモートワークを支えます。
5. 作業スペースの整備
テレワーカーには快適な作業環境が必要です。
適切な椅子、デスク、モニターなどの設備を提供し、適切な照明やエルゴノミクスに気を付けましょう。
6. 業務の可視化
テレワーカーの業務進捗を可視化する手段を確立しましょう。
プロジェクト管理ツールやタスク管理ツールを使用して進捗状況を把握し、必要に応じて調整できるようにしましょう。
7. フレキシブルなスケジュール
テレワーカーには柔軟な労働スケジュールを許可し、家庭と仕事の調和を支援しましょう。
一部の業務を非常に早い朝や遅い夜に行うことも可能にしましょう。
8. オンライントレーニング
リモートワーカーにスキルアップの機会を提供し、新しいツールや技術を習得できるようにしましょう。
オンライントレーニングプログラムを提供することで、専門知識を維持し、従業員のモチベーションを高めることができます。
9. ワークライフバランス
テレワークの利点の一つは、ワークライフバランスの向上です。
従業員が疲弊しないように、適切な休憩時間や休暇の取得を奨励しましょう。
10. フィードバックと評価
テレワーカーのパフォーマンスを評価し、フィードバックを提供しましょう。
成果に基づいた評価と報酬体系を確立し、モチベーションを維持しましょう。
これらの要点を考慮して、テレワークの導入を計画し、効果的なリモートワーク環境を構築しましょう。
従業員のモチベーションと生産性を高め、組織全体の成功に貢献することができます。

テレワークのメリット・デメリット
企業側のメリット
①多様な人材の雇用・活用
フレキシブルな勤務時間の実現によって、通常のフルタイム出勤がしにくい人材の雇用や活躍のチャンスが増える。これにより優秀な人材を獲得し易くなる。
②コスト削減
交通費・出張費用など、人材の移動に関する費用や、オフィス賃料・設備代などの固定費、電子化による印刷費などの雑費の削減効果が見込める。
③緊急時におけるの事業継続性の向上
予期せぬ災害などに対し、緊急時の事業停止のリスクを最小限に抑えられ、かつ早期回復も見込める。
④営業効率の向上
オフィスに訪問して商談を行う従来の営業スタイルでは、商談の時間よりも移動時間が長い場合も多い。
Web会議・商談ツールを利用してオンライン商談化することで、移動時間を減らし営業効率の向上が期待できる。
⑤企業イメージの向上
政府が在宅勤務の導入を推進していることもあり、withコロナにおいては在宅勤務を導入している企業に良いイメージを持つ人は多い。
テレワークを導入していることを内外に伝えることで、幅広い人材を受け入れられる可能性が広がる。
⑥デジタル化の促進
テレワークではペーパーレスな環境が重視されます。これまで、慣習的に非効率と思いながらも行っていたオフィス業務の改善が見込める。

企業側のデメリット
①従業員の勤怠管理
通常の勤怠管理で多いのはタイムカードやICTカードをオフィスで読み込んで打刻するなど、客観的な記録によって勤務時間が確認される仕組みです。
一方、テレワークでの勤怠管理は勤怠管理システムを導入しない場合、エクセルなどの電子ファイルの出勤簿などに自己申告で記入する、上長などへのメールでの報告などの自己申告によって成り立つものが多いです。
そのため従業員側も管理者側も信憑性にやや疑問を感じざるを得ません。
また集計作業を別途行う必要があるため、手間がかかり適切な勤怠管理がしにくいのではないかという課題があります。
②プロジェクト・タスクの管理
オフィスで定期的な会議の開催や、同じ空間にいることで小さなことでもカジュアルに確認できていたプロジェクトやタスクの進捗管理がテレワークの場合やや難しくなります。
従業員やプロジェクトメンバーが揃っていない中で円滑に仕事を進めるために、エクセルなどを使い進捗や課題を集めるためのシートを作成するといった「仕事のための仕事」に大幅な業務時間を費やしかねません。
結果的に記録漏れなどでうまく機能せず個人ごとにチャットや電話をするなどの場面も多いのではないでしょうか。
③セキュリティリスク
テレワークでは自宅やコワーキングスペース、カフェなどのオフィス以外の場所で社員が業務を行うため、オフィス勤務よりもセキュリティリスクが高まります。
何も対策していないと、使用しているパソコンなどのデバイスの紛失盗難・画面を第三者に見られる、安全性の低いフリーWi-Fiの利用などによる情報 漏えいといった危険性があります。

従業員側のメリット
①ワークライフバランスの向上
出勤する機会が減少することで、従業員は通勤時間を減らせます。通勤電車や通勤時間の長さは多くの社会人にとってストレスの原因であり、その減少が見込めます。
余暇時間の増加によりプライベートを有効に使えることで、ワークライフバランスの向上が見込めます。
②生産性の向上
オフィス勤務は、メンバーと密にコミュニケーションを取りやすい一方で、個人で集中して取り組む作業などは中断されることがあります。
テレワークでは不意に直接話しかけられるタイミングはほぼないため、オフィス勤務に比べると比較的一つの業務に集中しやすい環境です。
また、自分の時間の都合に合わせて仕事ができる場合もあります。家事や家族との時間などプライベートと両立しつつ、スキマ時間の活用もできるので、オフィス勤務よりも生産性が向上することも見込めます。
③健康管理
コロナ渦においての通勤やオフィスで人と人が近い状況で働くことに「コロナに感染するのではないか」という不安をもつ人も一定数います。
テレワークを導入することで感染リスクを下げられ、従業員の健康管理に繋がります。

従業員側のデメリット
①コミュニケーション不足
オフィスで同じエリアや近くの席で業務を行うのと違いテレワークでは互いに別々の場所にいるためコミュニケーションの頻度が下がります。
Web会議ツールや社内チャットシステムである程度のコミュニケーションはできますが、チャットでは対面で相手の表情や雰囲気から細かいニュアンスを読み取ることや、会議の時間をとらなくても気軽に確認することなどはできません。
在宅で他のメンバーと会う頻度が減り日常会話などがなくなることで、疎外感や孤独を感じやすくなり、チームワークの低下やメンタルの問題を抱えることもあります。
②時間管理の難しさ
管理職がテレワーク時の勤怠管理に課題を感じるように、従業員側も時間管理に苦労することがあります。
これまではオフィスでの決まったタイムスケジュールに従って自然とルーティーンができていたり、職場の雰囲気で自然と時間管理ができていたりしてもテレワークでは基本的に自己管理が必要なため、ルーズになってしまう傾向があります。
③作業効率が低下する可能性
時間管理の問題のようにテレワークではセルフマネジメントが必要です。
オフィス環境で自然とオン・オフの切り替えができていても、自宅だと家族と同じ空間であるため業務に集中しきれない、緊張感がなく作業効率が落ちて長時間労働になるなどの問題が起きる可能性もあります。
また、オフィスでは仕事スペースとしてデスク・パソコン・椅子が整備されていますが、自宅では十分な作業スペースがない場合も多く、作業効率が落ちる原因になります。
④運動不足による不健康
テレワーク中には通勤がなくなることや外出自粛などで運動不足に陥りがちです。
仕事が忙しくオフィス勤務時には運動ができていないと感じていた人もテレワークではさらに運動不足になります。

テレワーク導入ステップ
コロナ禍で在宅勤務導入率が2倍に急増
2021年3月に国土交通省が発表したデータによると、2020年のテレワーク実施率は2019年の9.8%から19.7%と、新型コロナウイルスの影響でテレワークを導入する企業が急増しました。
しかし、2022年に入ると、テレワークを継続する企業と、元のオフィスワークに戻す企業への2極化が始まりました。
オフィスワークに戻す企業は、総じてテレワーク導入の際の準備不足が主な原因として指摘されます。
当社ではテレワークの導入・運用が成功するよう、ご支援をさせていただいております。当社では全社員を対象に2020年7月より、テレワークを導入し、多くのメリットを獲得し、コロナが収束後も長期的にテレワークを継続すると決定しております。
感染対策や働き方改革などメリットが多いテレワークですが、導入においてはしっかりと手順を踏むことが重要です。以下に当社の成功体験をご紹介いたします。

テレワーク導入ステップ
第1ステップ 導入の検討・方針の決定・経営判断
1.導入目的の明確化
導入前に、テレワークを導入する目的や、どのような効果を得たいのかを決定することが重要です。
テレワークを導入する目的やメリットとして代表的なものは以下の通りです。
①多様な人材の雇用、離職防止
②交通費やオフィス賃料などのコスト削減
③非常時の事業継続性の向上
④生産性の向上
⑤企業イメージの向上
⑥企業のデジタル化の促進
⑦従業員の満足度やQOL(Quality of Life)の向上
上記の中で、どれを優先するのかを決めます。
コロナ禍における緊急事態宣言時では「非常時の事業継続性の向上」が最重要になる場合が多いですが、同時に達成するべき目的の優先順位を定めがあることで基本ポリシーの設定に役立ちます。
2.基本ポリシーの決定
次に、範囲と形態といった基本ポリシーを定めます。
基本ポリシーの項目としては、以下が挙げられます。
①対象となる従業員や部門
②対象となる業務(在宅勤務と相性の良い自己完結する業務や成果が見えやすい業務に絞るのか)
③実施頻度(週に1度なのか、完全テレワークなのか)
④導入形態(テレワーク、モバイルワーク、サテライトオフィス)
これらは重要な経営判断になるので、経営層や導入部門のトップがリーダーシップを取って進めます。
第2ステップ 現状把握
具体的な検討段階に進むにあたり、現在の社内制度や仕組みを確認し、テレワーク導入後にどう変わるのかもシュミュレーションします。
①就業規則(基本となる始業・終業時間や例外のケースなど)と勤怠管理制度
②人事評価制度(目標管理制度、成果に基づく評価制度など、それに伴う給与制度
③各部門のオフィス環境での仕事の進め方
④ICT環境(デジタル化やクラウド化が進んでいるのか)
⑤セキュリティ環境やルール
⑥労働組合がある場合は組合の考え方(労働組合がない場合には従業員の考え方)

第3ステップ 推進体制の構築
テレワークの導入時にはプロジェクトチームを立上げ、推進のための社内体制を確立することが重要です。
①経営企画部門
②人事、総務部門
③情報システム部門
などの関わる部門と各部門の代表を含めた横断的なチームメンバーで推進体制をつくります。
導入推進にあたっては以下の3つの観点も考える必要があります。
①社内ルールの観点
テレワーク実施者が適切な労働環境で働けるようにルールを整備し、教育・研修する。
②ITツールなど環境の観点
テレワーク実施者がオフィスを離れても快適な環境で働けるように、ITツールを導入するなど環境
を整備する。
③情報セキュリティの観点
テレワーク実施者が安心して働けるよう、情報セキュリティ対策を整備する。

第4ステップ 社内ルールの構築
プロジェクトチームが編成できたら、テレワーク導入に向けた社内のルールを作ります。
1.就業規則の変更
テレワーク時も労働関連法令を遵守する必要があります。長時間労働になる場合や、逆にルーズになってしまう場合もあるので、テレワーク時の労務管理についてルールを定める必要があります。
一般的にテレワークを導入する場合に就業規則に定める項目は以下の3つです。
①テレワーク勤務を命じることに関する規程
②テレワーク勤務用の労働時間を設ける場合、その労働時間に関する規程
③通信費・情報通信機器などの負担に関する規程
2.勤怠管理
オフィス勤務時の勤怠管理の方式を、テレワーク用の勤務管理の仕組みに切り替える必要があります。
電話・メールによる勤怠管理は導入コストが低いものの、記録に手間がかかります。大人数の勤怠管理は煩雑となるなどのデメリットも多いです。
導入コストは少し上がっても、ITツールを導入して勤怠管理をすることで、従業員の方から簡単に始業・就業時刻等を申請・管理ができる仕組みを作ることが望まれます。
また、働き方改革関連法の施行により、2020年4月より中小企業でも時間外労働の上限規制が強化されました。
違反時の罰則も規定されたので、労働時間を客観的に把握できる仕組みはより重要になっています。
3.安全衛生
労働安全衛生法により、テレワークを行う労働者も含めた全労働者に対しての安全衛生教育や健康診断とその事後措置、長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェック(常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務づけ)等が義務付けられています。
現在運用している仕組みやルールなどに、テレワーク用に修正すべき項目などがないか確認しましょう。たとえば、テレワークによる労働者の心身の負担を考慮し、健康上の相談ができる窓口の設置、医師や保健師による保健指導の実施などが挙げられます。
4.教育・研修
テレワーク導入時には、そのメリットやルールを理解してもらうためにも、従業員への教育や研修が必要です。説明会の実施や、オンライン研修・eラーニングを行いましょう。
テレワークの利用者(メンバー)だけでなく、テレワーク時にマネジメントを行う管理職など、それぞれを対象にした内容が好ましいです。
①テレワークの目的・必要性
②テレワークの実施の流れ・周囲の体制
③テレワーク時のツールの使用方法
の3点は導入計画に織込み実施します。

第5ステップ IT・情報システム環境の整備
テレワークを実施する場合、想定される業務内容に合わせてITツールの導入やセキュリティ対策などを行う必要があります。
1.ネットワーク環境整備
テレワーク時でも自宅のパソコンやスマートフォンから社内システムに接続できる環境を構築することで、オフィスにいるのと同じように資料の編集やメールなどの業務ができるようになります。
ネットワーク接続環境の構築と同時に、テレワークで使用する従業員の端末も用意しましょう。会社のパソコンを持ち帰り利用する方式や、個人所有の端末から会社パソコンにアクセスして遠隔操作を行う方式もあります。
2.業務のオンライン化
内線や外線などの電話もテレワークに対応することが可能です。クラウドPBX(電話交換機)などを利用することで、従業員のスマートフォンがオフィスの電話機として利用可能になります。
社外から会社への電話を自宅で応答する、スマートフォンから会社の電話番号での取引先への電話発信をする、また内線の転送なども可能です。
クラウドサービスを通じて、従業員間での内線通話も可能になり、通話料の削減も見込めます。
環境構築の方法には、オフィスで利用中の電話設備を有効活用する方法や、サーバーをクラウド化して災害対策までを実現する方法があるため、自社の状況に合わせて検討しましょう。
3.業務のオンライン化
オフィスでの業務が前提となっていた勤怠管理や会議・商談、契約処理や帳票管理などのバックオフィス業務も、ITツールの導入でテレワークに対応できます。
業務例は以下です。
①オンライン上で会議・商談・研修の実施
②電子契約での押印による契約締結
③帳票の電子化による管理効率化
4.情報セキュリティ対策
テレワークでは、従業員が業務に関わる情報を社外で利用する機会が増加します。
業務用端末の盗難や、外部からの不正アクセス、コンピュータウイルスなどの情報セキュリティリスクが増加するので対策が必要です。
主な情報セキュリティ対策は以下です。
①不正アクセス対策
②ファイヤウォールの導入、IPS(侵入防止システム)、IDS(侵入検知システム)の導入
③データ盗聴、改ざん防止
④VPN(仮想私設網)などの安全性の高い通信インフラの導入
⑤端末管理、情報漏えい対策
⑥ウイルス対策ソフトの導入、シンクライアント端末(保存機能などを持たない端末)や
端末操作制御ソフトの導入
上記に加えて、情報セキュリティポリシーの策定や研修による在宅ワーカーのセキュリティ意識向上なども重要です。
5.従業員へのサポート環境の整備
テレワークを導入時に、IT機器やツールの操作に慣れていない従業員をサポートする体制も必要です。
テレワークの導入後は、
①自宅側でインターネットにうまく繋がらない
②新しく導入したWeb会議ツールが使いこなせない
などの問い合わせが情シス担当に集中することが想定されます。
対応するためのリソースに余裕があれば、自社内で完結させることもできますが、情報システム部門の人数は限られている場合が多いため、アウトソーシングを活用して解決するのも有効です。
オフィス内のサーバーをはじめとした機器管理業務もアウトソーシングすることができ、IT担当者の業務負荷を軽減できるため、 検討してみるとよいでしょう。
また、ITツールはサポート体制の整っているサービスを選ぶことで、コールセンターでの対応など手厚いサポートを受けることができ安心です。
6.従業員へのサポート環境の整備
テレワークの導入後も完全リモートワークでまったく出社をしない人は少なく、週のうち数日の出社日がある場合や、やむを得ず出社する場合もあります。
オフィスでの物理的感染症対策として、従業員や来訪者の安全確保に努めることも重要です。密集や接触の機会が減少するようなルールづくりやツールの導入などを検討しましょう。
代表的なオフィスでの感染症対策は以下が挙げられます。
①マスク着用の義務化
②飛沫感染防止のアクリルパネルの設置
③サーマルカメラによる出社時の自動検温
④混雑状況を可視化するカメラシステム
⑤着席時のソーシャルディスタンスを保つルール決め
これらを活用して三密の回避に努めまることが大切です。

第6ステップ テレワークの導入とその評価
テレワークの本格的な導入の前にトライアルとして導入する場合は、導入目的の達成度合いや問題点の洗い出しなどの、効果測定を行う必要があります。
テレワークを実施した従業員へのヒアリングやインタビューによる「質的評価」や、アンケートの実施や期間内での業務量、成果などのチェックによる「量的評価」の2つの観点で行いましょう。
また、本格導入をして一定期間がたった振り返りのタイミングでは、より大きな指標として「会社・部門の売上高」「社員の求職・離職率」なども参考になる指標です。
テレワークを導入した目的を達成できているのか、また導入した結果マイナスになった部分はどこなのかを把握することで、会社全体の中長期的なテレワークの定着に繋がります。

英知コンサルティングの実績
実績
364件
料金
ご面談・ご相談の上、最適なプランとお見積りをご提案いたします。
一緒にご覧いただいているページ
ご相談・お問い合わせはこちら(無料)
コンサルティングのご依頼や、詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。ご相談は勿論、無料です。
お問い合せフォームでのお問合せは24時間受け付けております。
サイドメニュー
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー
Executive Consultant
清水 一郎
-------------------------------------
<専門分野>
経営再建、企業再生、経営戦略、営業戦略、マーケティング、間接部門改革、法務、財務、金融、会計、税務、監査、事業承継、IPO、資産運用、不動産、組織構築、人事制度、人事評価制度、目標管理制度
-------------------------------------