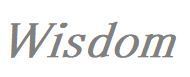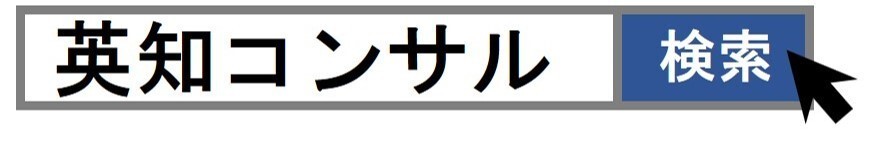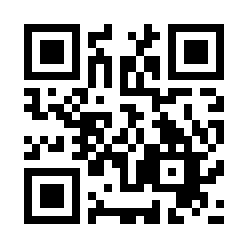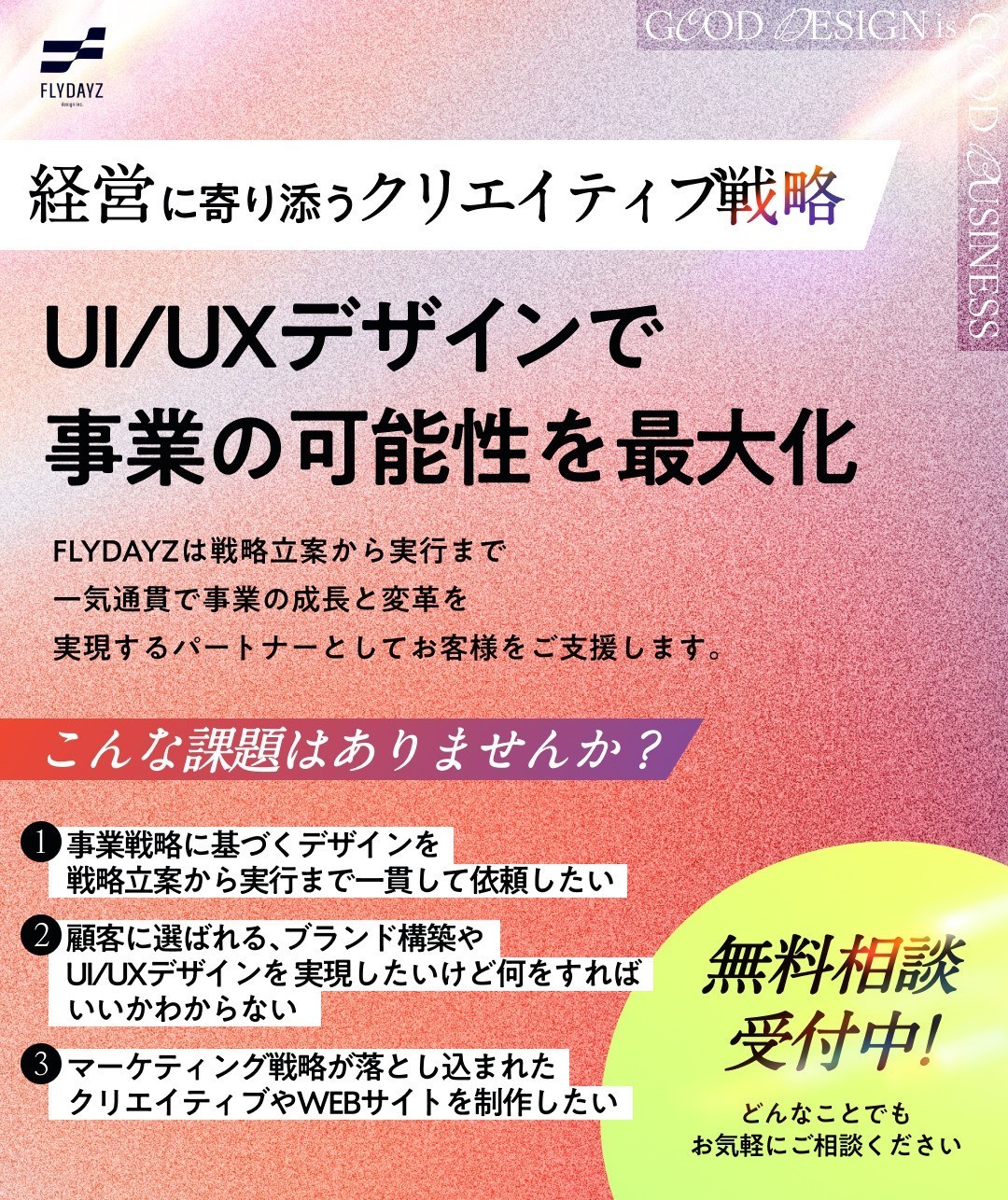中小企業・小規模事業者の経営コンサルティングは東京の英知コンサルティング株式会社(全国対応)
最終更新日 2024年06月22日
中小会計指針・中小会計要領
中小会計指針・中小会計要領の導入支援は東京の英知コンサルティング株式会社へ。
税務署に申告する目的だけの「税務会計」から、真に事業の拡大と発展に資する「企業会計」への移行を支援しております。

税務会計は経営者の経営判断を歪める危険性がある
「税務簿記」も「税務会計」も、「税」を中心とした会計手法のため、企業会計原則(一般原則)に記載されている「真実性の原則」や「正規の簿記の原則」の要件を満たしていません。
ここで大切なことは、経営者の経営判断を歪めない正しい経営情報を提供することです。
経理部門が「真実性の原則」や「正規の簿記の原則」の要件を満たしていない経営情報で、経営者の経営判断を歪めた場合、会社存亡にも係る「危機」を招く恐れがあります。
「経理」とは「経営管理」の略称です。経営管理とは、経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報」を有効活用して組織の目標達成を図ることです。
経理でまとめられた情報は、組織の現状把握や収益性を明らかにします。したがって、経理は経営層の意思決定をサポートする重要な役割も担っています。

「税務会計」から「財務会計」へ
日本で認められている会計基準は4種類
1.日本基準
日本基準は、1949年に公表された「企業会計原則」をベースとしています。その後、社会の変化に合わせて、2001年からは企業会計基準委員会が設定した会計基準を合わせたものが採用されています。
2.米国会計基準
米国で採用されている会計基準です。米国財務会計基準審議会(FASB)が発行する財務会計基準書(SFAS)、FASB解釈指針(FIN)などから構成されています。アメリカで上場している日本企業は、米国会計基準に基づいて財務諸表を作成しなければなりません。
3.IFRS
IFRS(International Financial Reporting Standardsの略)では、貸借対照表は「財政状態計算書」という呼び方になり、固定資産も「非流動資産」として計上されたりするなど、日本会計基準とはルールが異なります。
IFRSは時価評価を重視していて、売上ひとつとっても、出荷基準が認められず、すべて検収基準となります。日本企業が導入には、ハードルが高いといえます。
4.J-IFRS
日本会計基準とIFRSのあいだに位置付けられた内容で、2016年3月期末より適用されています。IFRSの内容を、日本国内の経済状況などに合わせて調整した会計基準です。

中小企業に推奨される会計基準
中小企業の会計基準
中小企業を対象とした会計処理の方法には、「中小企業の会計に関する指針」 ( 中小会計指針 )と、「中小企業の会計に関する基本要領」 ( 中小会計要領 )の2つの会計基準が公表さけており、中小企業はどちらの基準も適用することができます。
中小企業に推奨される会計基準
上記の4つの基準ほど厳密ではありませんが、中小企業を対象とした会計処理の方法には「中小企業の会計に関する指針」 ( 中小会計指針 )と、「中小企業の会計に関する基本要領」 ( 中小会計要領 )の2つの会計基準が公表さけており、中小企業はどちらの基準も適用することができます。
当社では、中小企業に対し、「中小会計指針」または「 中小会計要領」を強く推奨しております。
| 中小会計指針 | 中小会計要領 | |
| 想定対象 | 会計参与設置会社 (ある程度の規模がある中堅企業) | 指針と比べて簡単な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業 (小規模な中小企業) |
| 内容 | 中小会計要領よりも詳細に、一定の水準を保った会計処理が示されている | 簡潔で、できるたけやさしく記載されている |
| 会計ルールの数 | 18項目あり、税効果会計や組織再編会計などについての記載もある | 基本的な14項目に絞られており、税効果会計や組織再編会計などはない |
| 税務上の取扱い | 会計基準がなく税務上の処理が実態を適正に表しており、かつ、あるべき会計処理と重要な差異がない場合に限って、税務上の処理を適用できる | 実務における会計慣行を踏まえて規定されている |
「中小企業の会計に関する指針」(中小会計指針)とは
目的
株式会社は、会社法によって、貸借対照表や損益計算書などの計算書類を作成することが義務付けられています。
「中小企業の会計に関する指針」(中小会計指針)は、中小企業が計算書類の作成するにあたって、望ましい会計処理が示されています。
このため、中小企業は、この中小会計指針によって計算書類を作成することが推奨されています。
対象
「中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)の対象は、次の2つ(いわゆる大企業)を除いた株式会社になります。
①金融商品取引法の適用を受ける会社(上場会社など)と、その子会社および関連会社
②会計監査人を設置する会社(資本金5億円以上、または負債200億円以上の大会社など)とその子会社
したがって、大半の中小企業が対象になりますが、その中でも、会計参与設置会社が計算書類を作成する際には、中小会計指針に拠ることが適当であるとされています。
また、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社といった株式会社以外の会社についても、中小会計指針に拠ることが推奨されています。
方針
企業の規模に関係なく、取引の経済実態が同じであるならば、会計処理も同じになるべきです。しかし、中小企業にまで厳格に会計基準を適用することは、費用対効果の観点から、適切とは言えません。
そこで、会計処理の簡便化や法人税法上の処理の適用が、一定の場合には認められています。
また、会計情報に期待される役割として経営管理に資する意義も大きいことから、会計情報を適時・正確に作成することが重要です。
このような点を考慮して、中小会計指針では、中小企業が拠ることが望ましい会計処理や注記等を示しています。
「中小会計指針」適用のメリット
1.信用度の向上
2.融資の条件が有利になる場合がある
①利息が安くなる
②適用している場合に受けられる融資の制度がある
③補助金の申請の際、適用していると加点される場合がある
3.より正確な経営分析が可能になる
中小企業の会計処理の実態
税理士が用いる「税務会計」という基準は認められていません
「税務会計」は、税理士さんの「主観」に基づく「簿記」をベースとした経理処理であって、公式に認めれた「基準」ではありません。従って我国に「税務会計」なる基準は、そもそも存在しません。
「税務会計」と「財務会計」のズレ
不良在庫を例に説明いたします。
「企業会計」では、不良在庫は本来の商品価値を失った商品ですから、当然、相当の評価減を行った後の金額をもって貸借対照表に表示しなければなりません。
一方、税法の規定では、一定の基準を満たさなければ、評価減を行うことができないため、「税務会計」で経理処理をした場合には、実態とは異なる金額で貸借対照表に表示されることになります。
つまり、税理士さんが作成した「税務会計」に基づく決算書を用いて経営判断を行った場合、「実態」と大きなズレが生じることになってしまいます。
税理士さんが「税務会計」により作成した、貸借対照表・損益計算書を用いて経営判断をすることが、如何に危険かということがおわかりいただけると思います。

中小企業の多くは「税務会計」が用いられています
中小企業庁の統計によれば、我国の企業数は421万社あり、この内、中小企業が占める割合は99.7%の419.8万社とされています。
この中小企業の大半が、税理士さんの「税務会計」を用いていると推察されます。
本来であれば、正しい「財務会計」を用いて財務諸表を作成し、その上で税務上の課税所得を計算するための税務申告書を作成するのが、本来あるべき姿です。
しかし、税理士さんは「課税所得さえ正しく計算していれば税務署から文句を言われない」という考えが優先されています。
その結果として、貸借対照表と損益計算書が会社の財政状態と経営成績を正しく表示していないケースが圧倒的に多いのです。
「税務会計」で経営判断を行うことはたいへん危険です!
クライアント企業の税務調査に立会うことがありますが、当然のことながら税務署の調査官が、貸借対照表や損益計算書について会社を指導するケースはゼロです。
税務署が指導するのは、税務署の立場から見た正しい税務処理であり、極端な言い方をすれば調査官は正しい会計処理には全く関心を持っていないのです。
調査官の立場からは、課税所得さえ正しく計算されていればよいのであって、正しい勘定科目の処理などは「どうでもよい」ことなのです。
従って、税金計算目的の「税務会計」で経営判断を行うことは、経営者の経営判断を誤らせる、非常に危険なことなのです。

税理士は「税金のプロ」であって「会計のプロ」に非ず!
公認会計士は「会計&税のプロ」です!
税理士さんは「税」の専門家であり、公認会計士は「会計」と「税」の専門家です。税理士と公認会計士とでは、専門領域が異なるということです。
弁護士と公認会計士には、おまけに「税理士資格」が付いてきます。弁護士が税理士登録をすることは希ですが、公認会計士は「会計と税の一体性」から、ほぼ全員が税理士登録をしています。
当社では、「会計&税のプロ」である公認会計士に「会計・税務顧問」を依頼することがBESTであると考えております。
「財務会計」は「管理会計」へとし進化します!
「税務会計」から「財務会計」に移行したたげでは、経営判断を行うには十分とはいえません。
「税務会計」から「管理会計」に移行しても全く無意味ですが、「財務会計」は正しい「管理会計」へと進化することができます。
「管理会計」とは、主に企業の経営者、経営幹部、部門長といった企業の内部関係者に経営の実態を報告することを目的とした内部報告向け会計です。
「管理会計」が加わることで会計制度は完結されます。

会計・税務顧問契約(法人・個人)
当社の「会計顧問契約」が、税理士さんと決定的に異なる点があります。
それは、税理士さんが「作業の代行・外注」であるのに対し、当社では「経理の自計化」と経理課員の「人材育成」を目指している点にあります。
創業時から成長ステージへの変革期。未来へ進む成長ステージでは、経理や会計業務が高度になるため、求められるスキルや知識レベルも異なります。
「経理の自計化」のゴールは、月次決算・年度決算の一部を自社で完結させることです。各クライアント様の経理の原状と、経理担当者の能力に合った「人材育成」を行なっております。
「会計・税務顧問契約」と「月次経営顧問契約」をセットでご契約されておられる企業様が大半です。
会計・税務顧問に加え経営コンサルティングで、管理部門改革を支援しております。
月次決算
1.タイムリーな月次決算を行います。月次決算は「速報性」が重要です。
2.月次決算を継続する仕組みをつくります。
3.わかりやすい分析資料を提供します。
4.お客様とのコミュニケーションを重視します。
5.記帳代行を承ります。
6.リーズナブルな価格で会計ソフトを提供いたします。
確定決算対策
1.決算月の2か月前から、業績の着地点を想定しながら必要な対策をお客様とともに検討します。
2.納税資金の確保、資金の有効利用の観点から利益の平準化を検討します。
決算・申告
1.有利な税制を見逃しません。その上で適正な税務申告をします。
2.月次決算を継続する仕組みをつくります。
3.「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」および「中小企業の会
計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」を積極的に活用しています。

相続税申告・相続税対策
相続税申告
1.初回相談、申告費用の見積もりは無料です。
2.資産税専門の税理士が対応いたします。
3.二次相続まで視野にいれた分割案を提案します。
4.小規模宅地の特例、地積規模の大きな宅地などの制度について、幅広く深い見地から適用を検討し
ます。
5.複数の方法があるときは、それぞれのメリットデメリットを説明し判断をサポートします。
相続税対策
相続税大増税時代に不安をお持ちのことと思います。
何から手をつけて良いかわからない。そんな不安な気持ちから対策が後手にまわったり、あふれる情報に惑わされ、相続税対策で後悔をすることにもなりかねません。
テクニックとしての対策ばかりを先行させず、不安なお気持ちをお聞きするところからはじめます。相続税対策には何よりも現状の把握が重要です。私どもは現状把握に始まるプロセスを確実に進めます。
また、すでに対策をとられていても、法律の改正により過去の対策を見直す必要があるかもしれません。今のベストが将来のベストとは限りません。わたくしどもは継続的にフォローすることで対策をより確かなものにします。
弁護士、司法書士と連携しBESTな相続税対策をご提供いたします。
相続税対策と表裏一体のものとして資産活用があります。
長寿社会における将来の安心のために、ライフプランに合わせた長期の視点でお手持ちの資産を有効に活用することで得られる税務上のメリット、資産を運用する場合の税金についてFPがアドバイスを行っております。
相続税対策のプロセス
1.財産目録の作成および、親族関係図の作成
2.相続税額シミュレーション
3.相続税対策
①生前贈与の検討
②不動産の活用および、生命保険の活用
③相続時精算課税制度の活
④遺言書の作成指導
4.プランの作成と、定期的な見直し

当社はジョブカン会計の認定アドバイザーです
当社は「ジョブカン会計シリーズ」の認定アドバイザーに認定されています。
2023年(令和5年)10月1日施行の「インボイス制度」および2024年(令和6年)1月1日施行の「改正電子帳簿保存法」に完全準拠した会計制度を構築して参ります。
当社を通じて「ジョブカン会計シリーズ」を導入していただいた場合、割引を受けることができます。

英知コンサルティングの実績
実績
会計・税務顧問契約 529件
料金
ご面談・ご相談の上、最適なプランとお見積りをご提案いたします。
一緒にご覧いただいているページ
ご相談・お問い合わせはこちら(無料)
コンサルティングのご依頼や、詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。ご相談は勿論、無料です。
お問い合せフォームでのお問合せは24時間受け付けております。
サイドメニュー
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー
Executive Consultant
清水 一郎
-------------------------------------
<専門分野>
経営再建、企業再生、経営戦略、営業戦略、マーケティング、間接部門改革、法務、財務、金融、会計、税務、監査、事業承継、IPO、資産運用、不動産、組織構築、人事制度、人事評価制度、目標管理制度
-------------------------------------