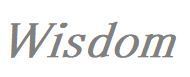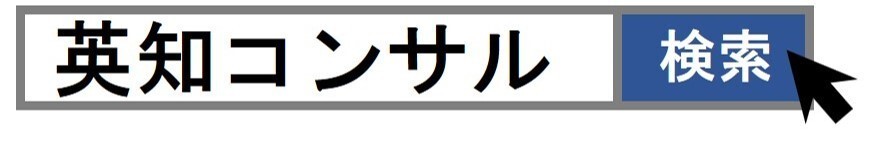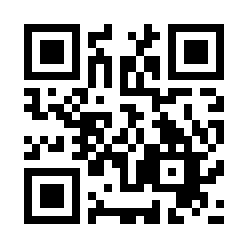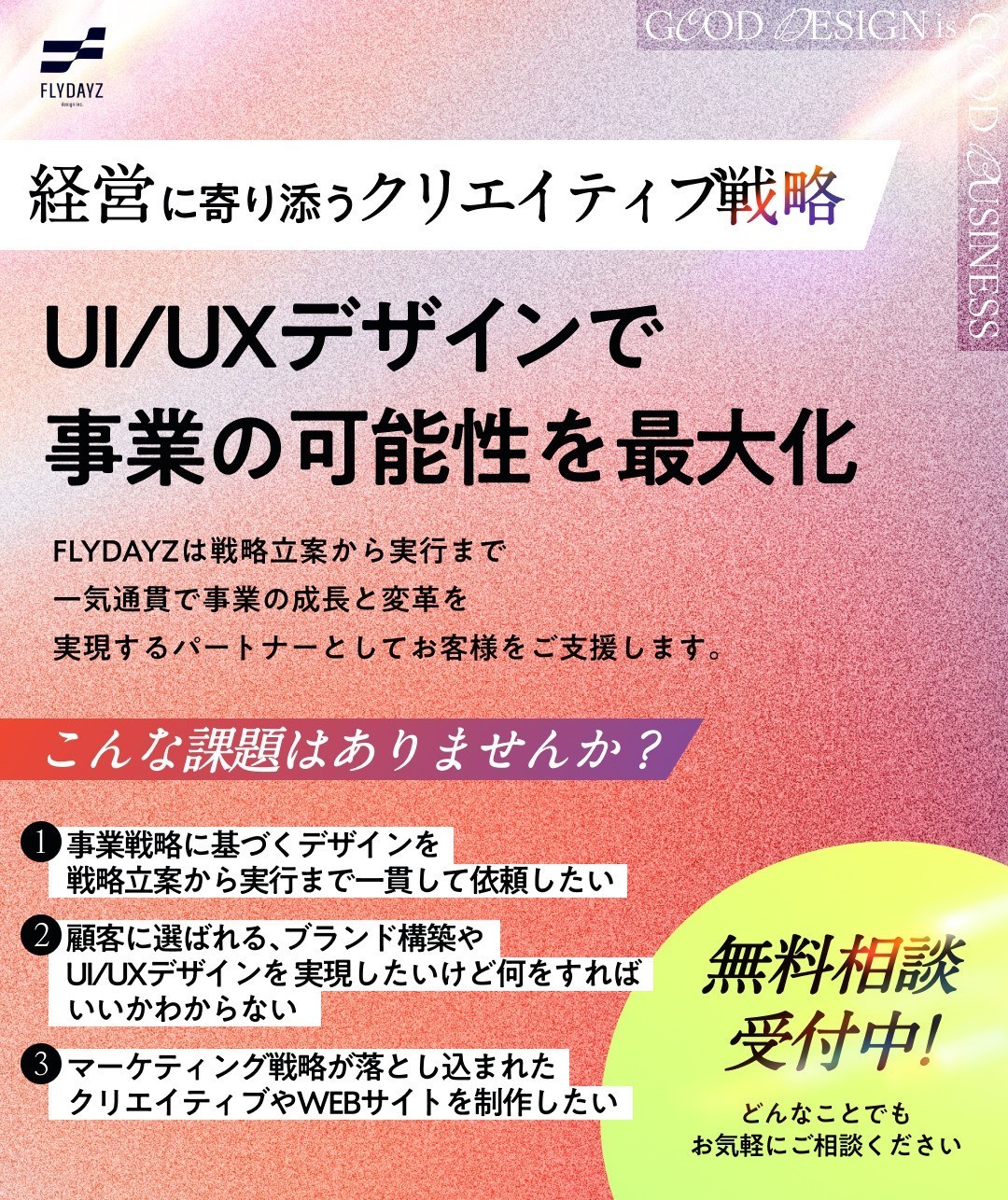中小企業・小規模事業者の経営コンサルティングは東京の英知コンサルティング株式会社(全国対応)
最終更新日 2024年08月17日
属人化解消コンサル
属人化解消コンサルは東京の英知コンサルティング株式会社へ。特定の社員にしかできない属人化業務には多くのはデメリットとリスクがあります。
業務を標準化することによって、特定の人物に依存することなく業務を遂行でき、業務品質の担保や生産性の向上が期待できます。属人化は速やかに解消しなければなりません。
属人化から標準化へ
クライアントから問い合わせがきたものの、担当者が不在で対応が遅れてしまった」、「前任者が退職してしまい業務が止まってしまった」という経験はありませんか?
これらはすべて「業務の属人化」が原因です。本ページでは、属人化の意味とそのデメリット、そして解消するための方法をわかりやすく解説します。
<目 次>

1. 業務の属人化とは
業務の「属人化」とは、企業などにおいて特定の業務のやり方が、その業務の担当者にしかわからない状態を指します。
言い換えれば、担当者以外の社員からは「何を・どのような手順で・どれくらいの時間をかけて」実施しているのかが分からない状況です。
「属人化」に陥ると業務負担に偏りが生じやすく、担当者の不在時や退職の際には業務が滞ってしまう可能性が高いため、多くの場合ネガティブな意味を持ちます。
「属人化」の対義語は「標準化(マニュアル化)」であり、ビジネスにおいてはポジティブな意味合いで用いられるのが一般的です。
高度な専門知識を要する業務や企画開発などは、「属人化」されてしまう業務もあるようですが、批判的なニュアンスを含むケースです。
基本的には業務の担当者以外にもわかるよう、マニュアルを作成するなどして「標準化」するべきです。
より、わかりやすく表現すると、「属人化」とは「特定の人物がいないとその業務がまわらない状態」だということです。
こうした状態になってしまうといろいろな場面で企業に悪い影響を及ぼし、リスクが出てきます。
2. 属人化によるデメリット
2-1. 業務の停滞リスク
2-2. 業務の不透明化
業務をどのように進めればいいのか担当者にしかわからない属人化した状態では、他の人からすると業務の内容としてはっきりと確認できるのは成果のみで、その結果に至るまでの過程は不透明になります。
こういった状態になることを、業務の「ブラックボックス化」とも呼びます。
過程がわからなくても成果がきちんと上がっているならそれでいいようにも感じてしまいますが、業務が不透明化していることになかなか気が付けないケースも多いです。
成果に至るまでの過程を把握できない、業務の担当者しかプロセスを理解できていない状態が続くと、さまざまなデメリットがあります。
例えば、業務をより効率化したいと思っても、担当者以外は業務の全容を把握できていない状態ではどう改善すればいいかの議論すらできません。業務内容のブラッシュアップがとても難しくなるのです。
2-3. 業務効率の低下
属人化によるリスクのひとつが、業務効率の低下です。担当者だけが業務の進め方を知っている状態では、業務の手順・方法について客観的な評価ができず、業務効率を改善しにくくなります。
また、長時間労働に陥りやすいという点にも注意が必要です。長時間労働によってパフォーマンスが低下したり、場合によっては休職や退職につながるケースも考えられるでしょう。
<具体例>
毎回手探りで行うため、同じ作業に通常の倍の時間がかかる。

2-4. 品質の不安定化
業務の品質が安定しにくいという点も、属人化のデメリットと言えます。属人化している業務は、手順書や業務マニュアルが存在しないことも多く、一定の品質を保つのが難しくなります。
属人化した状態では、担当者がいないと途端に業務が滞ります。担当者が何らかの事情で急に休むだけで業務がストップしてしまうのです。
退職や休職のような長期間の離脱ならいざしらず、自分が一日休むだけでも問題が起きることを担当者自身も理解しているため、休暇を減らすなどして無理をして働かざるを得ないケースが出てきます。
そうなれば作業効率は落ちてしまいます。業務の属人化は、働き方の質にも大きく影響するのです。
また、担当者以外に業務の適切な進め方を把握している社員がいないため、品質の低下やミスを発見・指摘することも難しくなります。
2-5. ミスや非効率が発見しづらくなる
担当者しか業務のプロセスを把握せずに仕事がまわっているということは、他の人による途中経過のチェックや確認ができていないということでもあります。
担当者がいくら業務を把握しているといっても、ミスをする可能性はゼロにはなりません。
属人化した状態では、重大なミスを見逃しやすくなってしまうのです。また、担当者がいないと進まない作業があると、その作業が終わるまで他の人は何もできず待つことしかできません。
属人化した業務に関して、担当者以外の人は手伝うことすらできないのです。また、人手があっても担当者の負担は解消されず、業務全体が非効率的に進められることになります。
しかも、業務の属人化について意識していないとこの非効率を改善するどころか、気が付くことすら難しいのです。
2-6. 適正な評価が難しくなる
属人化した業務は、適正な評価が難しいという課題もあります。担当者しか業務内容を把握していないため、どれだけ業務の質が高いのか、どれだけ以前より成長したのかなど、上司は正当な評価を行うことが難しくなります。
業務上の評価は、結果としてあらわれる数値と、評価をする人の主観によって行われます。営業成績の良し悪し、残業時間の長さ、勤務中の態度などが評価の基準となります。
業務が属人化していると、成果が上がっていれば関わっている人の評価は高くなりやすいですが、逆に成果が上がらないとどれだけ頑張っていても、どれだけ貢献していても、評価を下げられてしまいがちです。
最大のネックは、業務の属人化に対する問題意識がない場合、成果が上がらない理由としてプロセスが関係しているのかもしれない、という発想になかなかなりにくいことです。
成果が出ていないと、不当だと感じていても、その評価を受け入れざるを得ない環境になってしまうことも、大きなデメリットです。
また、業務量に対して担当者の数は適切かなど、体制に関する意思決定も難しくなるでしょう。
2-7. ナレッジ・ノウハウが蓄積されない
組織としてナレッジ・ノウハウが蓄積されないという点も、属人化のデメリットとです。属人化している業務から得られる知見は、あくまで担当する従業員のナレッジ・ノウハウであり、組織として共有・活用を促進することができません。
従業員が業務のなかで得たナレッジ・ノウハウを組織内で共有し、新たなアイデアの創出や業務改善につなげていくことができず、担当する従業員が離職してしまった場合には、得られたナレッジ・ノウハウも失うことになります。
<具体例>
新人教育が毎回一から始まり、時間とコストがかかる。

3. 業務の属人化が起こる原因
3-1. 多忙による共有不足
3-2. 業務の専門性の高さ
3-3. 従業員が情報共有に消極的なケース
3-4. 情報共有を促す仕組みが整っていない
3-5. 前任者からの引き継ぎが不十分
3-6. レガシーシステムの影響
レガシーシステムが原因で業務が属人化してしまうケースも考えられます。レガシーシステムとは老朽化・複雑化してしまった既存システムのこと。
新たな技術が次々に登場する現代、老朽化したシステムを放置していると複雑化が一層進んでしまい、社内の特定の人しか保守・運用を行えない状況に陥ってしまいます。

4. 業務を標準化(属人化を解消)するメリット
4-1. 業務効率の改善
4-2. ナレッジ・ノウハウの蓄積
4-3. 品質維持
4-4. テレワークへの対応
4-5. 人材流動化への対応
新卒一括採用に代表されるメンバーシップ型雇用が主流の日本企業は、人材の流動性が低いとされてきました。
しかし近年は、ジョブ型雇用の動きが活発化しているほか、働き方改革による多様な働き方の促進もあり、人材の流動性が高まりつつあります。
そうしたなか、業務が属人化していると人材の入れ替わりに対応するのは難しいと言えるでしょう。
一方、業務の標準化に取り組んでいれば、今後ますます活発化すると予想される人材の流動化にも対応することができるようになります。

5. 属人化解消の5つのポイント
5-1. ワークフロー(業務の流れ)の可視化
属人化の解消のポイントとして、ワークフロー(業務の流れ)の可視化が挙げられます。
まず、業務の一連の流れで発生する業務や、関係する部署や人物、やり取りされる情報(文書・データなど)を洗い出し、フローチャートを作成します。
そうすることで、どの業務がボトルネックになっているのか、特定箇所に集中している業務を分散できないか、あるいは業務の流れをシンプルにできないか、などの分析が可能になり、業務の改善につなげることができます。
5-2. 手順書・マニュアル作成
業務の流れを可視化することができたら、業務マニュアルを作成します。フローチャートよりもさらに具体的な内容になるため、実際の業務担当者に作成を依頼しましょう。
業務内容を把握していない社員でも理解できるよう、業務の手順やノウハウ、注意点など、できるだけ詳細かつ具体的に言語化することが大切です。
5-3. 継続的な評価・改善
5-4. 情報共有を促す仕組みを整備善
5-5. 業務の引き継ぎを徹底
6. 属人化を解消し標準化へ
6-1. 標準化とは
6-2. 標準化のメリット
業務の標準化には、先ほど紹介した属人化のデメリットを解消するようなメリットが多くあります。
属人化して一部の担当者にしかできなかった業務も、業務マニュアルをつくり標準化すれば誰でもこなせるようになります。
そうすることで、業務の不透明性も解消され、マニュアルさえチェックしていれば、誰もがプロセスから結果までを把握できるようになります。
その結果として、誰が担当しても同じレベルの業務をこなせるため、属人化した業務に比べ担当者の負担が減り、品質のばらつきも抑えることができます。
属人化した状態では難易度の高い休暇前の引き継ぎ作業も、基本の業務内容は始めから共有できているので容易になります。
そして誰でも業務を担当できるため、一部の人に負担が集中することがなくなり、働き方の質の低下も防げます。
一部の人の作業を待つ必要がなくなることで、全体の業務効率も上がります。
さらに、誰もが業務内容をチェックできるようになることで、ミスの発見・予防がしやすくなる他、より効率的な方法や高い品質を求めていくための改善点を見つけやすくなります。

7. まとめ
業務の属人化を解消するには、標準化が必要です。標準化とは、業務の流れを明確にし、誰でも同じ手順で業務を行えるようにすることです。
これにより、業務の効率化や品質の維持、ナレッジの蓄積など多くのメリットが得られます。属人化を解消し、組織全体として、効率よく業務を進めるための取り組みを始めましょう。
以上が、属人化解消支援に関する基本的な説明です。ご興味のある方は、ぜひ英知コンサルティング株式会社までお問い合わせください。
英知コンサルティングの実績
実績
407件
料金
ご面談・ご相談の上、最適なプランとお見積りをご提案いたします。
同時にご覧いただいているページ
ご相談・お問い合わせはこちら(無料)
コンサルティングのご依頼や、詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。ご相談は勿論、無料です。
お問い合せフォームでのお問合せは24時間受け付けております。
サイドメニュー
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー
Executive Consultant
清水 一郎
-------------------------------------
<専門分野>
経営再建、企業再生、経営戦略、営業戦略、マーケティング、間接部門改革、法務、財務、金融、会計、税務、監査、事業承継、IPO、資産運用、不動産、組織構築、人事制度、人事評価制度、目標管理制度
-------------------------------------