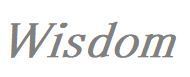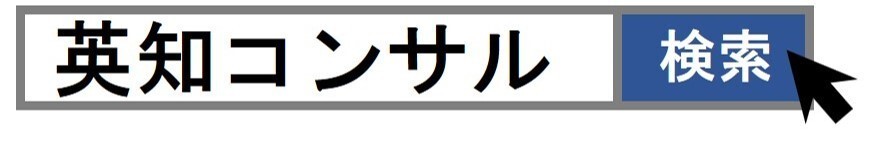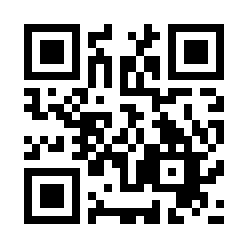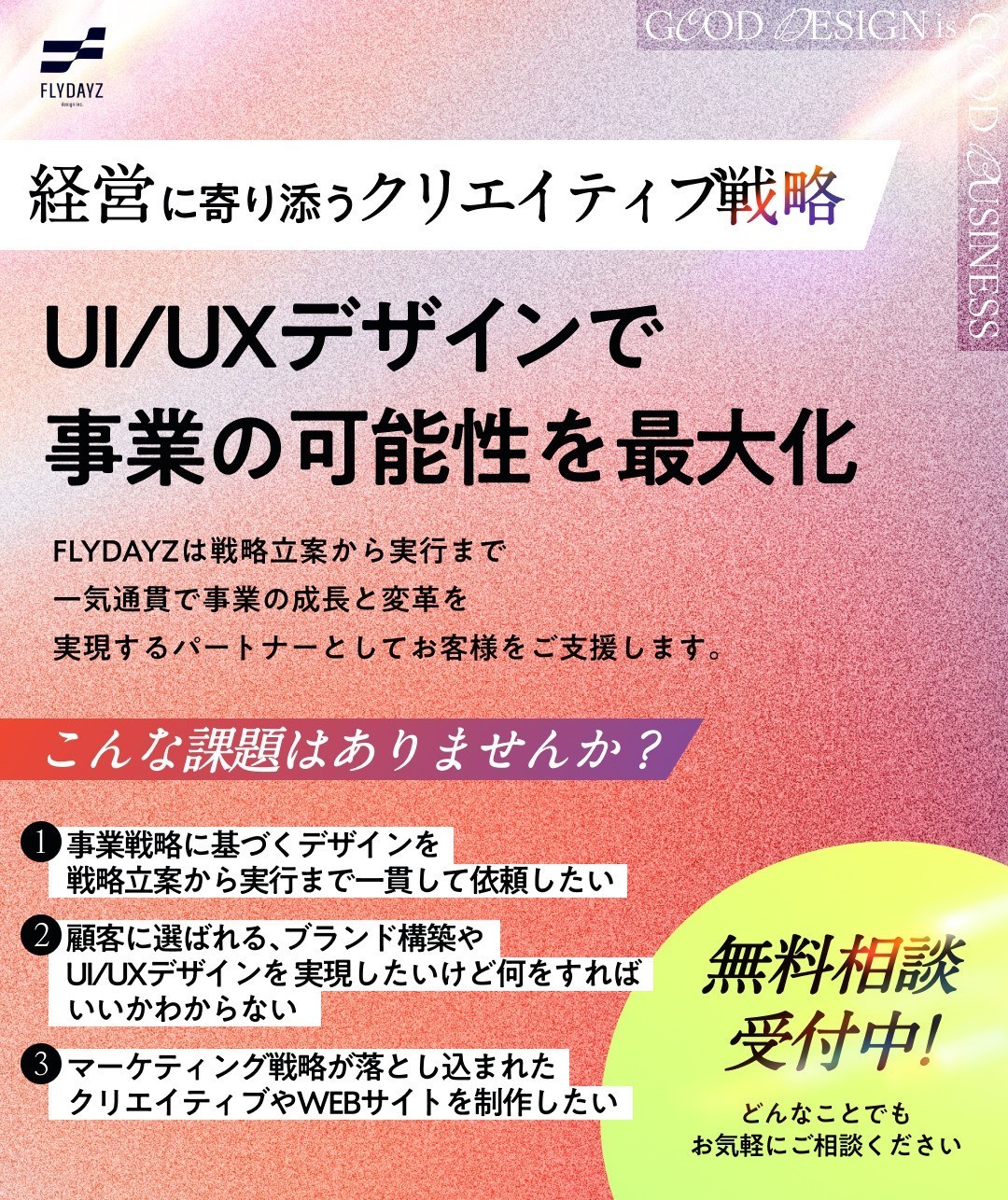中小企業・小規模事業者の経営コンサルティングは東京の英知コンサルティング株式会社(全国対応)
最終更新日 2024年08月17日
経理不正防止コンサル
経理不正防止コンサルなら東京の英知コンサルティング株式会社へ。
当社代表の 清水一郎 は、大手監査法人を経て、3社のCFO(最高財務責任者)として経理の不正防止対策を講じてきました。
その経験から、不正や横領などが起きる原因と手口、および対策をご説明いたします。
経理不正防止支援
<目 次>

1. 経理不正防止対策の基本的考え方
経理の不正防止のポイントをご説明する前に、その前提としておさえておいていただきたい「基本的な考え方」をご説明します。
それは、『従業員の不正・横領が起こりにくい仕組み作りは経営者の責任である』という考え方です。
従業員の横領・不正が起きた場合、横領額を従業員に請求することになりますが、横領が長期あるいは多額にわたることも多く、確実に全額を回収できるとは限りません。
また、場合によっては、納税にも影響がおよび、加算税などのペナルティーを受けることもあります。
さらに、不正を起こした従業員は解雇することになりますが、会社としては、また、新しい従業員の採用をしなければなりません。
このように考えると、横領・不正を起こさない仕組みを作ることは、会社の順調な経営のためには非常に重要であることがわかります。
不正を行う従業員が悪いのはもちろんのことですが、従業員が魔がさして経理の不正や横領に手を染めてしまわない環境づくりは「経営者の責任」であると考えなければ、不正や横領のない会社運営、安定した経営をすることはできません。
まずは、「従業員の横領・不正が起こりにくい仕組み作りは経営者の責任である」という基本的な考え方を確認したいと思います。
2. 従業員や経理による不正や横領が起きる原因
2-1. 不正や横領がしやすい環境にある
2-2. 不正や横領が発覚しにくい環境にある
2-3. 従業員が不正や横領を軽く考えている
2-4. 会計へのチェック体制が甘い
2-5. 経理担当者は悪いことをしないという思い込み
経理が一人しかいない中小企業も決して珍しくありません。経理を複数人雇用することは、人件費を支払えるだけの経済的な余裕がないと難しいためです。
会社によっては、新入社員の頃から何十年も経理を担当している場合もあります。付き合いが長く、通常業務も問題なくこなしていれば信頼するものです。ただ、信頼しすぎるとチェックが甘くなります。
また、経営者が経理の知識をあまり持っていないことも、良くない傾向です。経理担当者が「少々横領してもわからないだろう」と判断しても不思議ではありませんし、一度行ってバレなければ、以降、少額ずつ横領などをしてもバレないと考えるかもしれません。
経理担当者は、「横領なんて悪いことをするはずはない」という過度な信頼が経理の不正につながるケースもあるのです。
2-6. 経理担当者のモチベーション低下
経理担当社員に対し、不満が溜まるような扱いをしている会社も少なくありません。例えば、経理という仕事を、経営者が軽く見ているケースです。
本来、経理は会社の運営を支える重要な部署ですが、中には軽んじられているケースもあります。
会社で花形部署といえば、営業が挙げられるでしょう。「大きな契約を受注した」「新規取引先を開拓した」、このような業績を上げれば、華々しい評価を受けます。
ところが、経理の仕事は「お金の計算をしているだけ」と見られることもあります。
業務に対する適切な評価を与えられなかったり、その他の部署と比べて簡単な仕事をしていると見られたり、待遇が他部署と比べ低かったりすれば、モチベーションが低下してしまうのも無理はないと言えます。
「営業部門が管理部門を食わしてやっている」と、うそぶく営業社員を、わたしは何人も見てきました。
経理の仕事を担当したことのない、営業や技術系の社長が、経理を単に「お金の計算をしているだけ」と軽視することで、経理担当が不満を募らせ、モチベーションが低下し、復讐として横領をするケースもありました。

3. 従業員や経理担当者による不正や横領の手口
3-1. 小口現金やレジ現金の抜き取り
3-2. 預金の不正送金や不正引き出し
3-3. 水増し請求によるキックバック
3-4. 仮払金、仮受金を用いた不正や横領
仮払金勘定、仮受金勘定は不正や横領の温床になりやすい科目です。支払先や支払内容が不明または明らかにしたくない場合などに仮払金勘定が使われます。
また、受取先や受取内容が不明または明らかにしたくない場合などに仮受金勘定が使われます。やむを得ず、仮払金勘定、仮受金勘定を使用することは実務上ありますが、不正の温床になりやすいという認識が必要です。
例えば、仮払金勘定に多額の金額を計上し、実際には使っていないにも関わらず使ったように見せかけて現金を抜き取る手口です。
仮払金勘定、仮受金勘定が長期間にわたり未処理の場合は、速やかな原因究明が必要です。
また、安易に現金過不足勘定を使用させないことも大切です。万一、現金過不足勘定を使用する場合には、速やかに上司に報告させるルール化が必要です。

4. 従業員や経理による不正や横領の防止対策
4-1. コンプライアンス研修の実施
従業員に対して定期的にコンプライアンス研修を実施し、不正行為の重大さとそのリスクを理解させることが重要です。不正が発覚した場合の処罰についても明確に伝えることで、抑止力を高めることができます。
横領の発生事例や、横領をした従業員のその後の処遇(刑事罰の対象となったケースや、損害賠償請求をされたケースなど)を紹介することで、横領の抑止力につながります。
また、コンプライアンス研修を定期的に実施することで、会社が横領を許さないとの意思が伝わり、この点でも抑止力となるでしょう。
ただし、当然ながら横領などに手を染めず真面目に業務に励む従業員や経理担当者も多い中、あまりにも研修に力を入れてしまうと、疑われていると感じた従業員が業務への意欲を失ってしまいかねません。
そのため、研修の開催頻度や研修内容については慎重に検討することが必要です。
4-2. 就業規則の懲戒規程の見直し
4-3. ダブルチェック体制を整える
経理業務において、複数人によるダブルチェック体制を整えることが重要です。例えば、現金の取り扱いや銀行口座の管理など、重要な業務については複数人が関与し、互いにチェックし合う体制を構築します。横領を防止するためには、可能な限り横領をしづらい環境を作ることが重要です。
そのための対策の一つとして、現金や預金を取り扱う業務について、ダブルチェック体制を整えることが挙げられます。
経理担当者が一人で預金口座から振込みができたり、金庫から現金を取り出したりできない仕組みにすることが、不正や横領の防止につながります。
経理業務を一人の担当者に任せてしまうと、経理業務がブラックボックス化しやすくなります。ブラックボックス化した状態は、不正や横領に手を染めやすい状態であり、不正や横領の発見が遅れ、取り返しのつかない状態を招きかねません。
まず、小口現金に関してです。小口現金を利用している会社は多いですが、小口現金出納帳など、帳簿の管理やチェックが甘いと横領が起こりやすくなります。
実際、帳簿に記載された残高と実際の現金が一致しているかのチェックが適切に行われなかったために横領が起きたケースもありました。
対策として小口現金管理担当者に「出金伝票と請求書や領収書などのエビデンスの提出がないと支払わない」というルールを徹底することが重要です。
ただし、小口現金管理者の横領は防げません。そのため、小口現金管理者以外にチェック担当者を設けます。業務が終わったら毎日、出金伝票をチェックさせます。
また、帳簿の残高と実際の現金が一致しているかどうかもチェックします。
次に、預金に関してです。経理担当者が預金口座の入・出金を一人で完結できる仕組みは、不正や横領の大きな原因になりますので、直ちに改善が必要です。例えば、預金通帳と銀行印の管理者を分けるだけでも不正防止に効果があります。
また、ネットバンキングを利用しているなら、振込送金を一人では行えない対策が必要です。送金担当者とカードの管理者を分けるだけでも効果があります。
ワンタイムパスワードを利用しているなら、送金担当者とワンタイムパスワード管理者を分けるのも一つの方法です。また、振込に当たっては、上司による承認を必要とする設定にすることも重要です。
共通するのは「一人では引き出せない、振込送金ができない仕組み」を構築することです。
こうした仕組みが運用されれば、横領という考えが頭をよぎっても「どうせばれる」と思い直す可能性が高くなるため抑止力になります。
また、たとえ横領が起きなかったとしても、その経理担当者が急に退職や休職する必要が生じた際に、社内が大きな混乱に陥ってしまう可能性があります。
そのため、経理はチーム制として、ブラックボックス化を避ける対策が必要でしょう。

4-4. 現金は当日中に銀行口座へ入金する
現金をできるだけ早く銀行口座に入金することで、現金の管理を厳密に行います。現金が手元に長期間残ることがないようにすることで、不正行為のリスクを減らします。
横領を防止するためには、従業員が現金に触れる機会をできるだけ減らすことがポイントです。そのため、現金売上のある業種であれば、レジスター内の現金をできるだけ速やかに銀行口座へ入金するルールを構築する必要が重要です。
横領を防ぐには「当日、売り上げた現金は当日中に預金口座へ必ず入金する」といったルールが有効です。店舗に置いたままだと、横領の可能性だけでなく、盗難の恐れもあります。
また、入金担当者以外の従業員が、売上報告をすることも牽制効果があります。本社の経理担当者は報告を受けた金額と入金された金額が一致するか、定期的にチェックするのです。
当日中に入金とチェックをしないと、売上金と入金額が違っていても不正かどうか判断しづらくなります。
さらに、現金過不足ができるだけ発生しないよう従業員教育を徹底したり、レジスター内の現金を銀行へ入金する作業を一人で行わないようルール化するのも効果的です。
4-5. 小口現金を廃止する
可能な限り小口現金を廃止し、全ての支払いを銀行振込やクレジットカードで行うようにします。現金の取り扱いを減らすことで、不正行為のリスクを大幅に減らすことができます。
小口現金とは、日々の業務で発生する細かな支払いに使うため、金庫などで常備しておく現金のことです。
中小企業ではこの小口現金にまで管理が行き届かないことも多いため、現金化不足が発生しやすく横領の温床となる可能性があります。
そのため、可能であれば小口現金自体を廃止することも検討するとよいでしょう。
例えば、支払いには原則として法人カードを使用したり、やむを得ず現金払いをする際には立替経費として銀行振込で精算するルールにすることにより、小口現金の廃止が可能になります。
4-6. 入出金履歴を定期的に確認する
銀行口座の入出金履歴を定期的に確認し、不審な取引がないかをチェックします。定期的なチェックを行うことで、不正行為が早期に発見される可能性が高まります。
経営者が自社の通帳や入出金履歴を定期的に確認することも横領の防止には効果的です。経営者が自社のお金の流れを理解し注視しているとの姿勢を見せることが、横領の抑止力となるためです。
また、万一、横領が発生した際にも帳簿上の預金残高との差異や不審なお金の流れに気づきやすく、横領を早期に発見しやすくなります。
定期的に通帳をチェックする、これが一番簡単で重要な対策です。通帳をチェックすれば「いつ、何円」引き出されたかがわかります。
通帳をチェックする担当者は社長でもいいですし、上位の社員でもいいでしょう。支払いに対応する出金伝票と請求書などのエビデンスがあるかを必ずチェックすることが重要です。
問題はチェック担当者が一人しかいない場合です。チェック担当者もグルになれば問題は簡単には露見されません。チェック担当者を固定せず、毎日チェック担当者を変えるのも対策になります。

4-7. 各種帳簿の整備
各種帳簿を整備し、正確な記録を保つことが重要です。帳簿の記録が曖昧であったり、不備があると不正行為が発覚しにくくなります。定期的な帳簿の見直しと整備を行うことが必要です。
いわゆる「どんぶり勘定」では、経理の不正が起きやすくなります。そのためには、入金伝票や出金伝票、または現金出納帳、小口現金出納帳などの帳簿を作成し、お金の流れを記録しておくことも重要です。お金の流れを正しく理解していないと、不正が起きていたとしてもすぐに気づくことができません。
また、日々、現金実査を実施し、金種表を作成することも重要です。
現金の残高、申請する現金の金種などが把握できます。また、作成して終わりではなく、社長など作成者より上位の立場の人が承認する体制を整えておくことも不正がしづらい組織づくりとして有効です。
4-8. 切手や印紙類の管理
4-9. 内部監査部門の設置
内部監査部門を設置し、定期的に経理業務の監査を行うことで、不正行為の発見と防止を図ります。内部監査部門があることで、従業員に対して不正行為に対する抑止力を高めることができます。
社長直属の内部監査部門を設置することで、内部牽制機能が強化されます。内部監査部門は、社長に代わって、各部門の業務が法令や社内規程などの定め通りに行われているかを監査する部門です。
社長の命に従って監査を行う独立性と強制性のある部門です。
內部監査を実施することで、不審な点を見つけやすくなるでしょう。
経営者の立場だと、従業員を疑っているような気持ちになるかもしれませんが、経理での不正を長期間見逃せば、被害額が数億円に及ぶことも少なくはなく、経営に重大な結果を及ぼす結果になりかねません。
また、支店がある会社では抜き打ち監査も有効でしょう。支店には社長が常駐していません。チェックが甘いと判断し、不正経理に手を染める人が出やすい環境にあります。抜き打ち監査なら、不正の証拠を発見しやすいため、対策としてはたいへん有効です。
4-10. 役員や幹部社員は不正や横領をしないか?
4-11. 「社長は細部まで見ているぞ!」というサインを出す
わたしがCFO(最高財務責任者)時代に実際に行った不正防止の牽制方法を紹介します。財務本部の入口に、社員ならば誰でも見ることのできる掲示板を設置しました。普段は財務本部からのお知らせなどが貼ってある掲示板です。
その掲示板に、次のような資料を貼り出していました。
・会社支給の携帯電話の通話記録
・インターネットのログ記録
・接待費の領収書
・商品仕入れの請求書 などです。
資料には直径5cmもある大きな「CFO印」が目立つように押してあります。これを目にした社員たちはどう感じるでしょうか?
大半の社員は「CFO(最高財務責任者)は、こんな細かいところまで見ているのか!」と感じたと言います。つまり、これらの掲示物は、社員に不正などをさせない牽制となっていたのです。
これは大企業の例ですので、中小企業の場合は「社長印」を押して掲示します。
このように牽制することで、社員に対し「社長は細かなところまで見ているぞ!」というサインを出すことができ、不正などを思いとどまらせる効果があるのです。
4-12. 外部機関の監査を受ける
定期的に外部の専門機関による監査を受けることで、経理業務の透明性と信頼性を確保します。外部監査によって、内部では気付かない不正行為や不備が発見される可能性があります。
中小企業の多くは、定期的に税理士に会計帳簿を見てもらっていますが、税理士は「税」の専門家であって「監査」の専門家ではありません。
従って、税理士が従業員や経理による不正や横領を発見することは滅多にありませんし、また期待すべきでもありません。
一方、公認会計士は「監査」の専門家ですので、誤謬、不正および横領などを見つける知識と能力をもっています。
内部監査と併せ、毎月または四半期のペースで、公認会計士の監査を受けることで、不正に対する抑止効果が大きくなります。

5. まとめ
ダブルチェック体制を整えたり、ブラックボックス化を避けたり、内部監査部門を設置するなどの対策が不正や横領の防止に有効とはいえ、人員や資金に余裕のない中小企業にとっては、ハードルが高く感じるかもしれません。
そうした意味からも、外部機関による定期的な監査は、コストパフォーマンス上も現実的と考えられます。
弊社(英知コンサルティング株式会社)では、公認会計士やCIA(公認内部監査人)、および企業でCFO(最高財務責任者)や内部監査部門経験者などによる経理の不正防止支援と監査を承っております。
ご興味のある方は、ぜひ英知コンサルティング株式会社までお問い合わせください。
英知コンサルティングの実績
実績
463件
料金
ご面談・ご相談の上、最適なプランとお見積りをご提案いたします。
同時にご覧いただいているページ
ご相談・お問い合わせはこちら(無料)
コンサルティングのご依頼や、詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。ご相談は勿論、無料です。
お問い合せフォームでのお問合せは24時間受け付けております。
サイドメニュー
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー
Executive Consultant
清水 一郎
-------------------------------------
<専門分野>
経営再建、企業再生、経営戦略、営業戦略、マーケティング、間接部門改革、法務、財務、金融、会計、税務、監査、事業承継、IPO、資産運用、不動産、組織構築、人事制度、人事評価制度、目標管理制度
-------------------------------------