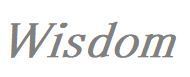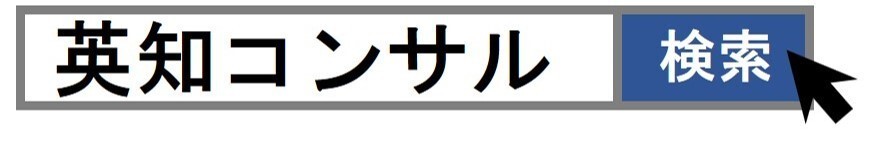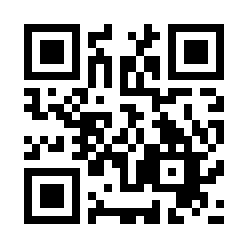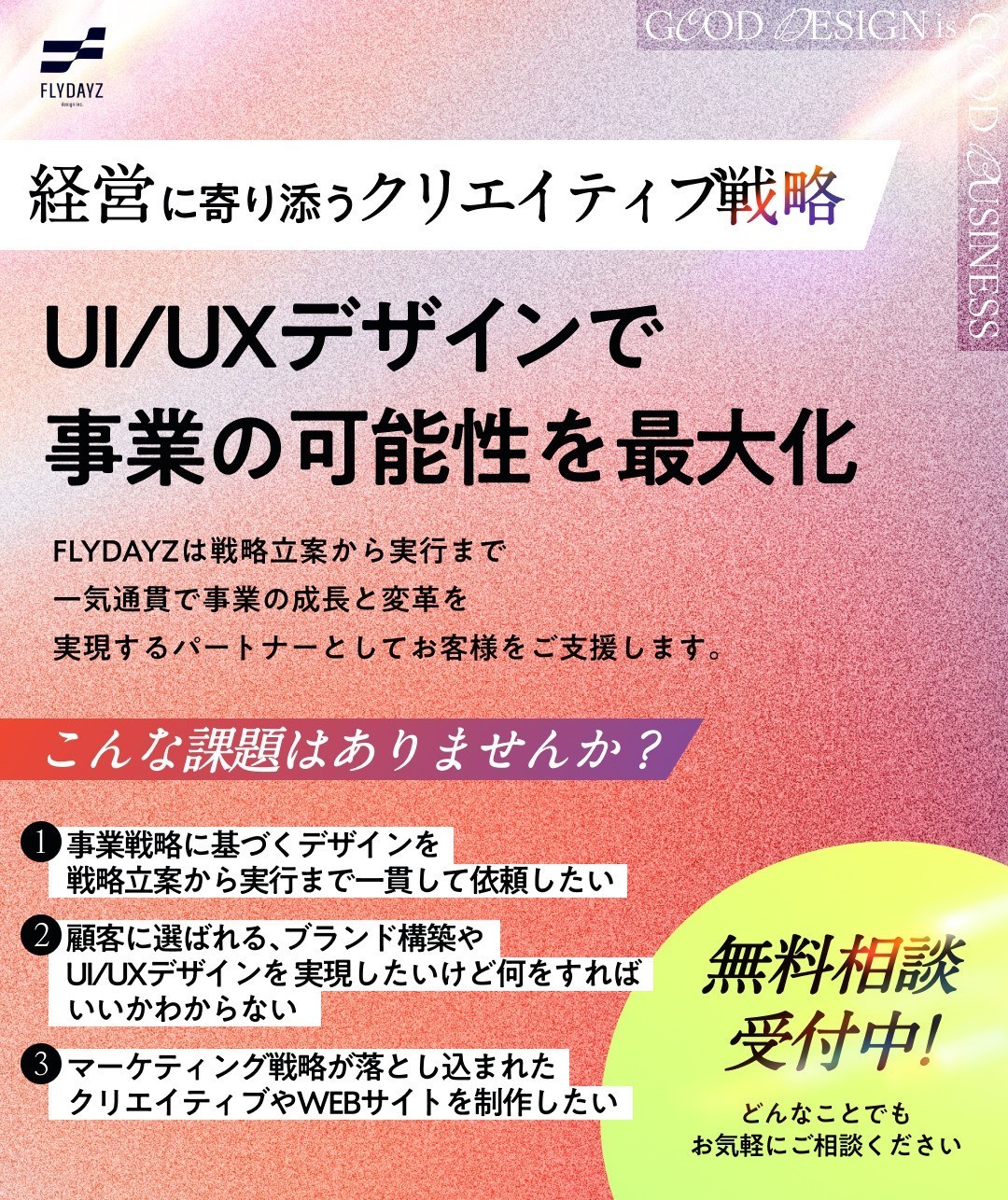中小企業・小規模事業者の経営コンサルティングは東京の英知コンサルティング株式会社(全国対応)
最終更新日 2024年05月30日
間接部門・管理部門改革
間接部門・管理部門改革は東京の英知コンサルティング株式会社へ。
間接部門・管理部門改革のポイントは「業務の俗人化」を排除し「業務の見える化」を達成することです。
そのためには、間接部門のDXの推進が最も有効な手段になります。当社代表の 清水一郎 は、3社の上場企業で「間接部門改革」を成功させた実績があります。
その成果は、「日経ビジネス」などのビジネス誌でも紹介されております。
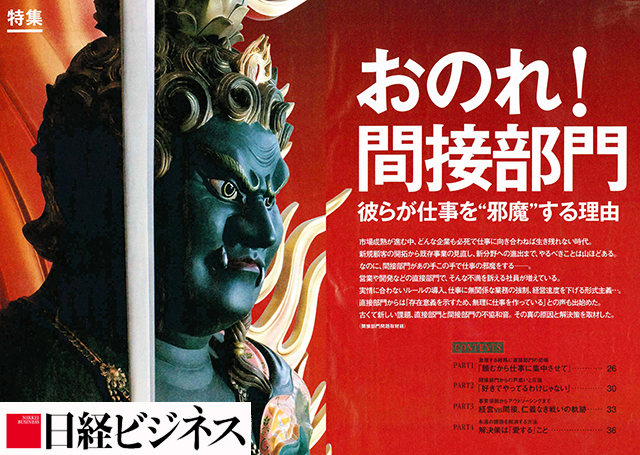
間接部門の役割
直接部門と間接部門の役割の違い
直接部門(プロフィットセンター)とは、製品やサービスの製造や提供に直接関与する部門のことを指します。例えば、生産部門や営業部門などが直接部門に当たります。
一方、間接部門(コストセンター)とは、企業全体の支援や管理を行う部門のことを指します。例えば、人事部門・会計部門・法務部門・総務部門などが間接部門に当たります。
直接部門は、製品やサービスを生み出すための主要な機能を担っており、企業の収益に直接影響を与えます。
一方、間接部門は、企業全体の円滑な運営を支援する役割を担っており、企業の生産性や効率性を向上させることが目的です。
間接部門とは
間接部門とは、製造業、販売業、サービス業などの企業において、製品やサービスの生産・営業活動に直接関わらない、間接的な業務を担当する部門のことを指します。
具体的には、人事・総務、法務、経理・財務、情報システム、広報・PR、品質管理などが挙げられます。
これらの部門は、直接的に製品やサービスを提供する業務を行っている部門とは異なり、企業全体の管理や支援を担当しています。
間接部門は、企業の業務の中で非常に重要な役割を果たしています。
例えば、人事・総務部門は従業員の雇用や労働環境の整備を担当し、法務部門は企業活動に必要な法律問題の解決やリスク管理を行います。
経理・財務部門は企業の資金管理や財務戦略の策定を担当し、情報システム部門は情報システムの導入や運用を行い、業務プロセスの改善を支援します。
企業にとって、間接部門と直接部門の両方がバランスよく機能することが重要であり、両者の連携を図りながら、経営戦略の実行を進めることが求められます。
間接部門の役割
間接部門には、企業全体の管理や支援を行うための役割があります。具体的には、次のような役割が挙げられます。
1.人事・総務部門
・従業員の採用や配置、教育・研修などの人事業務を担当
・社員の労働環境整備、福利厚生や労働条件の策定などを行う
2.法務部門
・企業活動に必要な法律問題の解決やリスク管理を担当
・契約書の作成や取引先との交渉などの業務を行う
3.経理・財務部門
・企業の資金管理、財務戦略の策定を担当
・決算や税務申告などの財務関連業務を行う
4.情報システム部門
・情報システムの導入や運用を行い、業務プロセスの改善を支援
・ITセキュリティの管理やサポート、情報システムの監視や保守などを行う
5.広報・PR部門
・企業のブランド戦略やイメージアップを担当
・メディア対応やイベントの企画運営など、広報・PR活動を行う
6.品質管理部門
・製品・サービスの品質管理を担当
・品質改善活動や顧客対応などを行い、企業の信頼性向上に貢献する
これらの間接部門は、それぞれが独自の専門知識やスキルを持っており、企業の業務を支援することで、直接部門の生産性や顧客満足度の向上につながっています。

間接部門の課題分析
間接部門の業務課題
間接部門は、企業のコアビジネスに直接関係しない業務を担当する部門です。そのため、次のような業務課題が生じることがあります。
1.コスト削減のプレッシャー
間接部門は、コストセンターであり、直接的な収益には直結していません。そのため、経営層から、コスト削減のプレッシャーが強く要求されるケースが多くあります。
2.業務プロセスの改善
間接部門の業務プロセスが適切でない場合、業務の効率性が低下することがあります。業務プロセスを改善し、効率的に業務を行うことが求められます。
3.コミュニケーションの課題
間接部門は、企業内の他の部門と密接に連携する必要があります。しかし、部門間のコミュニケーションに課題がある場合、業務の効率性が低下することがあります。
4.スキル・人材不足
間接部門の業務には、専門的なスキルが必要な場合があります。しかし、スキルや人材不足によって、業務の遂行が難しくなることがあります。
5.リスク管理の課題
間接部門には、リスク管理の業務も含まれます。しかし、リスク管理の専門的な知識がない場合、リスク管理が不十分になることがあります。
間接部門の問題点
間接部門には、以下のような問題点が存在することがあります。
1.コストの増加
間接部門は、生産や営業といった業務とは直接的な関係がないため、コストが増加する可能性があります。経理、法務、人事などの部門は、事務作業や手続きが必要であり、これらに関連するコストが高いことがあります。
2.業務プロセスの複雑化
間接部門が、直接的な業務と密接に関係していない場合、業務プロセスが複雑化する可能性があります。部門間での情報共有や調整が必要となり、業務の効率性が低下する場合があります。
3.コミュニケーションのミス
直接部門と比較して、間接部門は情報伝達の障壁が高いことがあります。特に、異なる部門や拠点、国などに所在する場合、コミュニケーションのミスが生じることがあります。
4.機能の重複
間接部門は、異なる部門や拠点、国などに所在する場合、同じような機能を複数の部門が持つことがあります。これにより、業務プロセスが複雑化し、業務の効率性が低下する場合があります。
5.成果の測定が難しい
間接部門は、直接部門と比較して、成果の測定が難しいことがあります。
たとえば、人事部門は、社員の満足度や離職率などを測定することができますが、業績に直接的な影響を与えるわけではありません。これにより、間接部門の業績評価(人事考課)が困難になる場合があります。
6.間接部門の俗人化
間接部門の仕事は「その仕事は誰々にしかできない」という俗人化しやすことが、最大の問題点です。
そうならないためにはITシステムなどを導入し作業手順を「見える化」するのが有効な手段です。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進は、俗人化を防ぐツールになります。

間接部門の俗人化
「間接部門の俗人化」とは、企業内での間接部門(経理、人事、広報、法務など)において、その業務内容やスキルセットが低下し、質が劣化する現象を指します。
これは、間接部門の業務に特化した専門的な知識やスキルが、企業にとって必要不可欠なものであるにもかかわらず、その業務が単純化され、一般的な事務処理やルーティンワークに集中することによって起こります。
また、間接部門における人員の削減や給与の引き下げなどによって、質の高い人材が退職し、採用が困難になることも一因として挙げられます。
間接部門の俗人化が進むと、企業内部での業務効率や品質が低下することになり、結果として企業の競争力の低下や、顧客からの信頼の失墜など、様々な問題を引き起こす可能性があります。
間接部門の評価
間接部門の評価にはいくつかの方法がありますが、一般的な方法は以下の通りです。
1.目標設定に基づく評価
間接部門には、目標設定に基づく評価が適用されることがあります。この場合、間接部門に対して目標が設定され、その目標を達成したかどうかで評価されます。
例えば、間接部門にはコスト削減の目標が設定され、その目標を達成するための取り組みや成果が評価されることがあります。
2.顧客満足度に基づく評価
間接部門が関わる業務やプロセスが、顧客満足度に影響を与える場合、顧客満足度に基づく評価が行われることがあります。
例えば、間接部門が製品の出荷手配や顧客対応を行う場合、その業務が顧客満足度にどの程度影響を与えたかが評価されます。
3.コスト効率に基づく評価
間接部門には、コスト効率に基づく評価が適用されることがあります。この場合、間接部門が担当する業務やプロセスにかかるコストを削減するための取り組みや成果が評価されます。
4.プロジェクト成果に基づく評価
間接部門が、あるプロジェクトの一部として関わる場合、そのプロジェクトの成果に基づく評価が行われることがあります。
例えば、間接部門が製品の開発プロジェクトに関わる場合、そのプロジェクトの成果や進捗状況に応じて評価されることがあります。
これらの評価方法は、単独でも組み合わせても利用されることがあります。評価方法は、間接部門が担当する業務やプロセス、目的に応じて選択されることが重要です。
間接部門の待遇
間接部門の待遇は、企業や組織によって異なりますが、一般的には直接部門に比べて低い傾向が多いです。
これは、直接部門が企業の主要な業務を担っているため、直接的な貢献が見込めることや、市場価値が高いことが理由の1つです。
ただし、近年は間接部門の重要性が高まっており、その役割が企業の成長や競争力に直接関わっていることが認識されつつあります。
そのため、企業によっては、間接部門の待遇改善やキャリアアップの機会を増やすなど、より公平な待遇を提供する取り組みを行っている企業もあります。
また、間接部門の待遇改善には、業務内容の見直しや生産性向上、スキルアッププログラムの提供、報酬制度の見直しなどが必要です。
企業が間接部門の待遇改善に積極的に取り組むことで、従業員のモチベーションや生産性を向上させることができ、企業全体の成長につながる可能性があります。

直接部門が間接部門を見下す
直接部門が間接部門を見下すことは、多くの企業でよく見られる問題の一つです。
例えば、営業部門の中には、「営業部門が上で、間接部門は下」、「営業部門が間接部門を食わしている」といった意識を持っている経営者や営業社員は決して少なくありません。
このような状況は、双方の部門が互いに理解し合うことなく、業務上の役割や責任範囲について誤解していることが原因となることが多いです。
直接部門が間接部門を見下すことによって、業務の連携や情報共有がスムーズに行われず、組織全体のパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。
また、間接部門の従業員がモチベーションを失い、仕事へのやる気やパフォーマンスが低下することもあります。
このような問題を解決するためには、組織全体で相互理解を深めることが必要です。直接部門と間接部門の役割や責任範囲を明確にし、業務上の関連性や依存関係を把握することが重要です。
また、コミュニケーションを改善し、情報共有を促進することで、部門間の信頼関係を築くことができます。さらに、組織全体で目標や価値観を共有し、協力して業務に取り組むことが、部門間の健全な関係を築く上で重要です。
「営業第一主義」ではなく、「顧客第一主義」、「社員第一主義」といった価値観を持つ企業が健全であると考えられます。
間接部門の人材流失理由
間接部門の人材流出理由にはいくつかの要因があります。以下は一般的な理由のいくつかです。
1.キャリアアップの機会の欠如
間接部門は、直接顧客にサービスを提供する部門に比べて、キャリアアップの機会が少ないことがあります。
これは、業務内容が間接的であるため、業務に関連する知識やスキルの習得に限界があるためです。そのため、従業員は、より良いキャリアアップの機会を求めて、他の企業や部門に移ることがあります。
2.報酬の低さ
間接部門の従業員は、企業の利益に直接的に貢献する機会がほとんどないため、報酬が低い場合があります。
また、業績に応じたインセンティブや昇給の機会が少ないこともあります。そのため、他の企業や部門に比べて報酬が低い場合、従業員は別の職場を求めることがあります。
3.ワークライフバランスの悪化
間接部門の従業員は、直接顧客にサービスを提供する部門に比べて、業務の緊急性や時間的な制約が少ないことがあります。
しかし、業務量が増え、残業や休日出勤が増えると、ワークライフバランスが悪化し、ストレスや不満を感じることがあります。そのため、従業員は、ワークライフバランスが良い企業や部門に移ることがあります。
4.社内文化の不一致
間接部門の従業員は、直接的に顧客にサービスを提供する部門に比べて、社内文化が異なることがあります。
例えば、コミュニケーションや協調性を重視する部門に所属する従業員が、個人の業績や競争を重視する部門に異動した場合、社内文化の違いからストレスを感じることがあります。そのため、従業員は、自身に合った社内文化の企業や部門を求めることがあります。
間接部門のムダ
間接部門におけるムダとは、価値を生み出さない活動や無駄な時間・コストを指します。具体的には、以下のようなものが挙げられます。
1.待ち時間(業務の進捗を妨げるために待っている時間)
2.過剰な運用(必要以上の業務を行うこと)
3.非効率的なプロセス(遅い、手順が複雑、情報が不足している等)
4.ミスや欠陥(業務の品質を下げるミスや欠陥)
これらのムダは、生産性を低下させるだけでなく、企業のコストも増加させます。したがって、間接部門のムダを削減することは、企業の収益性向上や競争力強化につながります。

間接部門改革のプロセス
間接部門改革のプロセス
間接部門改革のプロセスには、次のようなものがあります。
1.プロセスの見直し
業務プロセスを見直し、非効率な部分を特定し、改善することが重要です。プロセスに無駄がある場合は、効率化を図るために再設計することができます。
2.自動化の導入
業務を自動化することで、間接部門の効率化を図ることができます。例えば、業務の自動化により人的ミスを減らすことができ、業務効率を改善することができます。
3.外部の専門家の導入
外部の専門家(経営コンサルタントなど)にアドバイスを求めることで、業務の改善を促進することができます。例えば、効率的なプロセスの見直しや自動化についてのアドバイスを受けることができます。
4.チームのトレーニング
業務プロセスの改善に加えて、従業員のスキル向上を図ることも重要です。トレーニングを受けた従業員は、業務の効率化に寄与することができます。
5.KPIの設定
業務の効率化を測定するために、KPI(Key Performance Indicators)を設定することが重要です。KPIを設定することで、業務の改善点を見つけることができ、改善のための取り組みを促進することができます。
これらの方法を組み合わせることで、間接部門改革を効果的に行うことができます。ただし、改革を行う前に、現状を分析し、問題点を特定することが重要です。
間接業務の改善プロセス
間接業務の改善のプロセスにはいくつかのステップがあります。一般的なプロセスは次の通りです。
1.問題の洗い出しと目標の設定
間接業務の問題を洗い出し、改善の目標を設定します。問題は、現状の業務プロセスにおける課題、非効率な部分、生産性の低下などです。改善の目標は、具体的で測定可能なものであることが重要です。
2.原因分析
問題を引き起こす原因を特定し、問題解決に向けたアプローチを考えます。原因分析には、ルートコーズ分析(根本原因分析)などのツールを使用することができます。
3.解決策の検討
原因分析を踏まえて、問題解決に向けた解決策を検討します。解決策は、問題解決のために具体的かつ実現可能であることが求められます。
解決策は、関連する部署やステークホルダーと協力して検討することが望ましいです。
4.解決策の実施
解決策を実施するために必要な手順を明確にします。実施手順には、スケジュールや担当者、予算などが含まれます。
また、実施にあたっては、試験運用を行うことで、問題が発生しないか確認することが重要です。
5.成果の評価
改善活動の成果を評価し、目標に対する達成度を確認します。また、改善によって生じた副次的な影響や問題も洗い出し、必要に応じて改善活動を再度実施することが重要です。
6.継続的な改善
改善活動は一度で終わりではありません。継続的な改善を行い、常に業務プロセスを改善していくことが重要です。
定期的に業務プロセスを見直し、問題を洗い出して改善活動に取り組むことが望ましいです。

間接部門改革のステップ
間接部門改革は、次のようなステップを考慮することが重要です。
1.プロセスの分析
まず、間接部門のプロセスを分析し、その効率性と現状の問題点を特定します。プロセスマップを作成し、プロセスの進行状況と課題を明確にします。
2.目標の設定
改革の目標を設定します。目標を設定することで、改革が何を達成しようとしているのか明確になり、方向性が定まります。
3.チームの組成
間接部門改革のために、改革の責任者を任命し、専門チームを編成します。チームメンバーは、改革に必要な専門的な知識やスキルを持ち、意欲的であることが望ましいです。
4.オペレーショナルエクセレンスの原則の導入
オペレーショナルエクセレンスの原則を導入することで、プロセス改善を進めます。具体的には、品質向上、生産性の向上、リーンマネジメントの原則の導入などがあります。
5.技術的な改善
改革を成功させるために、技術的な改善を進めます。自動化、ITシステムの導入、ツールの更新など、技術的な改善によりプロセスの効率性が向上することが期待できます。
6.コミュニケーションと教育
改革の成果を最大化するために、チーム内のコミュニケーションを改善し、必要な場合にはトレーニングや教育を提供します。従業員が改革の目的や進捗状況を理解していることが重要です。
7.結果のモニタリング
改革の結果をモニタリングし、目標に向けて進捗状況を確認し続けます。改善すべき点を把握し、必要に応じて戦略を修正します。
これらのステップを順序立てて進めることで、間接部門の改革を成功させることができます。していく必要があります。問題点が再発しないように、定期的な監視と改善を継続的に行います。
間接業務の改革を阻む要因
間接業務の改善を阻む要因はいくつかありますが、次にその例を挙げます。
1.情報の欠如
間接業務に関する情報が不十分である場合、改善を行うことができません。例えば、業務プロセスの明確なマップや、必要なリソースの明確な定義がない場合、改善を行うことは困難です。
2.コミュニケーションの問題
改善を行うためには、関係者間の良好なコミュニケーションが必要です。しかし、部署間のコミュニケーションが不十分であったり、情報共有が行われていなかったりする場合、改善を行うことはできません。
3.システムやツールの不備
間接業務を効率的に改善するためには、適切なシステムやツールが必要です。しかし、システムやツールが古くなっていたり、使いにくかったりする場合、改善を行うことは困難です。
4.組織文化の問題
改善を行うためには、組織全体の文化が「改善志向」であることが必要です。しかし、改善を行うことが難しい文化や、改善に取り組むことが重要視されていない組織では、改善を行うことは困難です。
5.リソースの不足
改善を行うためには、十分なリソースが必要です。しかし、予算の不足や人員の不足など、必要なリソースが十分に確保されていない場合、改善を行うことは難しくなります。

新時代の間接部門
新時代の間接部門のあり方
新時代における間接部門のあり方には次のような特徴があります。
1.デジタル化
デジタル技術の進化により、間接部門でも自動化やAI技術を活用した業務改善が進んでいます。例えば、請求書処理や人事管理など、ルーティン業務は自動化することができます。
2.顧客志向
間接部門における業務は、顧客のニーズに合わせたサポートを提供することが求められます。例えば、マーケティング部門は顧客のニーズを分析し、プロモーション戦略を立てることが重要です。
3.マルチスキル化
オールラウンドなスキルを持った人材が求められます。例えば、営業部門の社員は、ビジネスモデルの理解だけでなく、プレゼンテーション能力やテクニカルスキルなど幅広いスキルを持っていることが望まれます。
4.コラボレーション
間接部門の業務は、企業全体の成長に直接的な影響を与えるため、他の部門との協力が不可欠です。例えば、生産部門や物流部門と協力して、在庫管理を改善することが重要です。
5.柔軟性
時代の変化に合わせて、間接部門の業務も柔軟に対応できる体制を整える必要があります。例えば、新たな業務が発生した場合でも、既存の業務と併せてスムーズに対応できるようにすることが望まれます。
6.革新的な発想
新たな課題に対して、従来の枠組みにとらわれない発想が求められます。例えば、環境問題に対応するために、間接部門でエコロジーに配慮した取り組みを推進することが重要です。
これらの特徴を踏まえて、間接部門はより高度化したサポートを提供し、企業の成長に貢献していくことが期待されます。

間接部門のDX
間接部門のDXとは、間接部門におけるデジタルトランスフォーメーションのことを指します。
間接部門は、企業内の生産やサービス提供に直接的には関わらない部署であり、一般的には管理部門や支援部門と呼ばれます。例えば、人事部門や財務部門、法務部門、広報部門などが含まれます。
間接部門におけるDXは、業務プロセスの自動化や効率化、データの活用、情報共有の促進などを通じて、業務の改善や付加価値の向上を目指すものです。
具体的には、次のような取り組みが挙げられます。
・ワークフロー自動化
・電子契約・電子承認システムの導入
・データ分析による業務プロセスの改善
・クラウドサービスの活用による業務効率化
・コラボレーションツールの導入による情報共有の促進
・セキュリティ対策の強化
これらの取り組みによって、間接部門における業務の効率化や品質の向上が期待できます。また、業務改善によって間接部門の社員のモチベーション向上やストレス軽減につながることも期待できます。
さらに、間接部門の最大の課題である「業務の俗人化」を排除し「業務の見える化」を達成することが可能になります。

英知コンサルティングの実績
当社代表の 清水一郎 は、3社の上場企業で「間接部門改革」を成功させた実績がございます。その主な成果は、次の通りです。
①IT化を促進することにより「業務の俗人化」を排除し、「業務の見える化」を実現
②月次決算を2日で完結させ、3日目に取締役会を開催
③間接部門人員を50%~75%削減
その成果は、「日経ビジネス 2016年12月5号」などのビジネス誌に掲載されております。
さらに当社では、727社の中小・中堅企業において「間接部門改革」を成功させた実績を持っております。
実績
727件
料金
ご面談・ご相談の上、最適なプランとお見積りをご提案いたします。
同時にご覧いただいているページ
ご相談・お問い合わせはこちら(無料)
コンサルティングのご依頼や、詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。ご相談は勿論、無料です。
お問い合せフォームでのお問合せは24時間受け付けております。
サイドメニュー
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー
Executive Consultant
清水 一郎
-------------------------------------
<専門分野>
経営再建、企業再生、経営戦略、営業戦略、マーケティング、間接部門改革、法務、財務、金融、会計、税務、監査、事業承継、IPO、資産運用、不動産、組織構築、人事制度、人事評価制度、目標管理制度
-------------------------------------