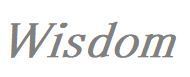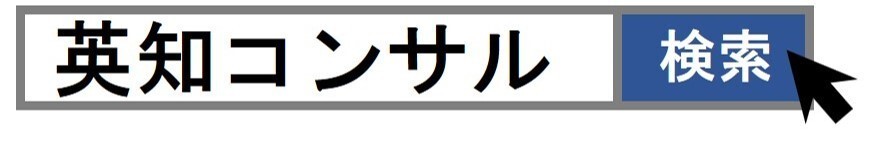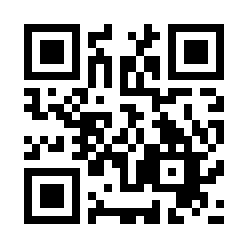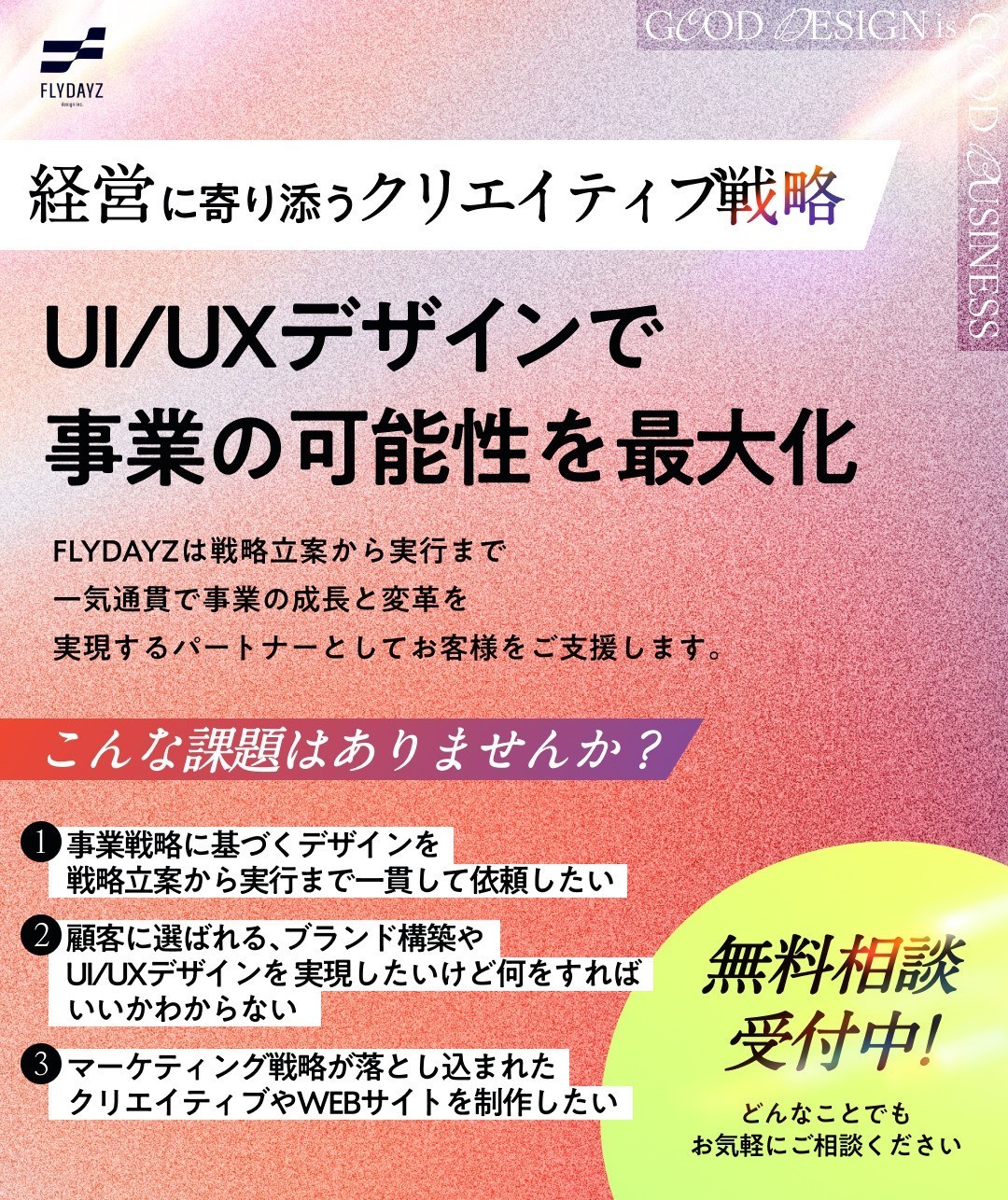中小企業・小規模事業者の経営コンサルティングは東京の英知コンサルティング株式会社(全国対応)
最終更新日 2024年08月17日
経理内製化コンサル
経理内製化コンサルなら東京の英知コンサルティング株式会社へ。経理を内製化した場合も外注化した場合も、それぞれにメリットとデメリットがあります。
概ね売上総利益が5,000万円超、または従業員数が30名を越えたら、経理の内製化をお薦めしております。
経理内製化支援
<目 次>

1. 弊社の管理部門の体制
1-1. 月次決算のスケジュール
1-2. 四半期決算のスケジュール
1-3. 期末決算のスケジュール
1-4. 経営管理上、決算はスピード重視
決算をいくら正確に行おうと努力しても、決算日から1年間経過をみなければ100%正確な決算はできません。
会計で最も重要なのことは「スピード」と「重要性の判定」であると考えます。経常利益の3%程度の「誤差」は容認し「スピード」を優先しています。
毎月末、毎四半期末、および決算日に、翌月、翌四半期、および翌事業年度のキックオフ・ミーティングを開催し、決算日の翌日にスタート・ダッシュができる体制が出来上がっています。
法人税等の申告期限および納税は、決算日から2ヵ月以内です。中小企業の多くは税理士に税務申告書の作成まで委任されていることでしょう。
税理士は「税」の専門家ですが「経営」のプロではないため、申告期限ギリギリにならないと決算が確定しません。
決算日から2ヵ月遅れで決算が確定するようでは、そもそも「勝負」になりません。「経営上」好ましい姿とはいえません。これが税理士の実態です。
2. 経理の外注化(アウトソーシング)とは
経理の外注化(アウトソーシング)とは、自社の経理業務を外部の専門業者などに委託することです。
経理のアウトソーシング(記帳代行業)は、古くからからありましたが、働き手不足の背景から近年注目を集めています。
主な業務内容は次のとおりです。
・記帳、仕訳入力
・請求書、納品書などの受領や発行
・売掛金や買掛金の管理
・振込データの作成
・給与計算・年末調整
・決算書作成・申告書等の作成 など
経理業務だけでなく、振込などの財務業務、社会保険の手続き、人事・採用業務など、バックオフィス業務全般を扱う業者もあります。
ただし、注意しなければならないのは代行業者の能力・資質は「玉石混合」なことです。

3. 経理のアウトソーシングの活用事例
4. 経理のアウトソーシングの費用相場
4-1. 記帳業務
4-2. 給与計算業務
4-3. 決算業務
決算書、勘定科目明細書、法人税等の申告書の作成を代行します。業務内容や事業規模によって金額は大きく変動しますが、中小企業の場合200,000円~300,000円程度が一般的です。

5. 経理アウトソーシングのメリット
5-1. コスト削減
5-2. 専門知識の活用
5-3. 時間の節約
5-4. 柔軟性の向上
5-5. 最新技術の利用
5-6. 人手不足を解消できる
5-7. 業務の属人化を防止できる
5-8. コア業務に集中できる
5-9. 専門性の高いサービスが受けられる
5-10. 最新の法改正に対応できる
経理業務は法改正や制度変更と密接に関連するため、正しく処理できているか不安を感じる担当者も多いでしょう。
経理アウトソーシング業者の中には、最新の法改正や会計基準に精通している業者もあります。サービスの利用により税法認識の誤りや人的ミスの防止につながり、会計処理の正確性が向上する 可能性があります。

6. 経理アウトソーシングのデメリット
6-1. 月次決算、四半期決算、期末決算が遅くなる
6-2. コントロールの喪失
6-3. 機密情報のリスク
6-4. コミュニケーションの課題
6-5. 隠れたコスト
6-6. 業務の質のばらつき
6-7. ノウハウを社内に蓄積できない
6-8. 経営状況を把握しにくい
6-9. 今以上のコストを要する場合がある
6-10. 急な変更への対応が困難になる
経理アウトソーシング業者は契約書の範囲内で業務を行うため、イレギュラーな事態に対応しにくいというデメリットがあります。
社内に経理業務の担当者がいない場合、トラブル発生時の対応にタイムラグが生じることを視野に入れましょう。
業務の遅延や品質低下を防止するためにも、急な変更への対応方法や速度などの事前確認が必須です。

7. 経理内製化(インソーシング)の目的
7-1. 経費削減効果
7-2. 業務効率化
8. 外注化or内製化を決めるポイント
8-1. 業務を行う期間
8-2. コストを比較する
8-3. 必要な知識や技術のレベルを確認
8-4. 内製化・外注化の範囲を決める
9. 決算早期化の必要性とメリット
9-1. 決算早期化による会社のメリット
9-2. 決算早期化による経理のメリット
決算早期化は経理部にもメリットをもたらす可能性があります。決算早期化のためには業務効率化が欠かせないため、経理業務全体の効率化が図れるはずです。その結果、効率化により生じた余裕をほかの経理業務に充てることが可能です。
経理担当者の繁忙期が短期化するのも大きなポイントでしょう。決算期は残業が多くなる経理部も少なくありません。決算期の業務負担が重い会社は、決算早期化がそのまま経理部の働き方改革にもつながります。

10. 決算早期化を阻む要因
10-1. 個別決算早期化の課題
決算の流れは大まかに言うと、「日々の記帳」「試算表による日々の記帳の確認」「決算に伴う調整」です。書類出力作業や調整など決算特有の業務もありますが、基本となる記帳や、試算表による確認作業は日々の業務の延長線上にある業務と言えます。特別な作業ではないはずですが、スムーズに進まないことも多いようです。個別決算に時間がかかる会社は、次のような課題があると考えられます。
①必要な書類が経理に届くまでに時間を要する
経費書類、請求書や納品書などが集まらず、勘定科目の残高確定に時間がかかります。
②書類の入力作業が非効率的
書類が集まっても手入力が多く、入力作業に時間がかかります。
③既存会計システムの使い勝手が悪い
例えば「各部門データの連携が悪い」「出したいレイアウトでデータが出力できない」といった会計システムは、手間がかかります。また、法改正のたびに手作業で修正が必要であると、業務量が大幅に増えてしまいます。そもそもシステムの処理速度が遅く、効率化したくともできないケースもあるでしょう。
10-2. 連結決算早期化の課題
連結決算は子会社および関連会社を含めたグループ全体の決算方法のことです。
個別決算の作成では問題ないと仮定すると、主に親会社が子会社及び関連会社の財務諸表を取りまとめるプロセスに阻害要因が存在すると考えられます。
①子会社等の会計方針が異なり、連携がうまくいかない
最初に子会社等から、連結財務諸表の作成に必要な情報を収集します。
必要情報は個別財務諸表のみならず、関係会社との取引明細や未実現損益計算書類など多岐にわたります。子会社等と提出時期をすり合わせて、必要な書類をすべて集めなければなりません。
連携がマニュアル化されていないと、毎回同じ苦労が生じかねません。
②子会社等と書式や勘定科目体系が異なり、手作業による調整が必要
集めた項目の名称や書式などが統一されてないと、確認や調整の手間が増えます。
例えば子会社ごとに取引先コードや勘定科目の設定が異なる場合は、連結の際に手作業で調整が必要です。
取引コードや勘定科目を親子間ですり合わせることができればいいのですが、会計システムが異なるとシステム上のすり合わせが難しいこともあります。
なお、親子間の取引や子会社間の取引など、連結決算で必要な調整を行うためのデータに齟齬(そご)がある場合は、確認して正しい金額を算出しなければならず、やりとりがスムーズでないとそれだけで時間が取られてしまいます。
上記のほか、決算業務の全体的な課題として、絶対的な経理人員の不足も考えられます。
一般的に経理部においては繁忙期と平時で必要な人員数が異なり、平時を基準とした人員で決算業務をこなしている場合があるからです。人件費の無駄を省く観点からは、そのような企業も少なくないと推測されます。
しかし、業務体質の健全化のためには解決を図っていきたいところです。このような課題を解決するためには、業務効率化とシステムの見直しが有効です。2つを順に紹介します。

11. 英知コンサルティングの経理内製化支援
11-1. 経理業務の外注による課題
この企業の社長と担当者にお話を伺ったところ、以下のような課題が浮き彫りになりました。
課題1. 慣例化したアウトソーシング
社内人材が成長し、内製化が可能な状態になっていましたが、以前からの慣習という理由でアウトソーシングを継続していました。
このように、実際には経理の内製化が可能なのにアウトソーシングしている企業は少なくありません。
敢えてアウトソーシングを選択する企業もありますが、慣例として外注をし続けているのであれば、内製化も検討する必要があるのではないでしょうか。
課題2. 税理士事務所の仕訳データ連動が一切ない
税理士事務所で全ての仕訳入力を手入力で行っていたため、仕訳については一切、データの連携を行っていませんでした。 そのため、転記時にミスが生じたり、税理士事務所の担当者が変わると、摘要等の書式ルールも変わってしまい過去の仕訳が検索しづらくなっていました。
課題3. 月次決算が遅い
アウトソーシングは月次決算の完成も遅く、約1.5ヶ月のズレが発生していたため、せっかくの会計データを経営に活かすことができない状況でした。
月次決算が遅れたことで、、海外送金等の為替レートの変動に気づくことができず、為替差損が発生したり、システム利用料等の経費使用額の把握が遅れ、解約すべき契約が更新されてしまうといった不利益・機会損失が生じていました。
課題4. 不正確なデータによる二重転記業務の発生
基幹システムと会計システムが連動していないことが原因で、販売管理システム上の債権債務が不正確になってしまっていました。 そのためエクセルで手動管理をしていました。
債権債務がズレてしまうのは自社が把握している金額に対して、仕入先から届いた請求書に不一致が発生した場合、基幹システム上で金額のズレを修正せずに、仕入先の金額をそのまま支払っていたことが原因です。
そのため基幹システムとエクセルの残高が不一致になっていました。
二重転記にかかる時間は月約50時間、基幹システムの残額を取引ごとに1件ずつ確認し、前月データを見ながら全て手入力するなど、とても労力のかかる業務でした。
転記作業は生産性がないだけでなく、ミスの原因にもなるため、もしも経理業務に重複・転記作業があるなら、速やかに改善すべきと言えます。
11-2. 経理の外注化はメリットとデメリットを比較して
今回のお客様は内製化に踏み切りましたが、仕訳記帳をアウトソーシングすることにはメリットもあります。事実、内製化できるのにアウトソーシングしている会社は少なくありません。
例えば、会計に関する情報を社内に非公開にすることで、経理が不正を行えない体制を維持する場合です。
また、経理は事業部門からの数字をまとめる所までを行い、記帳のみアウトソーシングするケースもあります。外注化することで、記帳ミスを防ぐことが可能だからです。
その他、仕訳記帳など生産性の低い業務は、単価の高い社員には任せないと判断する会社も少なくありません。
その場合、経営資料等の作成など高度な業務に特化させることで、コストパフォーマンスの最大化を図ることが目的です。
今回のお客様は、弊社に問い合わせをいただく前、経理に関する相談を基幹システムのベンダーや税理士事務所に相談していたそうです。
しかし、ベンダーは会計数値のことがわからない、税理士事務所は基幹システムを把握していないということで、誰に相談しても回答が得られない状態でした。
そこで、システムにも会計数値にも精通し、解決策が提案できる英知コンサルティング株式会社にご相談をいただきました。
今回の事例以外でも、
・税理士事務所は記帳はできるが経理社員に実務的な指導はしてくれない。
・システム会社はシステムの操作方法は教えてくれても、記帳ルールにある「勘定科目」「消費税計算方法」「各数値の集計基準」などは指導してくれない。
という話を耳にすることがあります。同じような悩みを持つ方は一度、英知コンサルティング株式会社にご相談ください。

英知コンサルティングの実績
実績
522件
料金
ご面談・ご相談の上、最適なプランとお見積りをご提案いたします。
同時にご覧いただいているページ
ご相談・お問い合わせはこちら(無料)
コンサルティングのご依頼や、詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。ご相談は勿論、無料です。
お問い合せフォームでのお問合せは24時間受け付けております。
サイドメニュー
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー
Executive Consultant
清水 一郎
-------------------------------------
<専門分野>
経営再建、企業再生、経営戦略、営業戦略、マーケティング、間接部門改革、法務、財務、金融、会計、税務、監査、事業承継、IPO、資産運用、不動産、組織構築、人事制度、人事評価制度、目標管理制度
-------------------------------------