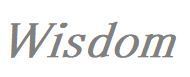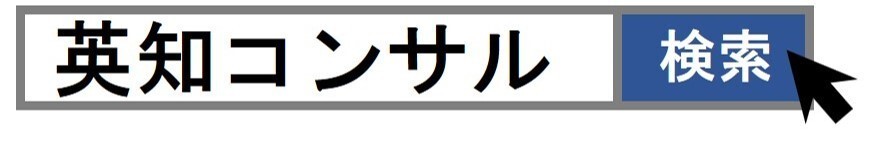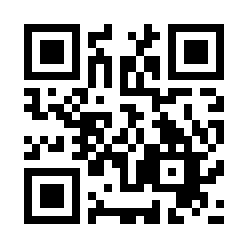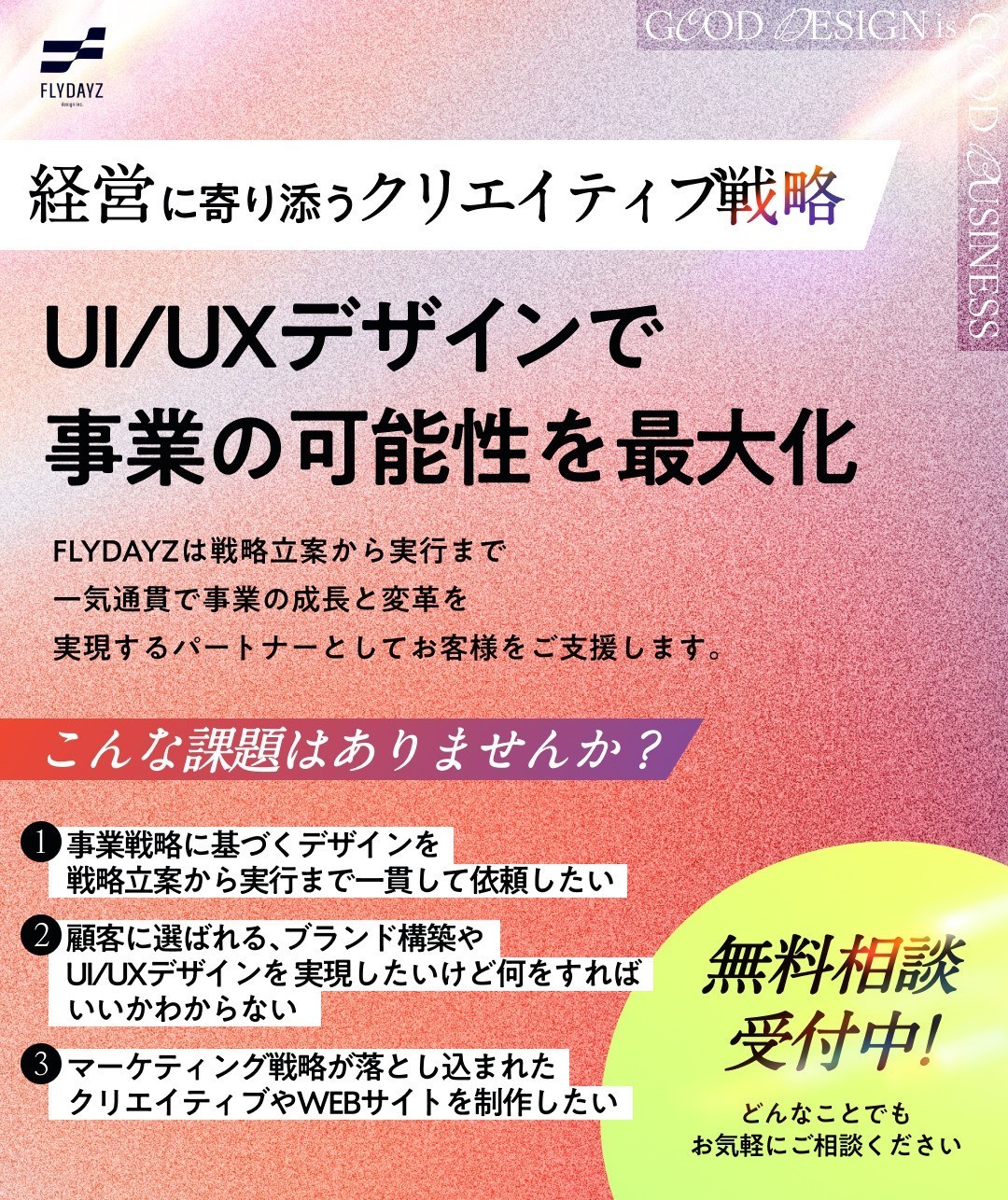中小企業・小規模事業者の経営コンサルティングは東京の英知コンサルティング株式会社(全国対応)
最終更新日 2024年06月22日
任意監査
任意監査なら東京の英知コンサルティング株式会社へ。
任意監査を受ける大きなメリットは、財務数値の透明性を証明でき、取引先や金融機関、利害関係者に対して信用力の高さをアピールできるとです。

任意監査とは
任意監査とは法定監査とは異なり法律等の規定で義務付けられていない監査のことをいいます。
監査を受けることは法律等の規定で義務付けられていませんが、企業が上場を準備するための監査、株価算定や株式交換比率を算定するための監査、企業売買や営業譲渡をするための監査、投資判断のための投資対象企業の監査、取引先や親会社からの要請による監査等、様々な目的を達成するために行われます。
会社法上の大会社(資本額が5億円以上または期末の負債額が200億円以上の株式会社)や上場会社は毎年監査を受けなくてはなりませんが、非上場の会社等は法律上、監査を受ける義務はありません。
監査を受けるには費用と時間がかかりますが、近年は欧米だけではなく、日本でも任意監査を受ける法人や組合等が増加しております。

任意監査が求められるケース
上場企業などは金融商品取引法に基づく監査が必要です。また、資本金5億円以上または負債200億円以上の会社は、会社法監査を受けなければいけません。任意監査は次のような場合に行われます。
1.被監査会社が経理の適正化等の理由から監査を自発的に受ける場合
2.第三者が被監査会社の財務諸表や収支計算書の適性を評価するために監査を義務付ける場合
3.第三者が被監査会社への信用供与を行う際の条件として監査を義務付ける場合
に大別できます。
1.には被監査会社の経営者が財務諸表の社会的信頼性を獲得するために監査を依頼する場合など
2.にはM&Aなどの際に買手会社が売手会社に対して行う買収監査(デューデリジェンス)など
3.には金融機関が有投資の条件として要求する監査などがそれぞれ該当します。

任意監査の種類
任意監査は様々な要請に基づき行われますので、拠り所となる法律等もニーズに応じて変わります。
金融商品取引法監査に準ずる監査
株式公開準備企業が監査を受ける場合は、「金融商品取引法監査に準ずる監査」として行われます。
将来、上場した際には金融商品取引法監査を受けることになりますが、その前段階として、金融商品取引法監査と同レベルの監査を受けます。
会社法監査に準ずる監査
取引先や金融機関、株主などからの要請で、監査を受ける場合は、「会社法監査に準ずる監査」として、会計基準や財務諸表の表示が会社法に準拠しているかという観点で行われる監査です。
「中小企業の会計に関する指針」準拠の監査
会社法監査に準ずる監査と同じく、取引先や金融機関、株主などからの要請で監査を受ける場合で、会計基準や財務諸表の表示が「中小企業の会計に関する指針」に準拠しているかという観点で行われる監査です。

任意監査のメリット・デメリット
任意監査のメリット
中小・中堅企業が、任意監査を受けるメリットは、財務数値の透明性を証明できること、取引先や金融機関、利害関係者に信用力の高さをアピールできることが挙げられます。
1.金融機関に対し
融資を受ける際の判断資料となり、融資金額、期間、利率、弁済条件等の決定に際し、適切に評価されることが期待されます。
2.取引先に対し
取引条件を決定する際の判断資料となり、支払サイト、取引保証金の設定の要否等の決定に際し、適切に評価されることが期待されます。
3.投資家に対し
投資先の利益や純資産の状況を把握する際の判断資料となり、投資するか、または投資を継続するか等の決定に際し、適切に評価されることが期待されます。
さらに、監査法人または公認会計士による監査においては、サービスの一環として組織の管理の状況(内部統制やガバナンス)もチェックされます。
これにより財務諸表に対する社会的信頼性を高めるだけではなく、業務の有効性や効率性、コンプライアンスの状況等についてもアピールでき、監査で行う適切なアドバイスをもとに組織を整備し業務の改善を行うことが出来ます。
4.自社に対し
任意監査は不正を見つけることが目的ではありません。しかし、監査を行なっていくうちに、不正が発覚する可能性があります。
不正は社内だけではなく、取引先や顧客にも悪影響を及ぼしかねません。そのため、任意監査によって早期に不正を防ぐことで取引先をはじめとした、ステークホルダーの保護も可能です。

任意監査のデメリット
任意監査のデメリットとして、監査に必要な書類の準備や監査法人との関係悪化が招くコスト増加が挙げられます。
特に、監査法人と関係が悪化してしまうと、コスト増加に加えて、自社の状況に応じた監査も期待できなくなってしまいます。
1.監査に必要な書類の準備
任意監査を行なうにあたり、監査に必要な書類を事前に用意しておく必要があります。
特に初めて監査を受けるとなると、流れが不明瞭なため、依頼先である監査法人とのコミュニケーションコストがかかってしまいます。
また、必要な書類が用意できなかったり、監査法人からの質問に答えられなかったりすると、監査業務は予定よりも長引いてしまい、コストがかさんでしまう可能性があります。
2.監査法人との関係性が悪化するとコストがかさむ
任意監査を依頼した先である監査法人との関係性が悪化してしまうと、コストの肥大化が危惧されます。
例えば、監査法人と経営者もしくは担当者の関係が悪化してしまうと、監査法人は会社の細かな点に目を向けなくなり、通常の監査を淡々と進めてしまいかねません。
一方、会社側は監査法人の指摘に対しての協力姿勢の低下が懸念されます。
このような状況に陥ってしまうと、監査される側、監査する側ともに疲弊して、監査業務の長期化によるコスト肥大につながってしまいます。
任意監査が有効な法人等
非上場株式会社
持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)
公益法人
一般社団法人・一般財団法人
特定非営利活動法人(NPO法人)
社会福祉法人
医療法人
宗教法人
農業協同組合、水産業協同組合
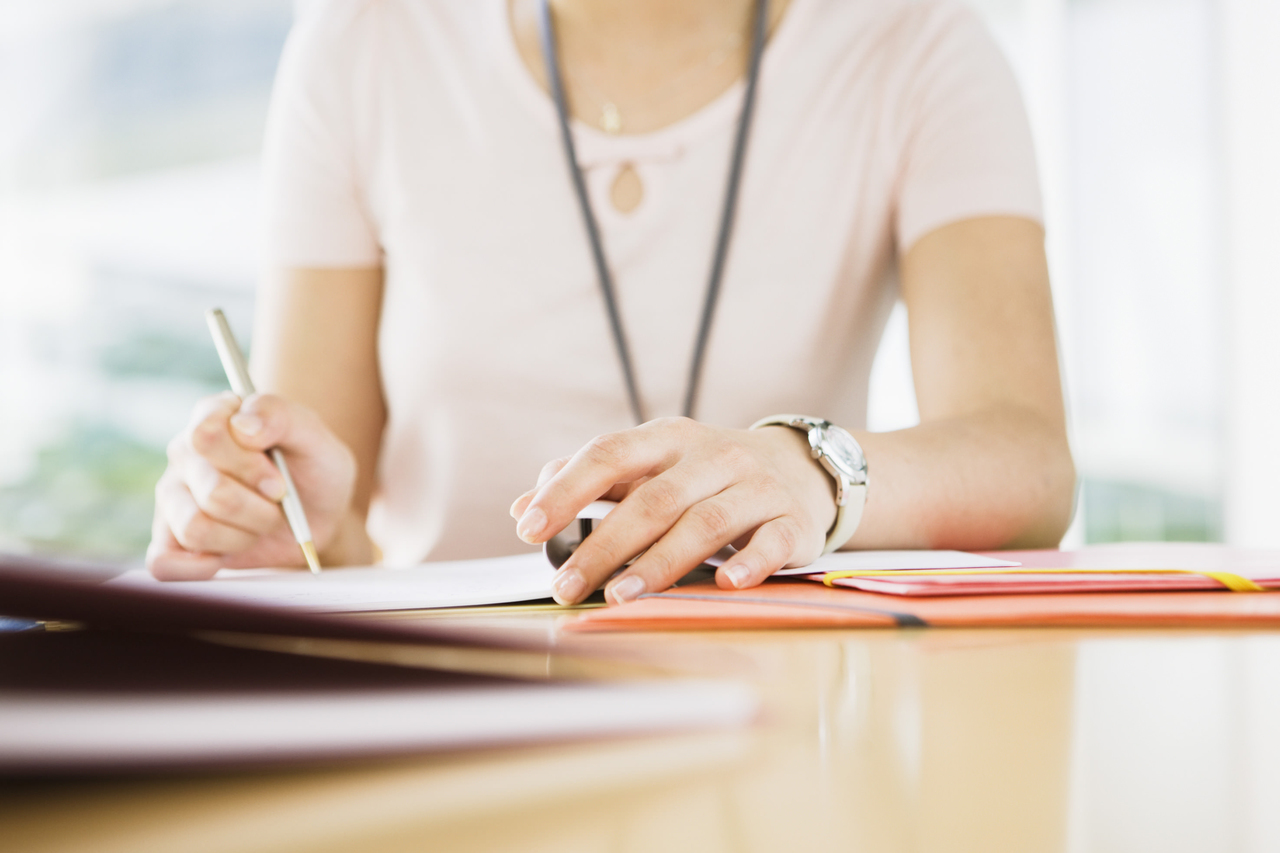
英知コンサルティングの実績
実績
208件
料金
ご面談・ご相談の上、最適なプランとお見積りをご提案いたします。
一緒にご覧いただいているページ
ご相談・お問い合わせはこちら(無料)
コンサルティングのご依頼や、詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。ご相談は勿論、無料です。
お問い合せフォームでのお問合せは24時間受け付けております。
サイドメニュー
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー
Executive Consultant
清水 一郎
-------------------------------------
<専門分野>
経営再建、企業再生、経営戦略、営業戦略、マーケティング、間接部門改革、法務、財務、金融、会計、税務、監査、事業承継、IPO、資産運用、不動産、組織構築、人事制度、人事評価制度、目標管理制度
-------------------------------------