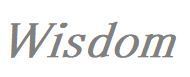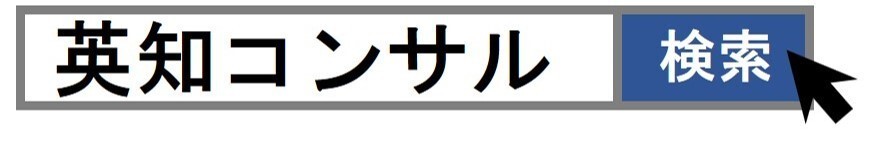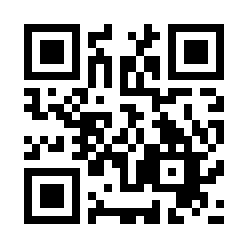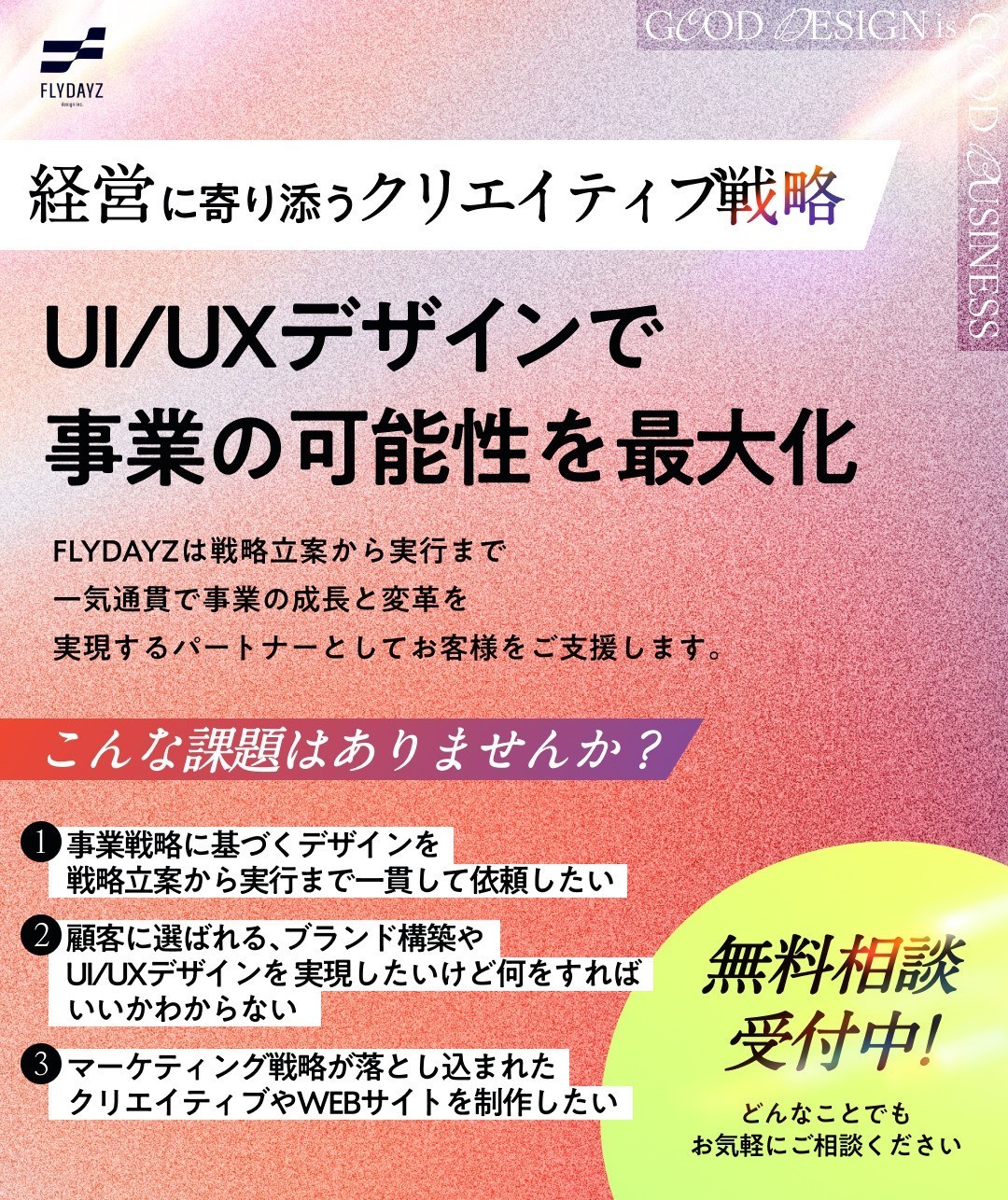中小企業・小規模事業者の経営コンサルティングは東京の英知コンサルティング株式会社(全国対応)
最終更新日 2024年06月23日
部下を褒めて育てる
「部下を褒めて育てる」ことには多くのメリットがあります。「部下を褒めて育てるなんて、とんでもない」という経営者・幹部も決して少なくありませんが、当社では「部下を褒めて育てる」ことを推奨しております。

部下を育て、組織を発展させるために、褒めることの重要性は計り知れません。本稿では、なぜ褒めることが成果をもたらし、どのようにして部下を育てる手助けになるのかを説明します。褒めることがビジネスに及ぼす影響、効果的な褒め方、そして実際の成功事例に触れながら、部下を褒めて育てる方法について考察します。
褒めることの重要性
褒めることは、組織内でのポジティブな文化を築き、成果を促進する重要な要素です。以下に、褒めることがなぜ重要なのかを示します。
1. モチベーションの向上
褒めることは、部下のモチベーションを向上させます。従業員は自分の仕事が認められ、評価されることで、仕事への情熱と努力を高めます。
2. 自己成長と自信
褒められることで、部下は自己成長と自己評価の向上を体験します。自信をつけ、新しいスキルや知識の獲得に積極的に取り組むようになります。
3. コミュニケーションの円滑化
褒めることは、上司と部下のコミュニケーションを円滑にし、信頼関係を構築します。部下は意見やアイデアを積極的に共有し、組織全体の協力を促進します。
4. 成果の向上
モチベーション向上、自己成長、コミュニケーションの円滑化が結実し、最終的には成果の向上につながります。褒められた部下は、より高いパフォーマンスを発揮します。

効果的な褒め方
褒めることの重要性を理解したら、次はどのようにして褒めるかを考えましょう。効果的な褒め方には以下の要素が含まれます。
1. 具体的で誠実なフィードバック
褒める際には、具体的な事例や行動に基づいて誠実なフィードバックを提供しましょう。例えば、「昨日のプレゼンテーションは非常にクリアで魅力的でした」と具体的な出来事を挙げることで、褒め言葉がより効果的になります。
2. 適切なタイミング
褒めることは適切なタイミングが重要です。部下の成功をすぐに褒めることで、その成果が新鮮なうちにポジティブなインパクトを持つことができます。
3. 均等な機会
褒める機会は公平に分けましょう。一部の部下だけに注目せず、全ての従業員に対して褒める機会を提供しましょう。これはチーム全体のモチベーションを高めるのに役立ちます。
4. 感謝の表現
部下に感謝の意を示すことも褒める方法の一つです。感謝の言葉や行動が部下の努力を認識し、結びつきを強化します。
ここまでの「まとめ」
部下を褒めることは、中小企業経営者にとって重要なリーダーシップスキルです。褒めることにより、部下のモチベーションが向上し、成果が増加します。効果的な褒め方を実践し、成功事例から学び、組織内のポジティブな文化を築くことで、中小企業の成長と成功に寄与します。部下を褒めて育て、共に目標を達成しましょう。

部下を褒めて育てる
部下を褒めて育てる
企業は「存続」することが最も重要であり、それが社会的責任を果たすことになります。そして、継続して利益を生み出していくことで「存続」が可能になることは言うまでもありません。さらに、利益を常に生み出すためには、強い「組織」の存在が不可欠です。
そこで、改めて強い「組織」とは何かと考えると、高い経営戦略の遂行能力を持ち、かつ高い状況変化に対する適応能力を持つ組織であると定義づけられます。 つまり、目的に向かって着実に業務を成し遂げる力と、自らを変革し結果を出す力がある組織が強い「組織」であると言えます。
「組織」は人の集まりであり、高い遂行能力も高い適応能力もその担い手は「組織」に属する「人」に他なりません。したがって、強い「組織」をつくるには「組織」に属する一人ひとりの行動様式が重要であり、その行動様式を束ね、経営者とメンバーをつなぐ「リーダー」の能力が大きく問われます。
「リーダー」が高い遂行能力を発揮するために「組織力を最大化する方法」をテーマに取り上げました。 「成功に導く組織力をいかに生みだすか」これがリーダーに与えられた究極の課題であり、同時にこれは私どもコンサルタントの日頃の活動にも当てはまることです。
リーダーの皆さんと共に「組織」を動かし、大きな経営成果を上げていくためには、メンバー全員がよいパフォーマンスを発揮し、かつ成長できる環境や仕組みを作り上げることが必要です。いかにメンバーを動かしていくのか、改めて振り返る機会にしていただければ幸甚です。

部下を褒めるとは
部下を褒めることは、その人のやる気や自信を高め、良い成果を生み出すことができます。部下を褒めて育てるための具体的な方法は次の通りです。
1.良い仕事をしたら、直ちに褒める。その時に、具体的な理由を伝えると、その人がどのように貢献したのかが明確になります。
2.部下には、彼らのアイデアや提案に対して積極的に耳を傾け、賞賛するように努めましょう。彼らに自信を持たせることができます。
3.成長を見せた部下に対しては、定期的に評価し、彼らが改善したことを認めましょう。また、次にどのような成長を期待しているかを伝えることで、彼らに方向性を与えることができます。
4.部下を表彰する場を設け、彼らが良い仕事をしたときには、同僚たちに誇らしげに紹介しましょう。そうすることで、彼らに誇りを感じてもらうことができます。
部下に対して、よくやったというだけでなく、改善の余地がある場合には、どのように改善するかについて具体的なアドバイスを提供することが重要です。そうすることで、彼らは成長し、より良い結果を生み出すことができます。
総じて、部下を褒めることは、モチベーションを高め、より良い成果を生み出すことができます。しかし、それが単なる表面的な賞賛にとどまらないようにすることが重要です。具体的なフィードバックと指導を提供することで、部下を成長させ、組織全体の成功に貢献することができます。

部下を褒めていますか?
組織の成果を上げようとする際に、メンバーに「なぜもっと売り上げが伸びないのか」、「なぜもっとコストが下がらないのか」と感情のままに声を荒げて言うことは容易です。
しかし、日常的にそうした言葉を掛けられていると、メンバーは「そんなことを言われても自分なりに努力をしている」、「そんなことを言われても難しい」と必ず反発の気持ちを抱くようになるものです。
そして、声に出さずに殻に閉じこもるだけで、なかなか良いパフォーマンスを発揮することはないでしょう。努力しても成果が出せない理由は何か、売り上げが伸びない、コストが下がらない背景にある問題に対しては、今、少しでもできたことを褒め、 次にどうしていこうかと考えさせることで、ゴールに到達する道筋が見えてきます。
ある新人営業マンの例で考えてみましょう。目標(ゴール)は売上目標を達成することです。したがって、その営業マンの成長を見ようとすると、売上目標に到達したかどうかにどうしても重点が置かれます。
そして、上司や先輩は売上目標を達成した際にほめる(結果承認)、または、目標に到達しなかった際には、「なぜ」と問い掛ける訳ですが、よい結果をほめたり、悪い結果を振り返らせたりする行為自体は、何ら難しいことではありません。ただ、それだけで新人営業マンの成長を促すことができるでしょうか。
新人営業マンが目標達成に至るまでにはさまざまなプロセスを経なければなりません。例えば、お客様に会えた、商談することができるようになった、商談をまとめて企画書を作れるようになった、お客様の前でプレゼンテーションができた、といったプロセスです。
そのプロセスの一つひとつで、できたことを褒め(事実承認)、次のステップを考えさせることが、自信をつけ、やる気を起こさせることにつながります。そして、広い意味で「存在を認める「感謝する」「仕事を任せる」と、自分自身の存在をリーダーが認めてくれていると感じ、その人の為に頑張ろうという気にもさせることができます。新人営業マンにしても、「常にあなたを見ている」という姿勢を示せば、より積極的に仕事に取り組むようになっていきます。
一方、メンバーをほめないリーダーに多く見られるのは、自分の期待まで到達していないと考えてしまう、立場上ついつい厳しく言ってしまう、なかなか一人ひとりのメンバーと話しをする時間がとれない、といった問題です。組織から結果を早期に求められる、メンバーの成長を待てない、自分でやった方がうまく行く、そもそも褒めることが苦手だ、などと考えてしまうことが背景にあるように思われます。
その結果褒めらられることの少ないメンバーは心を開かず、組織のパフォーマンスが一向に上がらないばかりでなく、かえって非効率な試行錯誤を要求することとなり、メンバーの成長を停滞させ、目標到達までになかなか至らない、という負のスパイラルに陥ってしまうのです。
仮に社員が経営者と同じ仕事ができたとしたら、経営者と同額の賃金を支払わなければなりません。「人材育成」は、時間が掛かるものと割り切ることも必要だと考えます。故に、経営者の「器の大きさ」が問われます。

「部下を褒めて育てる」メリット・デメリット
部下を褒めて育てるメリット
1.モチベーションの向上
部下を褒めることにより、彼らのモチベーションが向上します。褒め言葉によって自信がつき、より良い成果を上げることができます。
2.成果の向上
モチベーションが向上することで、部下がより良い成果を上げることができます。また、褒められることで、その行動を繰り返しやすくなるため、仕事の品質が向上することも期待できます。
3.コミュニケーションの向上
部下が褒められることで、上司と部下の間のコミュニケーションがよくなります。上司からのフィードバックによって、部下がより良い仕事をするための指示を受け取ることができます。
4.チームワークの向上
部下を褒めることで、その部下が所属するチーム全体のモチベーションが向上します。褒められることで、チーム全体の仕事の質が向上し、結果的に企業全体の業績も向上することが期待できます。
部下を褒めて育てるデメリット
基本的にデメリットはありませんが、褒めることにも注意が必要です。
例えば、褒めすぎると褒め言葉が軽くなってしまうため、適度な褒め方を心がける必要があります。また、褒め言葉が偽りやすい場合は、部下が信用を失う可能性があるため、褒める場合は誠実に行う必要があります。

「褒める」と「おだてる」は違う
褒めることは大切だと分かってはいるけれども、面と向かってほめるのは難しいと感じている皆さんは少なくないでしょう。
褒めることは何か相手に媚びるかのようで好まない、普段ほめていないので今さら何か魂胆があるのではないかと、誤解されるぐらいなら何も言わない方が良い、褒め言葉は特別なものであり容易には使えない、 そもそも何を言葉にすればよいのか分からない、これらが褒めることを苦手とする理由によく挙がります。
これらに共通して言えることは、いずれも「褒める」行為そのものを、自分中心に考えていることです。それらは真の「褒める」行為ではなく、むしろ自分のために相手に影響を与えようとする「おだてる」という表現が適切です。 褒めるのが苦手な人には、この「褒める」と「おだてる」の区別がついていないことが多く見られます。
私はコンサルティングの現場で「ありがとう」という言葉を積極的に使うことを心がけています。 また「嬉しい」という感情を表すようにも心がけています。例えば、ちょっとした改善提案をしてくれたパート社員の方に「ありがとう」と言葉をかけるなどです。
自分が抱える悩みをこのように解決しよう、と相談に来た若手社員に「前向きに考えてくれて嬉しい」、と言葉を返すといった具合です。 そして、したたかな計算でおだてて何かに取り組んでもらうよりも、その場で起きたことを素直にほめ、喜びを表現することが、確実に次のステップに繋がっていくことを日々実感しています。
「褒める」ことの重要性についてお話しました。それはメンバー一人ひとりの努力を正しく評価し、個人のモチベーションをアップさせるためにも大切なことです。
しかし、メンバーの行動や考え方に問題が見られる場合には、あえて苦言を呈することもリーダーの重要な役割です。いつも「褒める」ばかりではリーダーの任務は務まりません。 つまり、「褒める」と「叱る」をアクセルとブレーキのように使い分ける必要があります。

「叱る」ことの難しさ
ある小学生のサッカー大会でこんなシーンを目の当たりにしました。 キックオフから一方的な試合展開。明らかに力の差が見られるチーム同士の対戦でした。そして、試合時間半ば過ぎだったでしょうか、一方的に押されていたチームが初めてのシュートチャンスを迎えました。しかし、惜しくもシュートは枠の外。
すると、それまで大声で怒鳴っていたコーチが、試合中にもかかわらず、シュートを外した選手をピッチの外に出してこう叫んだのです。「もう出る必要はない!帰れ!」と。
一人少なくなってしまったチームはさらにガタガタになり、コーチの声のボリュームはさらに上がり、ピッチ内の選手は委縮し、ミスを連発。結果、数えきれないほどの失点をし、敗れました。
そのコーチがその場面で何を指導したかったのかは定かではありません。ただ、委縮した子ども達にコーチの真意が届くことはないことだけは確信が持てました。さらに付け加えるのであれば、シュートを外して怒鳴られた子どもは、対戦相手のチームの子どもと比べて遜色のないレベルに見えたということです。果たして子供たちの能力を引き出す手段として大声を上げることが適切だったのでしょうか。
感情に任せて「怒る」とは容易なことです。しかし、相手のプライドは大きく傷つき、怒られた記憶しか残らないでしょう。一方、「叱る」とは「しかるべき道を諭す」の略です。今回のケースを通して何を相手の記憶に留めたいのかを明確にし、一貫した姿勢を持って、相手の立場に立って傷つけることのないように伝えることが「叱る」ということです。
「褒める」ばかりで上手く行くのであれば、それに越したことはありませんが、時には「叱る」ことも求められます。個人の感情を脇に置き、「叱る」ことで組織的な信頼感を醸成することがリーダーには求められます。
私自身も、先程の小学生サッカーチームの事例を他山の石として、今日は上手く「叱る」ことができただろうかと自らの発言を振り返ることを忘れないようにしています。

効果的な動機付けで強い「組織」へ
リーダーがメンバーを動かして組織のパフォーマンスを高めていくためには、相手の心を開いて自らの考えをしっかりと伝えねばならず、そのために効果的に「褒める」、または「叱る」ことが重要であることを述べてきました。
アブラハム・マズローは、欲求の構造をピラミッド型の5段階のモデルでとらえました。「衣食足りて礼節を知る」と言いますが、人は生理的欲求(生きていくための基本的・本能的欲求)や安全欲求(安全・安心な暮らしを送りたいという欲求)、 社会的欲求(集団に属したい、仲間が欲しいという欲求)といった低次の欲求が満たされると、職場や地域社会のコミュニティの中で他者から認められたいという、より高次の“尊厳欲求”を感じ始めます。
ところが、この「尊厳欲求」が満たされないと、人は劣等感や無力感などを感じることになります。つまり、誤った褒め方や叱り方は、メンバーに劣等感や無力感を植え付けるだけでなく、より高次の自己実現欲求も持たなくなり、 潜在的な資質や成長の芽が出ないように抑えつけてしまう危険性をはらんでいます。
これまで述べてきたように、正しく「褒める」、または「叱る」ことで「あなたに常に関心を持っているよ」と言葉と態度で示すことが人をやる気にさせ、強い「組組織」をつくるベースになります。
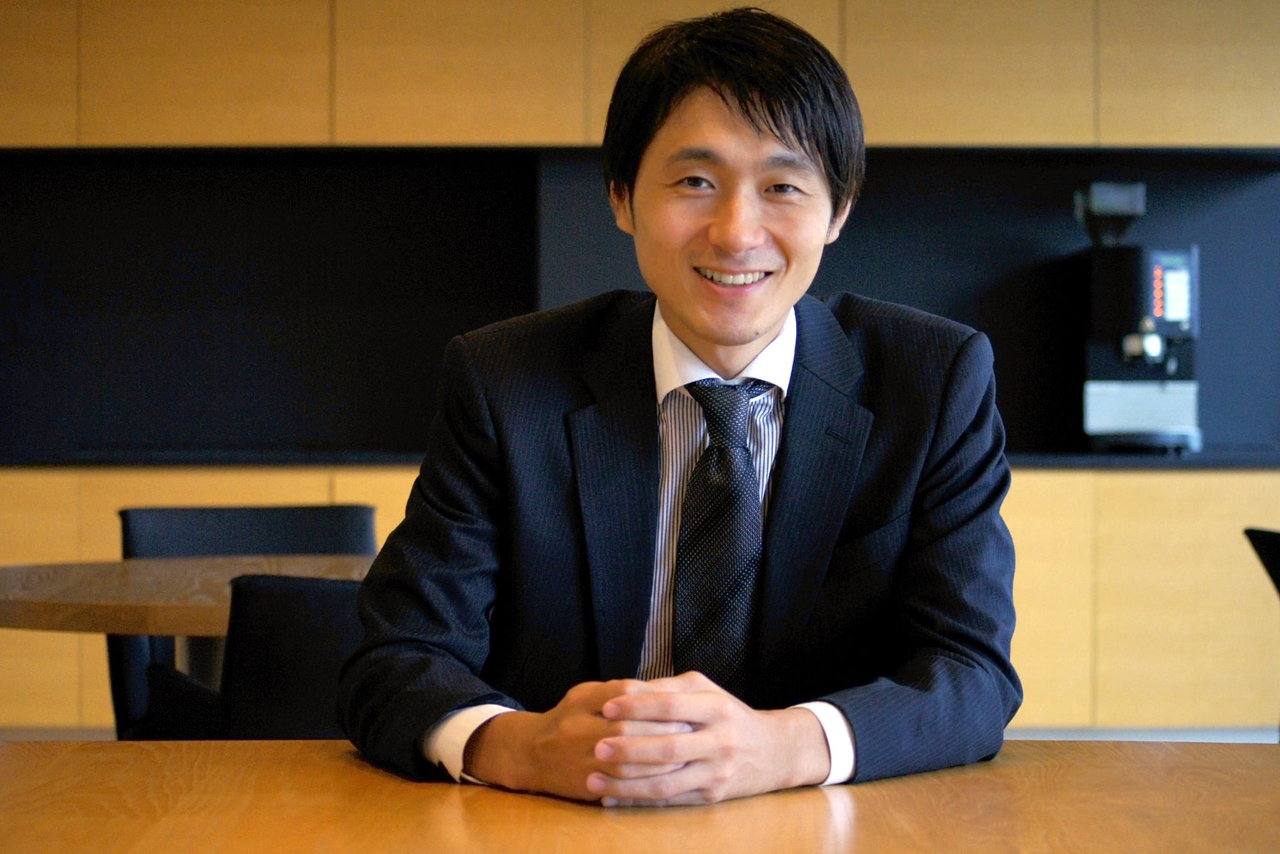
まとめ
「ほめる」「しかる」を上手く組み合わせた話法について紹介します。その話法とは、相手の心を開いてから本題を伝え、感謝と期待で締めくくる「サンドイッチ話法」です。以下にそのステップを記します。
①明るく感謝の言葉やほめ言葉を交えたプラスの話から始め、相手の心を開く
②本題(改善、要求、依頼)を話す
③最後に再び感謝や期待などを含めたプラスの言葉で締めくくる
例えば、生産現場の生産性向上のために設備改善を提案してきたメンバーに対して、まずは作業改善から行っていくべきだと伝える場合を考えてみましょう。
単に「お金がかかる提案ばかりではダメではないか!」と叱るのではなく、「今回はよく検討をしてきてくれたね、ありがとう。ただ、残念ながら、今回は予算が取られていないし、設備改善だと時間もかかってしまう。 まず作業改善から考えてみたらどうだろうか。 君ならきっとよい改善案を見つけてくれると期待しているよ。」というように、 否定的な表現(改善、要求、依頼)を肯定的な表現(感謝、期待)で挟み込むことで、相手を否定するような内容を奮起させる「ほめ言葉」にガラリと変えることができます。
このように強い組織をつくる上では、リーダーのメンバーに対する効果的な動機づけが不可欠です。 英知コンサルティングのコンサルタントは、自らがそうした技術を現場で実践し、リーダーの育成に努めています。組織の最大パフォーマンスを引き出す当社の取り組みに、ご関心をお持ちいただければ幸いです。
2022年01月02日
一緒にご覧いただいているページ
ご相談・お問い合わせはこちら(無料)
コンサルティングのご依頼や、詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。ご相談は勿論、無料です。
お問い合せフォームでのお問合せは24時間受け付けております。
サイドメニュー
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー
Executive Consultant
清水 一郎
-------------------------------------
<専門分野>
経営再建、企業再生、経営戦略、営業戦略、マーケティング、間接部門改革、法務、財務、金融、会計、税務、監査、事業承継、IPO、資産運用、不動産、組織構築、人事制度、人事評価制度、目標管理制度
-------------------------------------