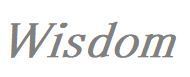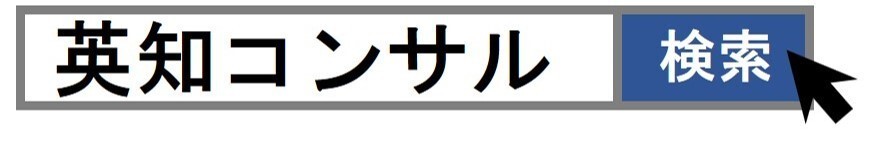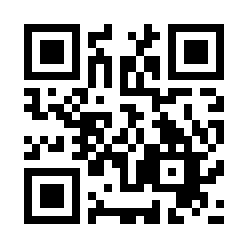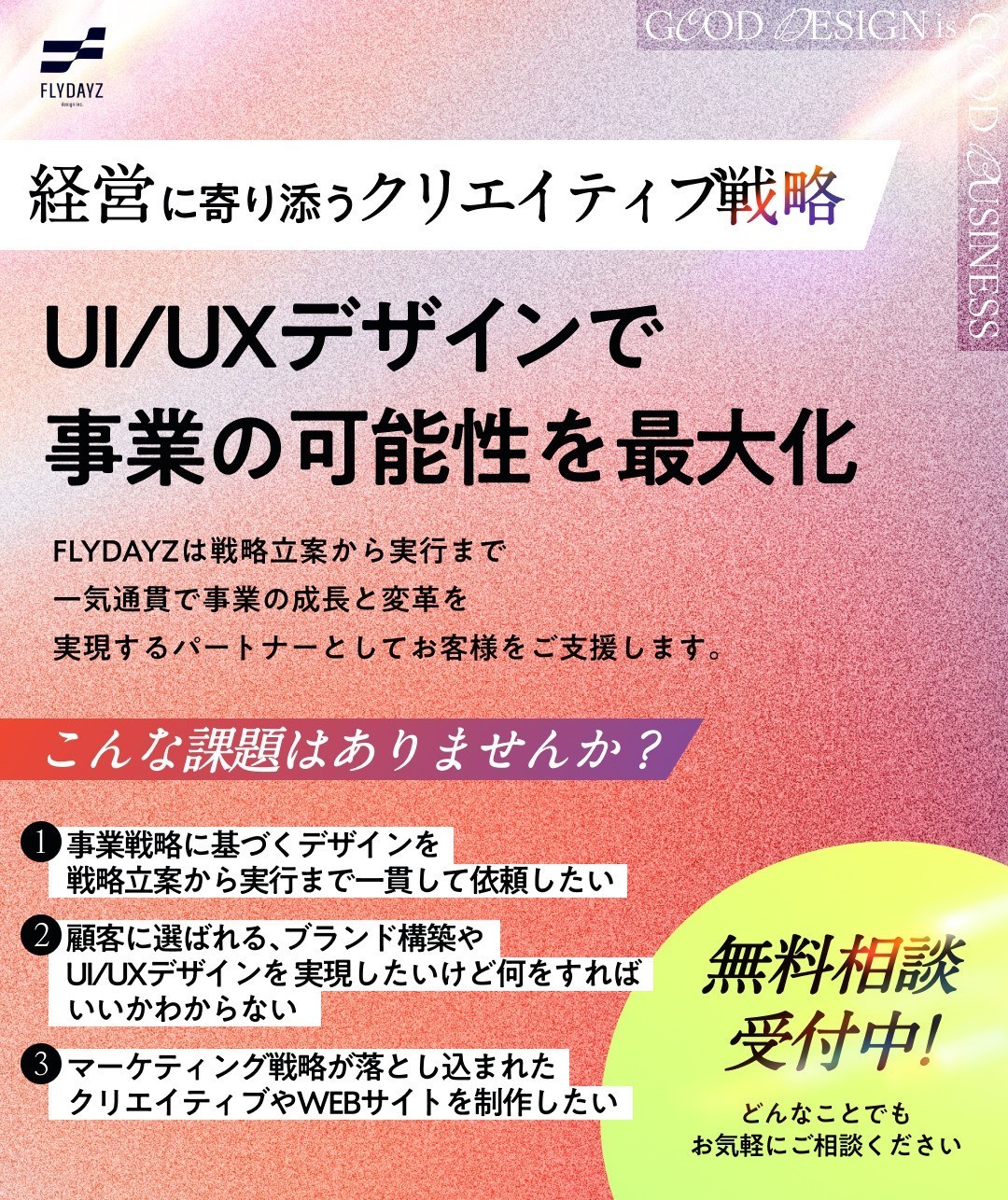中小企業・小規模事業者の経営コンサルティングは東京の英知コンサルティング株式会社(全国対応)
最終更新日 2024年06月23日
孫子の兵法から仕事を学ぶ
孫子の兵法から仕事を学ぶ。松下幸之助、ビル・ゲイツ、孫正義らの一流の経営者は、孫子の兵法から仕事を学び、事業を拡大しました。
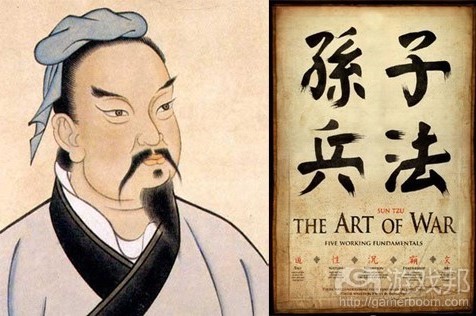
⑦ なぜ「事前の準備」ができない人ほど
奇跡を信じるのか
なぜ孫子は戦う前から勝が見えているのか
孫子は戦う前に「勝利の目算を高める」ことを何より重視していますが、リーダーが意識すべき5つの条件を列挙しています。この5つチェックポイントは戦場を選び、戦う態勢を整え、優れた将軍に実力を如何なく発揮させることを目指しています。
1.彼我の戦力を検討したうえで、戦うべきか否かの判断ができること
2.兵力に応じた戦い方ができること
3.君主国民が心を一つに合わせていること
4.万全の体制を固めて敵の不備につけこむこと
5.将軍が有能であって、君主が将軍の指揮権に干渉しないこと
2.の「兵力に応じた戦い方ができること」は、ビジネスに例えるならどのように始めるか、に当たります。従業員が数万人を超える大企業と、家族経営の延長線上にある小規模の会社では当然新規事業の始め方が違いますし、狙うべきチャンスの種類や規模も異なります。
美味しい話、すなわち何らかのチャンスが持ち込まれても必ずしも自社にとって絶好の機会であるとは限りません。素晴らしいチャンスでも自社の現在の環境と一致しない機会であれば手を出すべきではないかもしれないのです。
逆に言えば、君主は「自分たちが戦うべき戦場」を見つけ出すことに最善の努力を注ぎ込む必要があります。組織のトップは自社が進出して有利になる戦場を選び出すことに能力を使い、選別したチャンスに対して全軍を突撃させる必要があるのです。
一度戦闘を始めると、勝敗がつくまで簡単に撤退できません。そのため一歩を踏み出す分野は慎重に選ぶ必要があります。ソフトバンクを巨大企業に育てた創業者、孫正義氏は若い創業当時、事業分野を決定するまで1年間をかけ、そのあいだ情報収集と業界研究だけに時間を注いだと言われます。
とことん追求できる機会でなければ、安易に手を出したことで逆に成功へ遠回りになりかねないからです。したがって、追いかけ続けることができる機会か、慎重に見極める必要があります。戦闘が始まれば、この戦いに死力を尽くすことになるのですから、それだけの価値があるかを何より判断すべきなのです。

チャンスに対してアプローチを工夫する
「始め方」を工夫することで、有利に戦いを進めることも重要です。典型的な事例は、海外進出の際に現地代理店をまず募集し、数年間の契約期間を設定するなどです。
自社が直営するまでに至らない売上規模の期間は、代理店契約を継続し、いよいよ直接進出をするまで市場が拡大熟成した時には、契約継続を停止し、店舗を買収するなどで積極的に直営ビジネスに乗り出す例は、日本国内、海外で無数に目にすることができます。
これは市場の成長の各段階を追い掛ける形で進めていく、無理のない進出方法です。大きく考える場合、ソフトバンクが1995年当時世界第2位のコンピューター見本市だったCOMDEXを買収したように事業を丸ごと買ってしまうことも「始め方」です。
翌年のCOMDEXの基調講演はIBMのCEOルイス・ガースナーでしたが、孫正義氏が講演者の紹介をして世界的な知名度を得ることになりました(2001年に同社はCOMDEXを売却)。買収する場合も方向性はさまざまですが、最近話題になったサントリーの米ウイスキー大手「ビーム社」の買収などもあえて大手・超メジャーブランドを購入しています。
小さく考える場合、一つの新しい商品を店舗で取り扱い始める、新しい販売ルートを一つ開拓するなど、極小のきっかけから始めることもできるでしょう。自社の現状に対してリスクの低い始め方をできるなら、それだけ挑戦を行うことが簡単になるというメリットもあります。アプローチの方法自体の洗練、最適化が勝率を大きく高めてくれるのです。

リーダーが陥りやすい5つの危険
実行部隊の指導者としてのリーダー(将帥)を、孫子はどのような形で描いているでしょうか。将帥の陥りやすい失敗点について、孫子は興味深い指摘をしています。
【将帥の陥りやすい5つの危険】
1.いたずらに必死になること(これでは討ち死にする)
2.なんとか助かろうとあがくこと(捕虜になるのがおち)
3.短期で怒りっぽいこと(みすみす敵の術中にはまる)
4.清廉潔白すぎること(敵の挑発に乗ってしまう)
5.民衆への思いやりを持ちすぎること(神経がまいってしまう)
猪突猛進、勝ち目のない戦場でも必死になる将軍は戦死し、勇気をもって戦うことを知らない将軍は応戦すれば勝てる戦場でも、毎回捕虜になってしまう。ここで描かれる5つの失敗は、1つのことにこだわりすぎる、偏りすぎることから生まれる危険を指摘しています。
バランスが取れていないことである程度上手くいく人は、逆にそれが弱点にもなるということでしょう。勝ちパターンが完全に固定されている人も、足元を掬われやすい。では、孫子はどのような将軍を優れた人物として描いているのでしょうか。
戦場で柔軟性を失わず、君主に命令されたことを鵜呑みにするのではなく、自ら戦うべきとき、そうでない時を主体的に判断できること。結果として功績があっても名誉を求めず、敗北しても責任を回避しない。ひたすら人民の安全を願い、君主の利益をはかる。
ビジネスにおいても、仕事の本質から目をそらすことなく成果を追いかけ、悪戯に目立つことを避けて周囲の和をはかり、会社の利益に常に貢献する。このような人物こそ、企業社会における真に優れた将軍であり、国の宝(企業のエース)といえるのです。
5つの条件を元に健全な判断力を持ち、成果を出すために柔軟に攻めることができる人こそが、優れた将軍としてビジネスでも成果を出し続けているのです。

⑧ なぜ、部下の力を200%引き出すことができるのか
部下がやらざるを得ない環境を作る
意外なことかもしれませんが、兵法書の『孫子』は戦略戦術だけでなく、組織論にページを大きく割いています。
組織をどうまとめるべきか、兵士の実力を200%引き出すためには、リーダーは何をすべきかを書いているのです。第十一「九地編」で孫子は、どんな軍隊の兵士でも、戦闘が怖いのは当たり前であると指摘しています。
「彼らとて実は、財産は欲しいし、声明は惜しいのだ、出陣の命令が下ったときは、死を覚悟して、涙が頬をつたわり、襟をぬらしたはずである」
「そのかれらが、いざ戦いとなったとき、専諸や曹けい顔負けの働きをするのは、絶体絶命の窮地に立たされるからにほかならない」
現代ビジネスでは、戦場に出陣して死と隣り合わせ、という体験をすることはありませんが、別の意味で孫子の指摘は当たっています。ほとんどのビジネスマンは、自分の本来の能力を100%発揮して必死になることはなく、仕事に熱中するよりむしろ手を抜く方法を考えることが多いからです。
勿論、会社が期待する成果を出していれば問題はありません。しかし孫子は、平凡な兵士も英雄のような獅子奮迅の活躍をする条件を整えることを目指すべきだと言っています。逆に言えば、あまり真剣に仕事に打ち込んでいない部下の姿にイライラしているのは、実は会社や上司が職場環境を正しく整えていないことが理由かもしれないのです。
孫子は「窮地に立たせる」と書いていますが、社員を追い込むのではありません。社員がやらざるを得ない状況に置き、仕事に真剣に向き合える場を創ることがポイントです。

職場のチームを勢いに載せるリーダーたれ
また孫子は、職場のチームを勢いに乗せるリーダーになることを勧めています。勢いのある職場に入れば、大抵の人はその場の活気に流されて元気になり、自ら積極的に動き出すことになるのです。個人の奮起に期待するより、チーム自体を勢いのあるものにするリーダーの指導こそが大切なのです。
「戦上手は、なによりまず勢いに乗ることを重視し、一人ひとりの働きに過度の期待をかけない(中略)。勢いに乗れば、兵士は、坂道を転がる丸太や石のように、思いがけない力を発揮する」
よく言われることですが、動くことで成果が出る仕組みを作り上げることができれば、新人社員でも仕事が面白くなるものです。最初は仕組みで成果が出るのだとしても、自らの行動に対して自信を深めていくプラスの経験ができるからです。
そのためリーダーは「勝てる戦場」に部下を連れていく必要があります。この連載を通じて、孫子がいかに戦場を慎重に選んでいるかを解説してきましたが、戦うべき戦場を巧みに選び、兵士が戦果を挙げることに自信を深めるようにできるリーダーは、自軍に勢いを生み出し、それに部下を巻き込んで勝利を重ねることができるのです。
さらに孫子は組織を効果的に率いる3つの要素を提示しています。
(1)乱を治に変える「統率力」
(2)怯を勇に変える「勢い」
(3)弱を強に変える「態勢」
この3つはある種、舞台装置のようなものでその上に乗ることで、平凡な兵士も勇者のように戦う者に成長していくことになるのです。上司が部下を「あいつは使えない」と判断するとき、実は上司である自分自身が正しく職場の環境を整備していないことが原因かもしれないのです。
「統率力」とは、万一の場合や問題が発生した時の対処法を予め決定し、組織内に行動様式として浸透させておくことです。これにより「どうしていいかわからない!」という混乱を事前に避け、問題を粛々と解決することが可能になるのです。
「勢い」とは小さな成功を体験させることで自信を生み出し、自分にはできる、次も乗り越えることができるという信念を育んでいくことです。小さな成功と勝利を、ステップを踏んで体験させていくのです。
「態勢」とは、経験を積むことで成長を促す仕事を任せることです。会社側、上司が勝てる戦場を選び出し、進むべき場所を明示しておく。勝てる体制を作り上げておくことが、弱兵を強兵に変えていくきっかけとなるのです。

常勝軍団をつくりあげる3つのポイント
このように見ると、孫子は個人の才能だけに依存するのではなく、上司や組織が勝てる環境を作り上げることで、平凡な兵士を勇敢な兵士に自然に育て上げることが可能になることを指摘しています。ビジネスにおいても入社した人材が自然に育つ環境を作り上げることが、個人を叱責したり怒鳴り散らしたりするより、はるかに効果が高いのです。
個人に才能を求めすぎると、上司や企業は優れた環境を作り上げることを怠りがちになります。優秀な人の採用ばかりに注目している会社も、環境が勢いを創り出すことを忘れがちになります。孫子は、戦果を個人の適性だけに求めてしまうのではなく、指導者の環境整備の力に見出しているのです。
【常勝する軍団の3つのポイント】
・成果を上げることに必死にさせる
・仕事に熱中させること
・熱中し、必死に戦うチームをチャンスに殺到させる
もう一つ、孫子の組織論で忘れてはいけない点は「下に丸投げで成果を上げる」という発想とは180度違うことです。
君主、将軍を含めたマネジメント側は、部下が成長し勝利できる戦場を見極め、仕事の成果に必死、夢中になる環境の整備という重要な役割を担っています。そのため、正しい仕事の与え方こそが部下の才能と努力を200%引き出す基本となっていることは、部下が1人でもいる上司は心に留めておく必要があるでしょう。

⑨ 「小さな勝利で終わる人」と「大きな勝利を掴む人」の決定的な違い
新たな勝利につながる勝ち方こそが重要
「敵に勝ちて強を益す」つまり、勝ってますます強くなる。孫子の第2編「作戦」に出てくる言葉です。手柄をたてた兵士は、きちんと表彰する。捕獲した戦車は、味方の旗に変えて活用する。一つの勝利を、次の勝利に結びつけることを孫子はなにより重視したのです。
小さな成功が、部下の自尊心を高めることにつながっているか。チームの結束の強化につながっているか。今回の成功から、新たに何かを学んでいるか。これらは、次の成功を生むために必要な確認事項です。
さらに、味方が増える勝ち方をしているか、という点も大切です。成功することで、周囲に恨まれたり、反感を持たれていないか。勝ちを積み重ねるには、味方が増えていく勝ち方をしているかが重要なのです。
「俘虜にした敵兵は手厚くもてなして自軍に編入するがよい」
恨みを増幅しない勝ち方をすれば、昨日の敵を今日の味方にすることは、より簡単になるのは間違いありません。
「兵は拙速を重んじる」の言葉も、短期決戦を重視した孫子の姿勢を示しています。相争い、対決する時間は短ければ短いほど恨みが残りません。同様に、味方に恨まれない勝ち方も大切です。
「戦争で国力が疲弊するのは、軍需物資を遠方まで輸送しなければならないからである。したがって、それだけ人民の負担が重くなる。また、軍の駐屯地では、物価の騰貴を招く。物価が騰貴すれば、国民の生活は困窮し、租税負担の重さに苦しむ」
戦争で国民の負担が増して困窮すれば、かならず不満が満ちてきます。それは次の戦争を反対する声になり、政権の中枢を揺り動かす火種になるでしょう。ビジネスでも、自社内で恨みの声が残るような戦い方、勝ち方をすべきではありません。
やがて足をひっぱり、どこかで大きな敗北につながるからです。小さな成功の中に、あなたが次の成功の芽を育てているかが重要です。目の前の成功だけに目を奪われると、小さな成功で逆に没落する危険があるのです。成功や勝利を、かならず次につなげ拡大する意識が大切です。
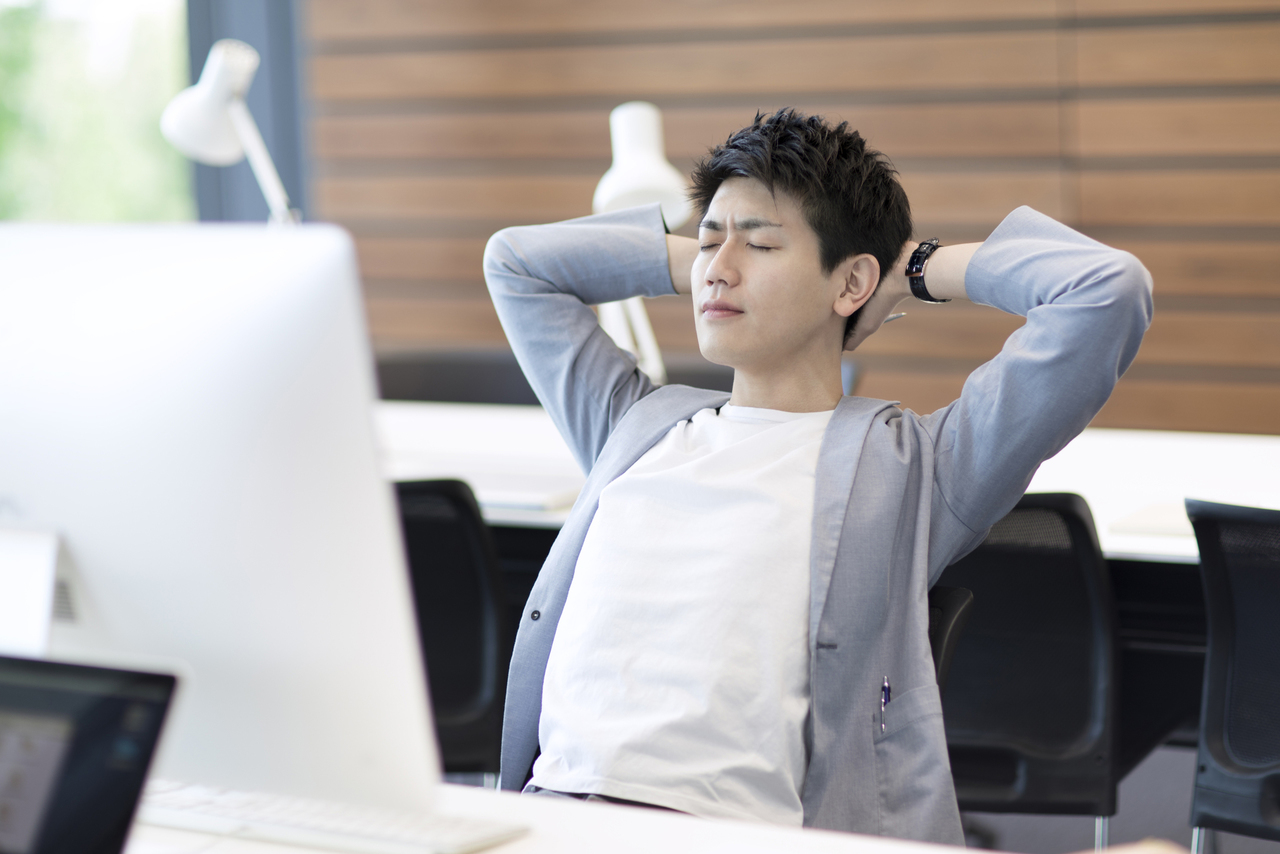
なぜ、目立たないことが大切なのか
小さな成功、少し儲かったなどの勝利があったとき。できるだけ目立たないように、周囲から浮かないようにすべきです。目立つことは周囲からの無用な詮索を生みます。次の成功と関係ない人間が寄ってくることにもなりかねません。
「誰にでもそれとわかるような勝ち方は、最善の勝利ではない。また、世間にもてはやされるような勝ち方も、最善の勝利とは言いがたい」
これは自然に勝つことを重視すべき、との孫子の指摘です。しかし同時に、勝ち続けるには一つの勝利が目立たないほうがよいとも理解できます。目立つことは、本来なかった向かい風を生み出す可能性があるからです。
あの企業が上手くいっている、あの社長が儲けている。このような話しが話題になるとき、尾ひれがついて伝わることが多いです。結果としていらぬ誤解を生み、人からうらやましがられたり、反感を買うことになる。
周囲の人たちにチヤホヤされるのが最終目標でない限り、目立たないことです。小さな勝利を当たり前に生み出せるくらいになるまで、じっと静かにしているのです。次の勝利を生み出すエネルギーを、他のことに取られてしまわないためにもです。
私たちが勝利を見せびらかすべきでない理由。それは、勝利を他社に真似られたり、利益を奪われる危険を避けるためでもあります。小さな成功で目立ち、あなたの成功要因が詳細に知れ渡った場合。当たり前ですが、誰かが必ず真似をしようと行動を始めます。
これではせっかく生み出した自社の成功の方程式も、長く効果を発揮しません。あっという間に、同じ池に釣り竿を垂れる人が殺到するようになるからです。

小さな勝利を大きな勝利につなげるには
「敵の態勢に応じて勝利を収めるやり方は、一般の人にはとうてい理解できない。かれらは、味方のとった戦争態勢が勝利をもたらしたことは理解できても、それがどのように運用されて勝利を収めるに至ったのかまではわからない」
上記の言葉は、第六編「虚実」の中にあります。ここでは「無形」すなわち形がないことの重要性を述べています。勝ったのち、次の勝利はさらに勝った理由がわからないようにすべきです。より自然に、より当たり前に、より努力が見えない勝ち方をするのです。
勝つことで、さらに賢い勝利を目指す。これを重ねると、勝利を続けているのに、やがて模倣者が生まれなくなります。あなたがどうして成功しているか、誰にもわからなくなったからです。 結局、敗者は小さな成功を思い上がりの入り口にしてしまいます。勝者は常に、勝利を新たな成長の糧にしているのです。この違いが積み重なると巨大な差を生み出します。
・勝利のたびに、自分の周囲の人材に感謝をしているか。
・勝利のたびに、自分の能力を過信して思い上がるか。
前者は勝利を、新しい挑戦に手を伸ばす基礎にすることができます。後者は勝利を、より大きな悲劇を生む落とし穴にしているのです。孫子は常に「最終目標を忘れるな」と説いたことを思い出してください。小さな勝利は、あなたが思い上がるためのものなのか。
それとも、本当に達成したい夢のための第一歩なのか。小さな勝利を、より大きな勝利につなげるにはどうすべきか。手にした勝利を前に、自分を賢く管理することこそ、最も大切な孫子の教えなのです。

孫子の名言 10選
孫子は『孫子の兵法』とも呼ばれ、元々は中国の春秋時代に活躍した兵法家 孫文 が記したものとされています。孫子は2500年以上前の書物ですが、その内容は現代でも十分通用するものが多く、様々な教訓を示唆してくれます。
- 1孫子の名言1:「兵は詭道なり」
(へいはきどうなり)
孫子の兵法の第一章「計篇」の一節で、「戦争とは騙し合いである」という意味です。
- 2孫子の名言2:「算多きは勝ち、算少なきは勝たず」
(さんおおきはかち、さん少なきは勝たず)
孫子の兵法の第一章「計篇」の一節で、「勝利の条件が多い方は実践でも勝利するし、勝利の条件が少ない方は実践でも敗北する」という意味です。
- 3孫子の名言3:「百戦百勝は善の善なる者に非ず」
(ひゃくせんひゃくしょうは、ぜんのぜんなるものにあらず)
孫子の兵法の第三章「諜攻篇」の一節で、「百回戦って百回勝つのが最善ではない。戦わずして勝つのが最善である」という意味です。
- 4孫子の名言4:「彼を知り己を知れば百戦して殆うからず」
(かれをしりおのれをしれば、ひゃくせんしてあやうからず)
孫子の兵法の第三章「諜攻篇」の一節で、「敵の実情を知り、己の実情を知っていれば、百回戦っても敗れることがない」という意味です。
- 5孫子の名言5:「善く戦う者は、勝ち易きに勝つ者なり」
(よくたたかうものは、かちやすきにかつものなり)
孫子の兵法の第三章「諜攻篇」の一節で、「戦い上手と呼ばれた人は、勝ちやすい状況で勝つべくして勝った人たちである」という意味です。
- 6孫子の名言6:「戦いは、正を以って合し、奇を以って勝つ」
(たたかいは、せいをもってごうし、きをもってかつ)
孫子の兵法の第五章「勢篇」の一節で、「戦いとは、正攻法を用いて敵と対峙し、奇策を巡らせて勝つものである」という意味です。
- 7孫子の名言7:「人を致して人に人に致されず」
(ひとにいたして、ひとにいたされず)
孫子の兵法の第六章「虚実篇」の一節で、「戦巧者は、自分が主導権を取り、相手のペースで動かされない」という意味です。
- 8孫子の名言8:「実を避けて虚を撃つ」
(じつをさけて、きょをうつ)
孫子の兵法の第六章「虚実篇」の一節で、「敵が備えをする「実」の部分を避けて、備えが手薄な「虚」の部分を攻撃する」という意味です。
- 9孫子の名言9:「囲師には必ず闕く」
(いしにはかならずかく)
孫子の兵法の第七章「軍争篇」の一節で、「包囲した敵軍には逃げ道を開けておき、窮地に追い込まれた敵軍を攻撃し続けてはならない」という意味です。
- 10孫子の名言10:「先ずその愛する所を奪わば、即ち聴かん」
(まずそのあいするところをうばわば、すなわちきかん)
孫子の兵法の第十一章「九地篇」の一節で、「まず敵が大切にしているものを奪取すれば、敵はこちらの思いどおりにできる」という意味です。
2023年06月30日
一緒にご覧いただいているページ
ご相談・お問い合わせはこちら(無料)
コンサルティングのご依頼や、詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。ご相談は勿論、無料です。
お問い合せフォームでのお問合せは24時間受け付けております。
サイドメニュー
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー
Executive Consultant
清水 一郎
-------------------------------------
<専門分野>
経営再建、企業再生、経営戦略、営業戦略、マーケティング、間接部門改革、法務、財務、金融、会計、税務、監査、事業承継、IPO、資産運用、不動産、組織構築、人事制度、人事評価制度、目標管理制度
-------------------------------------