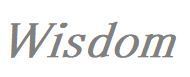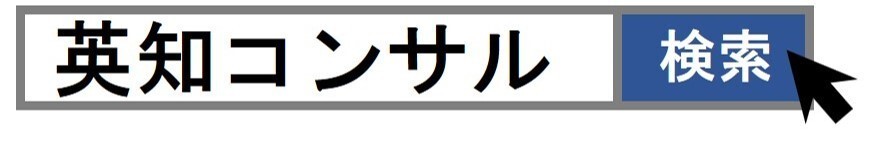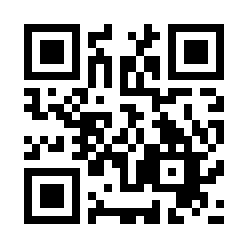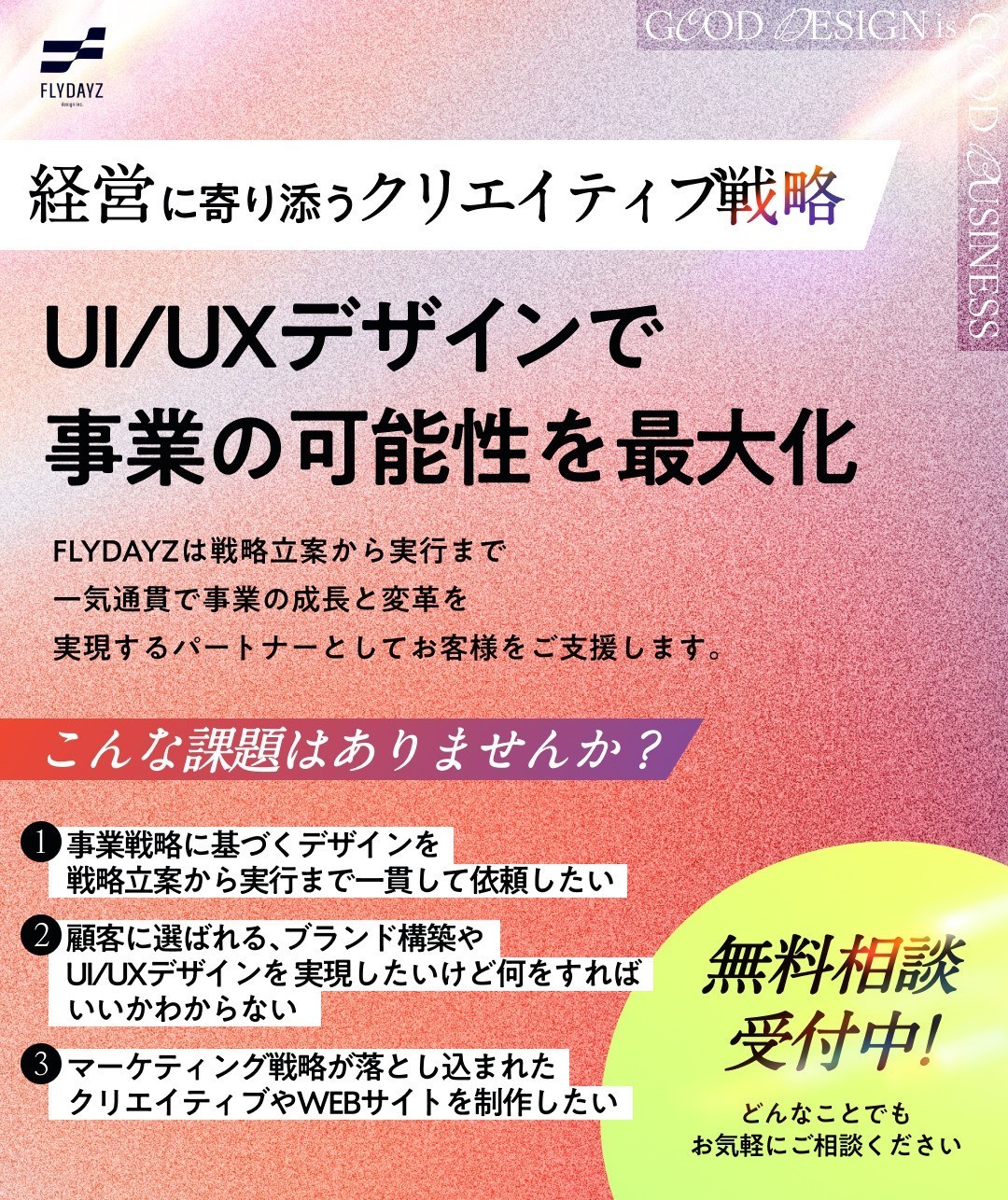中小企業・小規模事業者の経営コンサルティングは東京の英知コンサルティング株式会社(全国対応)
最終更新日 2024年06月23日
孫子の兵法から帝王学を学ぶ
孫子の兵法から帝王学を学ぶ。ビルゲイツや孫正義は「孫子の兵法」から、帝王学を学び、ビジネスを成功させています。
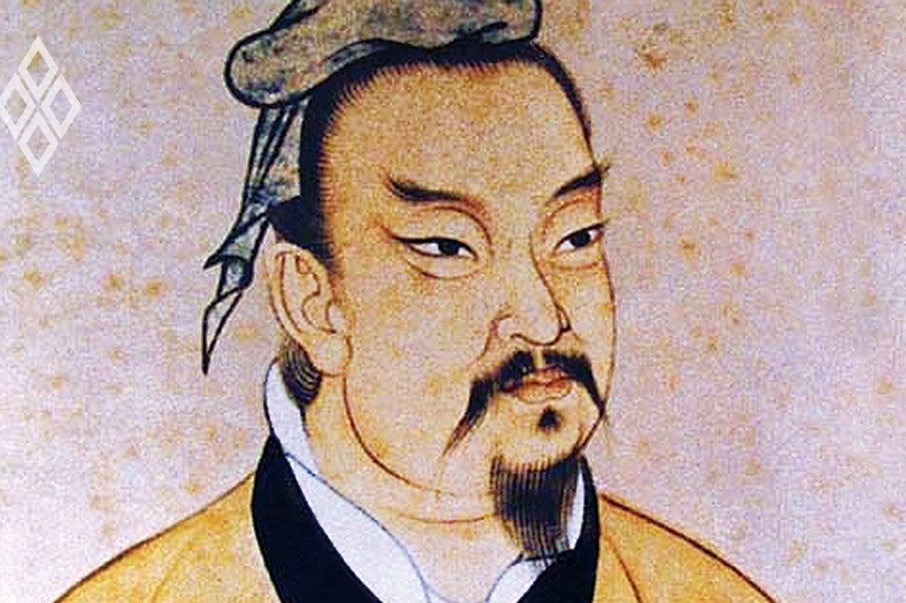
④ 孫正義は『孫子』から何を学んだのか
「孫の二乗の法則」を創った孫正義
孫正義氏は、1981年にソフトバンク株式会社を創業。同社は現在、国内の時価総額でトヨタ自動車に次いで2位、携帯通信事業者として世界3位の売上高を誇ります。グループの全従業員数は約7万人。創業からわずか35年間でこの成功を生み出した孫氏は、東洋のビル・ゲイツともウォーレン・バフェットとも言われています。
孫氏は有名な「孫の二乗の法則」として。25文字の事業戦略を20代半ばで創り上げています。詳細は書籍『孫の二乗の法則』などを見て頂きたいですが、内容の半分程度が孫子から、残りの半分を孫正義氏が創り出して現代ビジネスに当てはまるようになっています。
理念=道点地将法(どうてんちしょうほう)
ビジョン=頂情略七闘(ちょうじょうりやくしちとう)
戦略=一流攻守群(いちりゅうごうしゅぐん)
将の心得=智信仁勇厳(ちしんじんゆうげん)
戦術=風林火山海(ふうりんかざんかい)
「いままで僕は数千冊の本を読んで、あらゆる体験、試練を受けて、この二十五文字で、これを達成すれば、到達すれば、僕はリーダーシップを発揮できる。後継者になれる、本当の統治者になれるというふうに心底思っている」
上記は、孫氏の後継者を育成する「ソフトバンクアカデミア」の開校式の講義での言葉ですが、日本の枠を飛び越えて世界的な企業をわずが35年間で創り上げた人物が、20代半ばから孫子の兵法をビジネスに深く応用していたことがわかります。
多くの試練を潜り抜けながらも、ソフトバンク株式会社が急成長した姿は、戦国時代を駆け抜け覇者になった国家を連想させます。孫正義氏の活躍を見て、2,500年前の『孫子』が古いとは、誰もいうことができないと思われるのです。
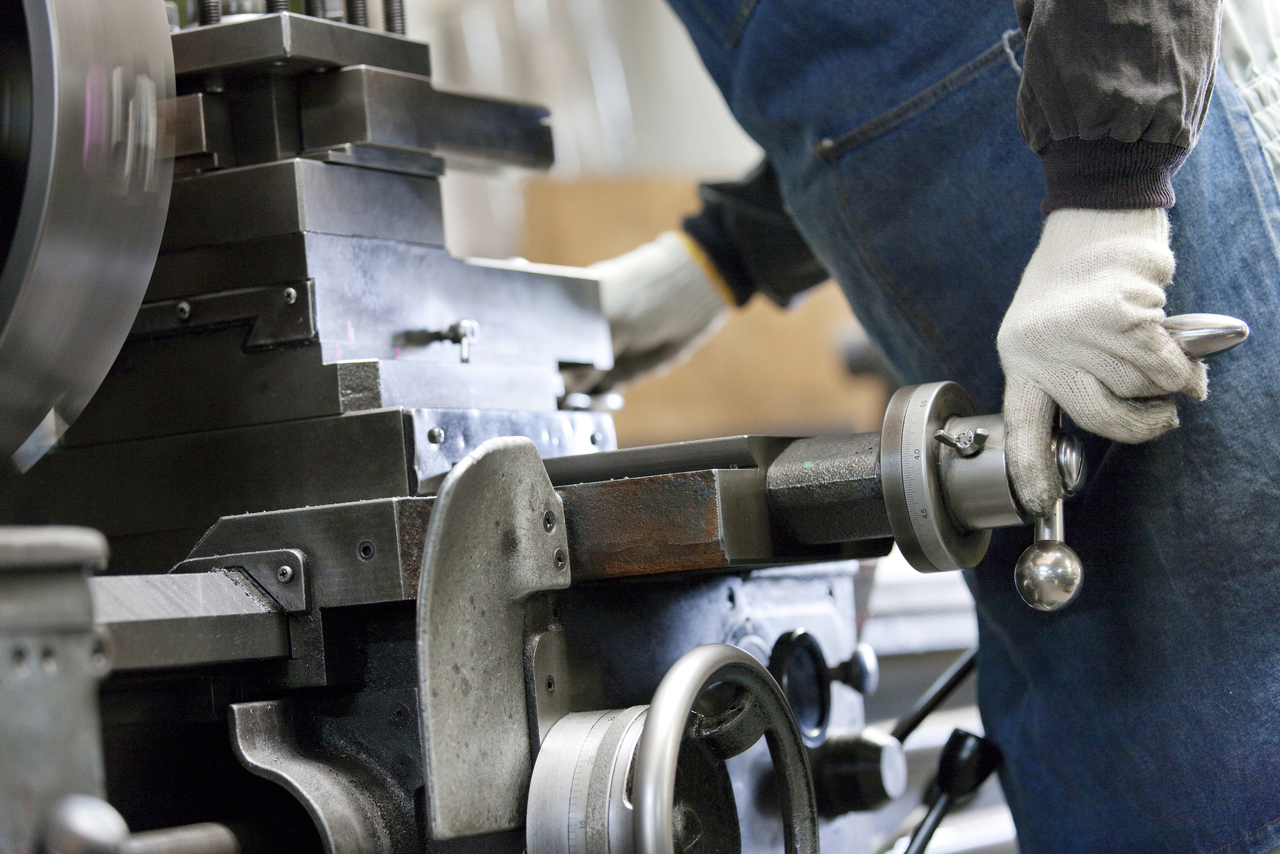
勝利を仕組化し、優れた人材を抜擢
徹底して勝利を仕組化し、危うい幸運によるまぐれな勝ち方ではなく、盤石の態勢を持つことによる本来の勝ち方を目指す。『孫子』と正義氏の思想には、勝負に対するある種の共通点が見受けられます。また、優れた人材を吸収し全軍を勝利に導く「将」の存在をクローズアップしている点も、極めて似通っています。正義氏は「将」について以下のように語っています。
「どんな戦いをやるにおいても、優れた将を得なければ大きな成功はできない。(中略)皆さんを支える優れた将を最低でも十人、皆さんのために、場合によっては腕の一本、足の一本をいらんと、場合によっては命さえもいらないというぐらいの志を共有する、そういう将を皆さんがどれだけ部下に持てるかと。これが皆さんが大将の器として、山を引っ張れるかどうかというようなことになる」
実際、正義氏はビジネスの節目、小さなベンチャーから台頭する過程で、出会ったビジネスマンの中で特に優秀な人を見つけ抜擢、勝負の最前線で重要な役割を担わせてきました。現SBIホールディングス代表取締役社長である北尾吉孝氏も、野村証券在籍時にソフトバンクの株式公開を担当したことで、正義氏と知り合い、ヘッドハントされた一人です。
正義氏は、単に優れた人材に仕事を任せるだけではなく、抜擢した人材が全力を発揮できるように、常に舞台管理をおこない「将」を挑戦の矢面に正しく立たせる配慮をしています。
これも孫子の兵法に一致し、組織を一丸となって勝利に向かわせる基本と同じです。ある意味、2,500年前の孫子の兵法を、漏れることなく適切に使いこなす姿には、勝利へのあくなき執念を感じさせ、「兵は国の大事である」という孫子の基本理念に極めて忠実なビジネスを展開してきたともいえるのではないでしょうか。

ソフトバンクがマルチブランド化を目指す理由
孫子の第七「軍争編」にある“風林火山”について、よく見ると孫正義氏の「風林火山海」には、最後に「海」の一文字が追加されています。
「疾風のように行動するかと思えば、林のように静まりかえる。燃えさかる火のように襲撃すると思えば、山のごとく微動だにしない。暗闇に身をひそめたかと思えば、万雷のようにとどろきわたる」
上記の孫子の文言を受けての、正義氏のバージョンアップの理由はユニークで思慮に飛んでいます。戦いに、勝者として勝つだけでなく戦いを収める「海」のような存在を目指すことを採り入れているのです。
「「風林火山」の戦いが終わると、戦場は死屍累々としている。しかし、焼け野原のままではそこからまた新たな戦いが始まってしまう。勝者が、広い、深い、静かな海のように、すべてを飲み込んで、天下を平定して初めて戦いが終わる」
正義氏は、単一事業ではなく「企業群」「マルチブランド」にも信念を持って取り組んでいます。例えば30年程度の寿命で考えるなら、シンブルブランドで一事業に専念するほうが効率的なのですが、時代を超えて成長を続けるためには「マルチブランドを持つ企業グループ」であることが不可欠との考えで事業を進めてきたのです。
ソフトバンクという稀に見る成長を成し遂げた企業と、創業者である孫正義氏。その行動理念と実際の戦いの姿は、「孫子の兵法」を現代ビジネスに縦横無尽に使いこなす君主をイメージさせます。また極めて果敢な挑戦をしながらも、その裏では事業リスクを極限まで減らしていく工夫を常に怠らないことも、「不敗をもっとも大切なものとする」孫子の兵法の思想と完全に一致しているのです。

『孫子の兵法』の要点
①「戦いについて」
『孫子の兵法』では、戦いはできるだけ避け、戦わずに相手を従えることを優先し、戦わざるを得ない時でも味方の国力を削らないよう短期に終えるべきとされています。
- 1戦いは騙し合いで、本当はできることでもできないように見せかけるし、必要であっても必要でないふりをする。
- 2最低限の目的だけを達成する短期決戦が有効なことがあっても、多くの目的を叶えようとする長期戦が有効であったことはない。戦いに勝つことは確かに必要だが、長期戦になることは避けなければならない。
- 3戦利品は自国に組み入れて戦力を増強する。捕虜にした兵は待遇を良くして味方に組み入れる。敵に勝ちながら、味方の体力を増強させなければならない。
- 4相手を傷つけずに降伏させることが一番重要で、戦いに勝っても相手を相手を打ち破るのは次善の策である。百回戦って百回勝つことよりも、戦わずして勝つのが最善である。
- 5戦うべき時と闘って波いけない時を知る者は勝つ。十分に準備し、準備できてない相手を待ち構える者は勝つ。
- 6戦いは迅速が第一である。相手の準備が整わないうちに、思いがけない方法を使い、備えていない場所を攻撃すべきである。
- 7戦いで大切な点は、敵の意図を正しく把握することである。

⑤ なぜ、個人の努力より「機会の大きさ」が
成功を左右するのか
ジカンの使い方を考えることが、孫子の時間術ではない
時間術といえば、24時間の中でどのように効果的に時間を使うか、ということが大抵テーマになっています。典型的な例では通勤電車で読書をしたり語学の勉強をしたり、といったところでしょうか。時間効率を少しでも向上する知恵を教えてくれる書籍は、書店に行けばたくさんありますし、実際にメリットのあるノウハウも多い物です。
実は孫子にも時間術が描かれています。しかしそれは、私たちが考える時間の有効活用ではありません。時間を活用するのではなく、自らの外にある機会を捉えるための時間の使い方なのです。
「勝機を見出したときは、すかさず攻勢に転じなければならない」
「攻めにまわったときはすかさず攻めたてて、敵に守りの余裕を与えない」
孫子が時間において意識しているのは「機会をモノにするための時間の使い方」です。機会に焦点を当て、時間そのものに焦点を当てているわけではありません。時間の有効活用とは、仕事のある人が夜にコンビニでアルバイトのかけもちをするようなものです。
一方の機会の有効活用とは、これから売れる商品やサービスを探し、自分の部署の仕事にとり入れたり、待遇をアップできる勢いのある環境に転職を成功させることです。
孫子は自らの外にある、戦場にある勝機を徹底活用するために時間を管理すべきだと言いました。それは、細切れの時間を少しでも活用しようとするのではなく、自らの外にあるチャンスに常に目を見開いておけ!という兵法独自の強烈なメッセージなのです。

主導権がある時間、ない時間を明確に意識せよ
物事を変えるには、戦場にある3つの時間帯を明確に意識する必要があります。
(1)主導権がまだ定まっていないとき
(2)実際の戦闘
(3)戦闘の結果、大勢が決定したとき
主導権がまだ定まっていないときとは、プロジェクトリーダーを探しているときです。誰かが手を挙げて、大きな存在感を示すことができればリーダーになれるときです。営業なら、提案見積りがまだ募集されている時期です。恋愛なら、意中の人がまだ誰とも交際していない時期です。実際の戦闘とは、決定したチームで活動をするときです。
そして大勢の決定とは、どこの企業が受注するか決定した時です。恋愛であれば、意中の人に特定の相手が決まったときです。上記3つの時間区分を見れば明白なのは、主導権がまだ定まっていない時期に、どれほど時間密度を高めることができるかが勝負だということです。
この時間帯を意識して勝負をかけることで、残りの時間帯の成果が完全に決まるからです。プロジェクトのリーダーが決定したあと、あなたが立候補しても変わりません。意中の人が恋人や結婚相手を決めたあとでは、あなたの熱意は届きません。孫子は主導権が宙に浮いているときに、驚くべき速さを発揮せよと主張しているのです。
時間の活用に焦点を合わせている人は、時間の有効活用ができている一方で、自分の外にある機会に鈍感だったりします。時間を活用することに精いっぱいで、外に目を見開いていることができないのです。
時間の活用を、夜にコンビニでアルバイトするようなものだと先に書きましたが、24時間を有効活用する「時間活用術」のもたらすプラスにはおのずと限界があります。一方で、人生に成功している人は機会のレバレッジで大きく飛躍をしているのです。
孫子の時間術が「機会」に焦点を合わせてことからもわかるように、時間効率ではなく「機会を増やす」行動は、そのまま人生の時間の活用になるのです。
部下に仕事の成果が上がらない状態を与え続けていることは、チーム全体の時間を殺しているようなものです。彼らが成果を高い確率で挙げられるように、営業体制を変えたり説明資料を改善することは、チーム全員の時間効率を高めることになるのです。

負け組は時間について驚くほど無知である
孫子を読み解いていく過程でわかるのは、敗者というものが時間について驚くほど無知であるということです。戦場の3つの時間帯の区別を勝者が驚くほど強く意識している一方、敗者は誰かに主導権をにぎられたあとで、泣き言のようなことを言い続けるのです。
当たり前ですが、主導権を握るものがそのあとの長い時間、成功と幸せを手に入れます。あの仕事がしたかった、と言ってもすでに担当者は別人で決まっています。あの人が好きだった、と言ってもすでに別人と結婚しているのです。孫子の時間術は、そのまま人生の成功者の行動と直結していると言えるのです。
孫子の時間術は「時間活用」ではなく「機会活用」だと理解できたなら、私たちの日々には大きなチャンスがあることがわかります。例えば、年齢を重ねると時間が少なくなりますが、社会にある機会そのものが減るわけではありません。目を向ける対象をかえることで、人生をいつのタイミングからでも輝かせることができるからです。
ケンタッキーフライドチキンで有名な、カーネル・サンダースは60歳前後でそれまで成功してきた店を売却しています。幹線道路にあるガソリンスタンドに併設されていた彼のお店はチキンの美味しさで有名でしたが、高速道路ができたことで車の通りが完全に途絶え、借金の返済のためお店を売却したのです。
しかしサンダースの手元にはほとんどお金が残りませんでした(なんという不運でしょうか!)。普通、60歳といえば人生の総括をする時間帯です。その時間帯でほとんど無一文になってしまったら、たいていの人は嘆くことしかできないでしょう。これから老後を楽しむ資産を作るには時間が足りなさすぎるからです。
ところがサンダースは、人気の高かった自分のフライドチキンの製法を教えるフランチャイズを展開。製法を教えた店の売上から、一定の割合をもらうビジネスを開始します。なんと店を売却してから10年もたたずに、サンダースのフランチャイズ店は600店舗を超えていました。
もしサンダースが「時間の活用」だけに焦点を合わせていたら、老齢期に入った自分の境遇に簡単に絶望していたでしょう。彼は孫子の時間術と同じく、機会の活用に焦点を合わせたことで、私たちの社会にその名を残すほどの成功を収め、裕福な成功者として90歳まで長生きし、大きな達成感と共にこの世を去ることになったのです。

『孫子の兵法』の要点
②「用兵について」
まず相手と自分の実情を分析した上で、勝てる条件を整えることが重要で、勝てる条件が揃わない場合は、戦いに臨むべきではないというのが『孫子の兵法』の考え方です。
- 1用兵の原則は、味方の兵力が敵の十倍であれば包囲し、五倍なら攻撃し、倍なら敵を分断し、対等なら士気を上げて戦い、敵に劣れば退却し、敵が圧倒的であれば戦いを避かくれる。兵力が大きく劣っているのに強きで挑んでも、敵の捕虜になるだけである。
- 2相手の実情を知り、自分の実情を知っていれば、百回戦っても負けることはない。
- 3勝つ軍は戦う前にまず勝つ条件を整えてから戦いを始めるが、負ける軍は戦いを始め何とか勝とうとする。
- 4優れた兵法家は、軍の勢いを求めるが、個々人の力を求めることはない。自分が主導権を取り、相手のペースに巻き込まれない。自分の意図を隠して相手に態勢をとらせるため、自分たちは兵力を集中できるが、相手は全ての可能性に備えようとして兵力を分散し、手薄な部分ができる。
- 5用兵は相手の裏をかくことが基本で、損得勘定を計算しながら動く。
- 6知恵のある者は、ある一つのことを考える時にもメリット・デメリットの両面から洞察する。利益になる事柄にデメリットの側面を加えて考えることで、狙い通りに達成できるし、マイナスとなる事柄にメリットを加えることで不安を消すことができる。
- 7相手が大切にしているものを奪取すれば、相手を自分の思い通りにできる。

⑥ なぜ「できる人」より「好かれる人」が出世するのか
能力が高いことより、嫌われないことが重要
高峰の戦略書として世界に知られる孫子は、現代人にとって多くの名言を残した存在でもあります。「兵は拙速を重んじる」なども有名ですが、「はじめは処女のごとく」で始まる言葉も、私たちの教養的な知識といってよいでしょう。
この言葉は勿論、処女の演技を推奨するものではなく、相手の隙を作り上げる作戦の効果と重要性を指摘したものです。例えばダッシュするウサギのような突撃力を持っていても、相手があなたの攻撃を十二分に警戒し、守りを鉄壁のように固めていれば威力は半減してしまいます。逆に相手が無防備であるほど、あなたの攻撃の威力は倍増するのです。
「要するに、最初は処女のように振る舞って敵の油断を誘うことだ。そこを脱兎のごとき勢いで攻めたてれば、敵はどう頑張っても防ぎきることはできない」
この言葉を考える時、ビジネスパーソンへの教訓として「純粋に能力が高いことより、嫌われないことのほうが重要」とよく言われる理由がわかります。何らかの学歴や肩書、能力を鼻にかけて相手に嫌われるような態度を取れば、結果としてこちらの提案や商品、メッセージを相手が受け入れなくなるからです。
別の視点で考えるなら「嫌われないこと」「好かれること」自体、ビジネスで効果を発揮する一つの才能ともいえるでしょう。相手が心を開いてくれるなら、あなたの提案はより心に響きやすくなるのは当然のことです。
上司であれば、部下があなたの指示を素直に聞き入れて行動する人間関係を作り上げておくことです。それは時に、優れた指示能力以上に必要な行為といってよいでしょう。

仕事のできる人は、周囲の警戒や反発を避ける
優れたカウンセラーは、相談者の話しの中で相手への回答がすぐにわかっても、相手が話しを終えるまで静かに待つものです。理由は相手が心を開き「この人は自分の話しを親身に聞いてくれる人だ」と理解を得ることで、カウンセラーのアドバイスがよりスムーズに相手に浸透することになるからです。
社内でも、具体的な成果以外のところで目立ちすぎるのは考えものです。常に注目を浴びていれば、ライバル視する人たちや妬みがやがて生まれるからです。それが特に自分の上司や肩書で上の人たちも含まれると、問題はやっかいになります。自分を追い越す存在だと思われたら、回してくれるはずのチャンスもあなたに巡ってこなくなるからです。
孫子を活用して仕事のできる人は、自分の武器を無用に振り回して周囲の警戒や反発を招くのではなく、感情の摩擦からくる損を正しく避けることができる人です。お互いを受け入れて、相手の長所を引出し、こちらを有効活用してもらう。
足を引っ張らずに協力して勝利を目指すならば、チームの力を何倍にも高めることが可能です。逆に高飛車に出たり相手の感情をむやみに逆なでする人は、本来なかった障害を、自分の前にいくつも持ってきてしまう損な道を歩むことになります。
「打つ手打つ手すべてが勝利に結びつき、万に一つの失敗もない。なぜなら、戦う前から負けている相手を敵として戦うからだ」
「勝つ」とは相手を打ち負かすだけでなく、好意的に受け入れてもらうことも意味します。敵意や警戒ではなく、周囲があなたに親近感と好意を抱いていればそれだけで仕事の成功に大きく近づきます。多くの仕事を成し遂げて社会的に高い地位にある人達が、一様に丁寧で腰が低いのは、幾多の経験から成功する要素を持ち合わせて発揮しているからだといえるでしょう。
あなたのプランなら必ず受け入れ実行すると周囲が考えているならば、打つ手打つ手は必ず勝利に結びつきます。お客様であれば、あなたの提案する商品なら間違いないと喜んで購入頂ける関係こそ、孫子の兵法が真に目指すところなのです。

常に目に見えない力が勝者を支えている
実は、相手の油断を誘う「はじめは処女のごとく」の言葉と、有名な「兵は拙速を重んじる」は効果としては同じものを求めています。相手にこちらの攻撃への準備・防備をさせないということです。ビジネスにおいて速さというのは、競合他社が準備を整える前に勝つことを意味します。
概算見積りの提出が、常に他社より早ければ「検討されないで負ける」ことはありえず、しかも他社の提案を見る前に受注できる可能性も高まります。早い見積りを評価する顧客は、納期の早さや手間のかからなさを喜ぶ傾向があるからです。
企業変革において、新しいリーダーの取るべき道は2つあります。一つは、どんなことが始まるかと警戒している社員をまず安心させること。
もう一つは、大きな方向転換を阻止しようとする古株の社員が抵抗の態勢を固める前に、断固とした方針を示して行動を開始することです。さらにリーダーは、社員が驚いている期間に一定以上の成果を生み出すことができれば最高です。自然と新リーダーに、皆が従う流れが形成されるからです。
孫子の指摘を振り返ると、何か成果を上げるためにとにかく「能力が高い」だけではなく、隠された別の道があることがわかります。
テストの点数や資格取得などと違い、人に好かれて嫌われない能力(社交的な人柄や優れた人間性)や、ずば抜けて速い実行力などは測ることや点数化が難しい能力です。しかしそのような能力こそ、実社会での勝者を支えている力なのです。
不思議にスルスルと出世階段を登っていける人、ふわふわした雰囲気で仕事をしているのになぜか顧客に好かれて信頼が厚く、大口の売り上げをいつも獲得している人など。
一見なんの脅威とも思えない能力が、実は自信満々の人間にはできない成功を成し遂げる力となる。孫子の指摘は、勝利への道はいくつも分かれており、正解は一つと思い込む視野の狭さこそが、勝者になれず負け続ける側の隠れた共通項だと示唆しているのです。

『孫子の兵法』の要点
③「トップと現場指揮官」
トップ(王)と現場指揮官(将軍)に求められる資質や行動についても『孫子の兵法』に記述されています。現代のビジネスシーンにピッタリの指摘です。
- 1現場指揮官はトップの補佐役である。現場指揮官がトップと親しくしていれば、その国は必ず強いが、現場指揮官とトップの間に溝があるなら、その国は弱い。
- 2現場指揮官が有能で、トップが余計な干渉をしなければ勝つ。上下の間で意思統一ができている者は勝つ。
- 3トップは現場の事情や業務内容をよく知らないのに干渉してはならない。現場が混乱し、トップへの疑いを生む。
- 4現場指揮官が弱腰で厳しさが無く、敵情を分析できず、命令も明確でなければ、組織は乱れて敗れる。
- 5現場指揮官は、物静かで思料深く、公明正大で自分をよく律しなければならない。
2023年05月03日
一緒にご覧いただいているページ
ご相談・お問い合わせはこちら(無料)
コンサルティングのご依頼や、詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。ご相談は勿論、無料です。
お問い合せフォームでのお問合せは24時間受け付けております。
サイドメニュー
代表取締役 社長兼CEO
代表パートナー
Executive Consultant
清水 一郎
-------------------------------------
<専門分野>
経営再建、企業再生、経営戦略、営業戦略、マーケティング、間接部門改革、法務、財務、金融、会計、税務、監査、事業承継、IPO、資産運用、不動産、組織構築、人事制度、人事評価制度、目標管理制度
-------------------------------------